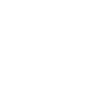Thinking Framework – 考える枠組み vol.2
2019/04/19
2. すべてのことはメッセージか

アメリカは私は何者であるというアイデンティティの国であり、私の主張はこうだというメッセージの国でもある。ドナルド・トランプの「Make America Great Again」という選挙のスローガン、Nikeの「Just Do It」や Appleの 「Think Different」のキャッチコピーは当然として、音楽界隈でもこうした メッセージが溢れている。
古くはウッディ・ガスリーのギターに書かれた「This Machine Kills Fascists」。なぜかノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの『Subterranean Homesick Blues』のミュージックビデオに見るメッセージボード(これはピチカート・ファイブのそのものずばり『メッセージソング』のミュージックビデオでも少しだけ引用されている)。最近 Vetementsがコピーして話題になったカート・コバーンのTシャツ「Corporate Magazine Still Suck」もそうだ。
「目にうつるすべてのことはメッセージ」と歌ったのは荒井由実で、この歌は小さい頃は感受性が高くすべてのものからメッセージを受けとることができたという受けて側の話だが、子供でなくても感受性がそれほどでなくても、すべてのものがメッセージを発している。それがアメリカという国だ。
アメリカがシンプルな言葉を使った直接的なメッセージで溢れているのであれば当然それを逆手にとった表現もある。60年代から活躍するアーティストであ るエド・ルシェはシンプルな言葉をキャンバスに描いているが明確なメッセージを意図的に排除した作品を制作してきた。「Japan Is America」のような戦後の日本を批評的に表したような鋭い作品もあるが、多くの作品は抽象的で多 義的であり言葉の意味性を曖昧にしている。
アンディー・ウォーホルの『129 Die in Jet!』は129人が飛行機で死んだと衝撃的な文字が飛び込むが、これは1962年に実際に起きた飛行機事故を報じた New York Mirrorの紙面をそのまま模写したものだ。シンプルで強い言葉が並びなんらかのメッセージを示したサインボードのようにも映るが、そこにある のはメッセージではなく揺るぎない事実だ。

言葉を使ったアーティストと言えば、バーバラ・クルーガーにも言及すべきだろ う。彼女の代表作であるデカルトの「I think, therefore I am(我思う、ゆえに我あり)」をもじった『I shop therefore I am』は消費主義を批判したメッセージ性の強い作品だ。しかしその赤のボックスに白のFuturaフォントを Supremeがロゴとしてコピーし、(もう誰も覚えていないと思うが佐藤可士和も スマップのキャンペーンでコピーしていた)商品として消費されることで、本 来の消費主義批判が消費主義賛歌のスローガンのようにも見える面白さがある。 私は買い物する、ゆえに私である。高額なブランド品を買う動機付けのマントラとして、メッセージは逆転する。
これら先人が行ってきた言葉とメッセージの関係の解体をさらに推し進めるの が、現行のアーティストであるLAのカリ・ソーンヒル・デウィットだ。彼の代表作である事件現場や動物、薬や札束などの強い写真の上と下に写真との関連 が不明確な一見ランダムとさえ思える強い言葉を配置したサインボードは、見る者の社会性や政治的な志向、過去の経験などを通じて様々な事象を思い起こさせる。そして、その強い写真と強い言葉の関連の不明確さに、本来そこにあ るはずのメッセージの不在に見る者は戸惑い揺さぶられる。

OFF-WHITEのヴァージル・アブローは、このメッセージなき言葉をファッションに持ち込む。Nikeの Air Forceや Air Maxという誰もが知っているアイコニックなスニーカーにダブルコーテーションで囲った”AIR”と書く意味の無さ。彼はカニエ・ウエストのアートディレクターとしてカニエのマーチャンダイズに 前出のカリを起用していることからも分かるように、メッセージとその意味性 については当然、意識的なのだろう。しかし、このHelveticaのボールドで綴られた大文字の世界が商品として乱用され THE CONVENIとタイプされると、メッセージの不在は商品のロゴとして隙間を埋めるだけの文字に変わる。もともと売りたい以外のメッセージの無いところにメッセージが無い言葉を置いても何も生まれないのだ。
本来メッセージがあるべきところにメッセージが無いという面白さを音楽に持 ち込む最新型がスウェーデンのViagra Boysだ。彼らのようにポストパンクや グランジといった音のバンドは、その多くが愛や生や死のようなシリアスなテーマを歌ってきた。あるいは歌っていると思わせてきた。そういった前提において Viagra Boysの『Sports』は Nirvanaの『Smells Like Teen Spirit』 のリフに乗せて、ベースボール、バスケットボールとスポーツの名前を山手線 ゲームのように列挙する。続くサビではただスポーツと連呼するだけだ。それはヴァージル・アブローが”SPORTS”と大文字でダブルコーテーションで囲いタイプするかのようにまるで意味を持たない。
しかし、本当に意味が無いのかというとそうでもなく色々な解釈が可能なようにも思える。例えば野球、バスケットボールとアメリカ産のスポーツから始まることには、商業化したアメリカ型のスポーツへの批評性を読み取ることができる。テニスコートを MVに使ったことは、元ネタのNirvanaのMVのバスケットボールコートのパロディーでもあると思うが、今や高所得者のスポーツである テニスや唐突に挿入されるWeiner dogs(ダックスフンド)にはイギリスへの、 バーベキューにはアメリカへの批判を感じる。これはロックの大国であるイギリスとアメリカに対するロック辺境の地スウェーデンからの一撃という受け取 り方も当然できるだろう。
また、歌詞を注意深く読んでみるとスポーツ名の列挙だけではなく、「裸の女の子たちと/裸の男たちが/ダンスして/ビーチに倒れこむ」というような映像的な表現もあれば「大麻を吸って/朝、ハイになり/インターネットで物を買う」という自身の行いを憂いたような私小説的な表現も見受けられる。スポーツの種目やスポーツの連呼と、その間に挟まれたこれらの写実的な表現との関連は不明確であり、本来そこにあるはずのメッセージもない。このスポーツの種目とスポーツの連呼を強い言葉、写実的な表現を強い写真とみなすと、この曲はカリのサインボードと同じ構造だということに気づく。そしてカリのサインボードと同じように、聞く者は様々な事象を思い起こされるのと同時にメッ セージの不在に戸惑い揺さぶられるのだ。
Text by Naohiro Nishikawa
category:COLUMN
RELATED
-
2019/04/11
Thinking Framework – 考える枠組み vol.1
1. 2018年代 by Daiki Miyama 現代史は10年を単位としたディケイド、つまり年代で区切られ語られることがある。特に音楽やファッションなどのカルチャーはその様式の記号として年代が使われる。このスネアのリバーブは80年代っぽいとか、このスニーカーのハイテク感は90年代っぽいといった具合に。 しかし変化の進みが早く多様な音楽やファッションの様式を10年という単位で区切るのは無理があるように思う。音楽で90年代と言って思い浮かべるのはグランジだろうか、アシッドジャズだろうか、それともドラムンベースだろうか。ファッションにおいてもそうだ。90年代に今につながるハイテクスニーカーの多くが発明されブームになったのは確かだ。ただ 90年代の足元がすべてハイテクスニーカーだったかというと、当然そんなことはなく、ドクターマーチンなどの定番はもちろん、レッドウイングのエンジニアブーツや UGGのムートンブーツなどもブームになりよく履かれていたように思う。 それでも、10年という区切りが有効な分野もある。そのひとつが進みの遅い音楽メディアの物理フォーマットだ。リスナーが音楽を安心して購買し収集できるようにするためには、音楽メディアの物理フォーマットはファッションのトレンドのようにシーズン毎に変わるわけにはいかない。 レコードブームと言われて久しい昨今だが、アメリカに端を発するレコードブームはがいつから起こったかを考えるとそれは 2008年頃であったように思う。アメリカのレコード会社の業界団体であるアメリカレコード協会(RIAA)のデータによると CDの登場により落ち続けたレコードの売上が初めてプラスに転じるのは 2008年からだ。 USでのレコードの売上枚数。濃い青はアルバムとEP、薄い青はシングル盤を示している。これを見ると90年代のレコードはシングルで成り立っていたことがわかる。参照元:https://www.riaa.com/u-s-sales-database/ その 2008年に何が起こったかを振り返ると Captured Tracks、Mexican Summer、Acéphale、Big Love, The Trilogy Tapesや PANなど今に繋がるインディーシーンを作り上げたインディーレーベルがこぞって設立されたのが、この年だということに気づく。その前後も含めると Italians Do It Better、Secred Bones、DAIS、Burgerなどが2007年で一年早く、Posh IsolationやR.I.P Societyが2009年となる。これらのインディーレーベルの主要なメディアがレコードであることを考えると、2008年から続くレコードブームは彼ら新興のインディーレーベルが主導したブームであると言えるのではないだろうか。 また、スマートフォンや音楽関連のサービスを眺めてみると、世界で最初のスマートフォンであるiPhoneが登場したのが 2007年で、日本ではじめて発売されたiPhone 3Gが2008年。対抗する Androidも2008年に登場している。インディーレーベル御用達の Soundcloudと Bandcampができたのは共に 2007年なので、2008年は今に続く環境が一通り揃った年だったとも言える。 本連載『Thinking Framework – 考える枠組み』では、今に続くレコードブーム/インディーシーンの起源である 2008年をひとつの時代の始まりと捉え2008年代と呼ぶことにする。そうすると 2018年は必然的に 2018年代という新しいディケイドの最初の一年ということになり、今年 2019年はそのディケイドの二年目ということになる。 これは自分だけではなく、多くの人に共感してもらえる感覚ではないかと思うのだけどここ1、2年で何かが大きく変わるんじゃないかというゲームチェンジの予兆みたいなものがある。『10年後から振り返ればここが節目だった』本連載では、そういった視点で現在を捉え、ひとつの目として感じたことを伝えていければと思う。今の時点で振り返れば2008年がいろいろな始まりであったように、2018年は今後の 10年の方向性を決定付ける新しいディケイドの始まりとして後年に記憶される年となるような何かを。 Text by Naohiro Nishikawa
-
2019/05/09
Thinking Framework – 考える枠組み vol.4
4. 内燃機関の哀しみ by Daiki Miyama 2017年7月、フランス政府がガソリンおよびディーゼルエンジン、つまり内燃機関を搭載した車の販売を2040年までに終了すると宣言した。イギリスもそれに呼応し同様の宣言を行った。車が個別に内燃機関で燃料を爆破させ運動エネルギーを得るよりも、発電所で燃料を燃やすなどし電気を作り車はモーターで走らせた方がエネルギー効率が高く、二酸化炭素の排出量を低減できるのが狙いだ。 この電気自動車への転換は環境問題に積極的な北欧や、車の生産に依存していない国だけでなく、自動車生産大国であるドイツまでもが内燃機関の自動車の販売を禁止する議論を始めている。つまり近い将来、内燃機関は蒸気機関や真空管のように失われた技術になるのだ。 ある技術が別の技術に取って代えられようとするとき、旧来の技術が異質な進化を遂げることがある。例えば SSDに取って代わることが宿命であるHDDが SMR(Shingled Magnetic Recording。データの書き込みを隣のトラックと瓦のように重ねて行うことによってデータの密度を上げて容量を上げる方式)によって延命を図ったように、内燃機関でもこれまで不可能とされた異質な技術が実用化されはじめている。日産の可変圧縮比エンジン『VC-T』やマツダの『SKYACTIV-X』がそれだ。 日産が開発した可変圧縮比エンジン『VC-T』は、燃費の向上とトルクの維持を両立させる技術だ。燃費の向上には燃料であるガソリンと空気の混合気の圧縮比を高める必要がある。しかし圧縮比を高めすぎると点火プラグで点火する前に混合気が部分的に爆発するノッキングが起こり、エンジンに異常な振動が発生し、最悪エンジンを壊すことにもなりかねない。このノッキングは発進や加速時などのエンジンの負荷が高いときに起こりやすく、一定の速度で走っているときには起こりにくいことが分かっている。であれば、発進や加速時だけ圧縮比を低くし、一定の速度のときに圧縮比を高めることができれば、ノッキングを防ぎ燃費を向上できる。これが可変圧縮エンジンの狙いで『VC-T』では動的にストロークの長さを変更することで圧縮比の変更を行っている。 動的にストロークの長さを変更と言うのは容易いが、ガソリンが爆発する力を全て受け止めるところに新たな部品を追加し、その角度をアクチュエータで電子制御することによってストロークの長さ変え圧縮比を変更する機構を製品化するまでに、日産は30年近い月日をかけている。このエンジンの研究は1989年に始まり、2018年の春に発売されたインフィニティのSUV『QX50』に初めて搭載された。 マツダの『SKYACTIV-X』も燃費の向上とトルクの維持の両立という目的は変わらないがアプローチは『VC-T』とかなり異なり、燃費の向上を混合気の自動着火に求めている。『VC-T』の説明では自動着火はノッキングの原因であり、ガソリンエンジンでは避けなけれならない現象であると述べたが、『SKYACTIV-X』では逆にその自動着火を利用し燃費向上を狙う。 通常の点火プラグでの混合気への点火は着火にムラができ、燃料の燃え残りが起こることによって燃費が低下する。着火にムラができる原因は紙の端についた火が全体に燃え広がるのに時間がかかるのと同じで、混合気が爆発しピストンを押すまでには全体に火が届かず、どうしても燃え残りができてしまうからだ。一方、自動着火は混合気の圧力と温度で決まる。燃焼室内の圧縮された混合気の圧力と温度はほとんど同じであるため、自動着火の条件は燃焼室内で同時に起こる。そのため燃え残りが非常に少なく燃料を効率よくエネルギーに変換することができるのだ。また、自動着火では点火プラグで火をつけるのとは異なり、混合気のガソリンの比率を下げることができる。これによりピストンを押し出すのにかかるガソリンの量も減らすことができ、さらに燃費を向上することができる。 燃費にとっては良いことずくめのように思える自動着火であるが、ガソリンでそれを制御し確実なタイミングで起こすのは実はとても難しい。その理由は自動着火が起こる温度と圧力の範囲が限られているからだ。『SKYACTIV-X』ではこの問題を解決するために、自動着火が起こらない温度のときはガソリンを噴射しプラグで着火するということを行う。燃料の消費を抑えたい巡航走行時に自動着火が起こるように燃料室の大きさを合わせることにより、発進時や加速時は点火プラグを使うとしても、安定した巡航走行の燃費を格段に向上することができる。 『SKYACTIV-X』を搭載した『Mazda 3』は今年の5月頃に世界で販売される予定である。『SKYACTIV-X』がモーターを付けたハイブリッドであることや、世界戦略車である『Mazda 3』の一部のグレードにしか搭載されないことで、その性能には懐疑的なところもあるが、世界を席巻したスモールセダンである『BMW 3シリーズ』になぞられたその名前の最高グレードに『SKYACTIV-X』を設定したことにマツダの本気度をうかがうことができる。 内燃機関にはこういった努力にもよらず最終的には失われてしまうという哀しみがある。しかし内燃機関が失われる技術だから哀しみがあるのかというと、それだけではないようにも思う。内燃機関には、燃料の爆発を閉じ込め運動エネルギーに変換するというその行為自体に、ある種の哀しみがあるように思えるのだ。 その内燃機関の本質的な哀しみを端的に表しているのが Blood Orangeの『Negro Swan』の一連のMVであり、特にそのジャケットにも使われた『Jewelry』のMVだ。 海外でのチューニングした日本車ブームの起源は90年代の終わりに西海岸で東洋系マフィアがはじめたものだと言われている。そこに日本のアフターパーツメーカーや自動車雑誌が便乗して日本のチューニング文化を持ち込み、映画『ワイルドスピード』の世界的なヒットもあり世界中に広まることになる。 現在の80年代、90年代の日本のスポーツカーの中古価格の高騰は、こうした文化的なものと、販売から25年以上経つ車は規制が緩和され新車では禁止されている右ハンドルの車も走ることができるというアメリカの「25年ルール」によるものが大きい。 『Jewelry』のMVに登場するスプリンタートレノは、こうしたチューニング文化を作りあげた源流とも言えるモデルであり、なかなか良い選択だと言える。特にこの個体は外見はペイントをやり直しているくらいでノーマルに近く、日本で当時流行した「つり革」や車検証を模したステッカーなどに日本のこの時代の車に対する強いこだわりが感じられる。 しかしAE86、しかも白と黒のいわゆるパンダトレノを使うのは、その流行をまじまじと見てきた我々には、あまりにも豆腐屋すぎる。いくらチューニング文化の源流であるとしてもここはS13型シルビアや FD3S型 RX-7あたりを選んで欲しかったところである。 内燃機関の哀しみをジャケットに使った最近のものとしてはMall BoyzのEP『MALL TAPE』がある。この『Higher』のMVにも登場するフォルクスワーゲンのポロはWRCでも活躍するヨーロッパで人気のホットハッチだ。 この個体はサイドに MALLと大きく書かれてはいるが、WRC的なレース仕様という訳ではなくほとんどノーマルに見える。それでも後部座席の窓には2013年から18年のWRCのチャンピオンのセバスチャン・オジェとジュリアン・イングラシアのステッカーがある。またユーロのようなナンバープレートの上に群馬ナンバーが重ねられている。 これを選ぶのが彼らのモール感であり、我々が郊外で実際に見るワンボックスやミニバンに支配された世界とは少し違う架空のモールなのだろう。それは彼らのジャージやサングラスがドンキホーテの前で見かけるリアリティーから少し離れたところにあるのと同じように、どこでもありそうでいて、どこでもない。特定のフッドを持たないという彼らの気分を良く表していると思う。 Text by Naohiro Nishikawa
-
2019/07/07
Thinking Framework – 考える枠組み vol.5
5. バーニング by Daiki Miyama 村上春樹の短編小説『納屋を焼く』を原作としたイ・チャンドンの『バーニング』は独特のトーンに覆われた静かで美しい映画だった。 原作は小説家であり妻帯者である物語の語り部となる<僕>と、たまにモデルの仕事をしているが自由人である年が一回り下の女の子<彼女>との都会的でカジュアルな関係から始まる。 あるとき彼女はバーのカウンターで僕と世間話をしながら、実際には無い蜜柑をむいて食べるパントマイムを行う。その動作に「まわりから現実感が吸い取られていくような」特別なものを感じ関心する僕に彼女は説明する「こんなの簡単よ。そこに蜜柑があると思いこむんじゃなくて、そこに蜜柑がないことを忘れればいいのよ」と。 「ない」ということを忘れる。この実在と非実在の関係がこの物語では重要なテーマとなる。 その後、親の遺産を手にした彼女はナイジェリアに長い旅行にでかけ、現地で知り合った日本人のボーイフレンドと帰国する。その貿易商を営んでいるらしい男が加わり物語は別の方向へ進み出す。 映画もこの実在と非実在の関係をテーマに原作と同じように物語が進む。ただ映画と原作では大きく異なるところがある。それは社会との関係であり距離の取り方だ。 村上春樹の作品群は、社会との関係によって大きく二つの期間*1 に分けることができる。最初はなるべく社会との関わりを持たないようにした期間で、デタッチメント期と呼ばれる。この期間は彼がデビューした1979年から1993年頃まで続く。長編で言うと『風の歌を聴け』から『国境の南、太陽の西』がこの期間に書かれた。次の期間は社会との関わりを積極的に持とうとした期間でコミットメント期と呼ばれる。コミットメント期は1994年頃から始まり現在も続いている。長編で言うと『ねじまき鳥クロニクル』からとなる。 原作の『納屋を焼く』は1983年に書かれたデタッチメント期の作品であり、80年代という時代性もあるが、現実の社会と切り離されたどこか浮世離れした世界の物語だ。それに対して映画は舞台を現在の韓国に移し、積極的に現実の社会と地続きである現在の韓国とその中で生きる若者を描こうとする。 物語の視点となる<僕>は小説家でもなければ妻帯者でもない。素朴な風貌の兵役帰りで小説家志望ではあるが、まだ何も書いていない無職の青年ジョンスに。<彼女>は年の離れた女の子ではなくジョンスの幼じみのヘミになる。二人の関係もカジュアルなものではなく、量販店のコンパニオンと客として再会するとすぐに恋仲となる。 ヘミがアフリカへの旅行中に知り合い一緒に帰国する男ベンだけは原作と同じ設定であるが、原作ではフラットであった僕ジョンスとの関係は映画では少し異なる。ジョンスがニートのような生活をしていることやヘミへの思いが強いことからか、ジョンスは若くして金持ちのベンを訝しがり、ヘミを取り合う三角関係のようになる。 原作には仕事をしているようでもなく、何をして金を得ているか分からない男に対して僕が「まるでギャッズビーだね」とつぶやく描写がある。映画でもジョンスは同じセリフを吐くが「韓国にはギャッズビーが多い」と付け加える。 これは、日雇い労働のようなことをしながら日銭を稼ぐジョンスからみた韓国の富裕層の姿であり、どちらか一方に固定化してしまった格差社会を揶揄しているのだろう。そういった原作には無かった現実の社会問題の描写が映画には随所に散りばめられている。 映画の中盤のハイライトで物語が動き出す、ジョンスの実家の庭で三人が大麻を吸うシーンもそうだ。ジョンスの暮らす誰もいなくなった実家は北朝鮮との軍事境界線の近くにあり、日中は北朝鮮のプロバガンダ放送が休みなく聞こえる。 ヘミが大麻を吸ってリラックスし上半身裸になって踊り出すシーンは、この映画でもっとも美しいシーンの一つであるが、ヘミが空中に投げ出す両手の先にはマジックアワーの幻想的な夕焼け空をバックに韓国の国旗が映る。 更に面白いのは、この作品は原作の『納屋を焼く』ではなく村上春樹がデタッチメント期からコミットメント期に移行する最初の長編小説である『ねじまき鳥クロニクル』から着想を得たと思われるシーンをいくつか盛り込んでいるところだ。 『ねじまき鳥クロニクル』では猫がいなくなるところから物語が始まるが、ヘミが飼っている姿を見せない猫もやはりいなくなる。ジョンスの実家ににかかる無言電話も最終的には妻クミコからだと気づくことになる謎の女からの電話や、取られることの無かった電話を思わせる。 極め付けはヘミが幼い頃に井戸に落ちているということだろう。『ねじまき鳥クロニクル』で井戸とは、ノモンハンで間宮中尉が銃殺の代わりに落ちることになった井戸であり、主人公のオカダトオルが自ら下りた世田谷の井戸だ。冷たい井戸の底でオカダトオルはひとりでじっと考える。考えることによって現実の壁を抜け、時空を超えて様々なものと繋がることになる。それは行方不明の妻であり、ノモンハンから現在に形を変えながらも続く絶対的な悪、現代の日本社会が未だ清算することのできていない負債の一部だ。 昨今、ラジオDJを務めるなど小説や翻訳以外での活動も慌ただしい村上春樹は、朝日新聞の「平成の30冊」の企画で、自身の作品が1位に『1Q84』と10位に『ねじまき鳥クロニクル』と二作が選ばれたことで、インタビュー*2 に応じている。 この自身の活動を振り返るインタビューで、『ねじまき鳥クロニクル』の『壁抜け』を語ったあと、95年に阪神大震災と地下鉄サリン事件が起こります。という社会との関係を問われた質問に村上春樹は以下のように答えている。 「個人的な信念として、小説家は作品がすべてで、正しいことばっかり言っていると作品はろくなことにならないと思っている。ただ、作家といっても一市民であるわけで、小説家としてのアイデンティティーやレベルを保ちつつ、市民として正しいことをしないといけない。正論ばかり言ってイマジネーションが壊れないよう、バランスを保つのが大事だけど。」 正論ばかり言っていると想像力が壊れる。インタビューを書き起こした文章なので、どれくらい本気で言っているかが分かりにくいが、こういうことを何のてらいもなくさらりと言えるところが、村上春樹の強さであり資質であるように思う。 そして『納屋を焼く』の物語と『ねじまき鳥クロニクル』の想像によっ壁を抜けて現在の社会を描くことができるという力を借りて、韓国の現代社会を描こうとしたイ・チャンドンもまた、この正論よりも想像こそが大切だということを信じている一人であり、イ・チャンドンが村上春樹の作品から読み取り自作に反映したかったことなのではないかと思う。 この映画の最大の謎であるヘミの喪失は、見るものに想像力を働かせることを要求する。ジョンスから見た視点は一方的な視点であり本当に正しいのか。その正論は本当に正論であり正義なのかということを見る我々に突きつける。その視座が出口のない物語と同じように不条理と感じる、この現実社会に有効なのは正論ではなく想像力だということに気づかせてくれるのだ。 Text by Naohiro Nishikawa (Thinking Framework 2018-2019 前編完) *1 村上春樹本人はデタッチメント期を更に二つに分け、物語を指向する前の作品をアフォリズム(格言)の時期としている。この期間に書かれた長編作品『風の歌を聴け』と『1978年のピンボール』を本人は習作として気に入っていないようで、この二作を別の期間だったと定義しているのではないかと思う。本人が気に入っていなかったことは、英訳があるにも関わらず長らく英語版が日本国外では発売されていなかったことからも分かる。 *2 https://book.asahi.com/article/12182812
FEATURE
- 2025/07/10
-

-
ゆっくりと記憶が蘇り、また消えていく|「AVYSS Chain」VLOG公開
雨と私の夢とファイアファイア more
- 2025/07/08
-

-
iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」に出演するバンドメンバー発表
iVy コンテンポラリー・パーク・オーケストラ♪としての演奏も披露
more
- 2025/06/18
-

-
iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」がWWWにて開催
1stアルバム『混乱するアパタイト』CD版発売決定 more