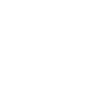Thinking Framework – 考える枠組み vol.7
2023/09/28
7. 現実に戻ってくる価値はあるのか

Text : Naohiro Nishikawa
Photo : Daiki Miyama
6年ぶりの長編小説となる村上春樹の『街とその不確かな壁』と、10年ぶりの長編アニメーションとなる宮崎駿の『君たちはどう生きるか』は、世界的に人気の二人の日本人作家の長く待たれた長編という背景だけではなく、内容から結末に至るまで驚くほど共通点の多い作品であった。
村上春樹の最新作となる『街とその不確かな壁』は、そのタイトルの示す通り実に43年前に書かれた中編小説『街と、その不確かな壁』を下敷きにしている。村上は、これまでも発表済の短編小説を拡張し長編小説にしたり(『蛍』からの『ノルウェイの森』や、『ねじまき鳥と火曜日の女たち』からの『ねじまき鳥クロニクル』など)、短編の『めくらやなぎと眠る女』を改編した『めくらやなぎと、眠る女』など、自身の過去作を長編に組み込んだり改編し違うバージョンとして発表するということを度々行っている。
中編小説『街と、その不確かな壁』は1980年に三作目として書かれたものであるが、村上はその内容を気に行っておらず、本人の意向により単行本や全集にも収録されていない「幻」の作品となっている。しかしながら村上はその壁に囲まれた「街」に強いこだわりがあるようで、度々、作品に織り込んでいる。長編としては四作目となる『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、「世界の終わり」と「ハードボイルド・ワンダーランド」という別々の物語が交互に進むが「世界の終わり」のパートは『街と、その不確かな壁』で書かれた壁に囲まれた街の話だ。また『海辺のカフカ』は当初『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の続編として「街」やその壁の外の森に取り残された人たちを書こうとしたがうまく書けなかったとも語っている。
これらが示すように『街とその不確かな壁』は村上がこれまでずっと抱えていたが、技術的な問題や、その時々の別の仕事のために書けなかった「街」について、小説家としての技術を極めた晩年のこの時期に、正面から挑んだ小説といえるだろう。
一方の宮崎駿の『君たちはどう生きるか』も宮崎がこれまで抱えていたが、描けなかった幼少の頃の自身の置かれた環境や母への想いを反映させた自伝的な作品と言えるだろう。主人公である眞人は父親が航空機関連の会社を経営しており裕福であることや、戦争で東京から田舎に疎開すること、この作品で非常に重要になる母親への想い(作中では戦時中に亡くなり父親は母の妹と再婚することになるが、実際の宮崎の母親は戦時中には亡くなってはおらず長年病床に伏していたそうであるが)など、宮崎自身の幼少期の体験と重ねることができる。
長編アニメーションという多くの人が関わり、莫大な制作費と時間をかけて製作する決して失敗できないプロジェクトにおいて、これまでの成功の実績により、何をやっても許されるという環境を得た今だからこそ、そして最後の作品になるかも知れないからこそ、長年抱えていたが描けなかった自身の想いに決着を挑んだのであろう。
『街とその不確かな壁』では、主人公である<ぼく>が17歳のときに高校生エッセイ・コンクールの表彰式で出会った別の学校の一つ年下の少女に恋に落ちる。<ぼく>と電車で1時間半ほど離れた街に住む少女は手紙の交換からはじめ、やがて二人で長い時間を語り合う会う仲になる。会話を続けるなかで少女は「壁に囲まれた街」という少女が空想の中で作り上げた街の話をする。少女はこちらの世界の自分は本当の自分ではなく、本当の自分は「壁に囲まれた街」に住んでいるのだと打ち明ける。こちら側にいる私はあちら側の「街」に住む本物の私の影にすぎないのだと。
そして、少女は<ぼく>に宛てた長い手紙を最後に現実のこちら側の世界からこつ然と姿を消すことになる。<ぼく>は、こちら側の世界で恋に落ちた少女を永遠に失うのだ。
この少女の空想から生まれた「街」と現実の世界をつなぐ重要な役割を果たすのが「図書館」だ。<わたし>は向こう側の世界である「街」の「図書館」で夢読みとして働く。「街」では本物の少女も「図書館」で働いており、夢読みの<わたし>の手伝いのようなことをしている。一方、現実の世界で少女を永遠に失った<ぼく>は孤独のまま中年の<私>になり、45歳のときに長らく勤めた出版社を退職し、地方都市の「図書館」の館長として働くことになる。そこでも「図書館」はあちら側の世界とこちら側の世界を結ぶ特別な場所として機能する。
『君たちはどう生きるか』においても、眞人は入院中の母を空襲の火事で亡くす。幼少の眞人にとって母という存在は特別でかけがえのない存在と言えるだろう。その後、眞人の父親は実母の妹と再婚し、眞人は疎開先として父の故郷の大きな屋敷に、父と新しい母と一緒に暮らすことになる。
屋敷のそばには大叔父が立てた塔の形をした「書庫」がある。そこには大量の書物が保管されているが老朽化が激しく、眞人は近づかないように言いつけられている。『君たちはどう生きるか』では、この「書庫」が、『街とその不確かな壁』の「図書館」がそうであったように、こちら側とあちら側をつなぐ役割を果たす。
ある日、眞人の継母であるナツコが夕方になっても戻ってこなくなる。ナツコが森に入るのを見ていた眞人は、その足跡を追い「書庫」に入る。それをきっかけに、あちら側での冒険とファンタジーの、宮崎駿がこれまでに描いてきたあの世界に迷い込む。その世界では死んだ母も継母も若く美しく、屋敷で使いとして働く婆も若く勇ましい姿で描かれる。
世界的に人気の作家が抱きつづけたがこれまで書けなかったテーマに晩年になって取り組んだという背景。恋に落ちた少女/母を永遠になくしたこと。図書館/書庫という大量の書物、あるいは物語であり過去の記憶が保管された場所がこちら側とあちら側を繋ぐ役割を持つこと。あちら側には、こちら側では永遠に失った特別な存在である少女/母が存在していることと、シンクロニシティと言うべきか、両作はまるで申し合わせたかのように多くの部分が奇妙に一致する。
その極めつけは両作の物語の終わらせ方だ。<わたし>も眞人も、少女/母がいる、あちら側の世界を捨ててこちら側に戻ってくることを選ぶ。あちら側にはある種の理想の世界があるというのにだ。結局のところ本のページの最後に到達すれば、スタッフロールが流れれば我々読者/観客は強制的にその小説/映画の世界を追い出されこの現実の世界に戻ることになる。それにも関わらず、小説の映画の中で、むこうの世界から、こちらの現実の世界に戻る必要なんてあるのだろうか。そもそも、この現実に戻ってくる価値なんてあるのだろうかと思う。
村上は1949年生まれで、1968年に早稲田大学に入学している。60年代の終わりと言えばそれは政治の季節であり、作品であの時代の学生運動について特に運動の欺瞞について否定的に語ることはあるものの、社会に「異議申し立て」を行ってきた世代でありその一人だ。宮崎は1941年生まれと村上よりも8年早く生まれており、あの時代には学生ではなく東映動画の会社員であったが、東映動画労働組合の書記長を務めるなど、こちらも会社や社会やそのシステムに対して「異議申し立て」を行ってきたと言えるだろう。
つまり、彼らは社会に「異議申し立て」を行い、ある種の挫折を経験した後に、この現実の世界で各々のやり方で多くの成功を掴んだのだ。これは何も二人だけの特別な話ではない。この世代の多くが社会に「異議申し立て」を行った末に、うまく行かず挫折を経験するも、日本の経済成長に合わせ豊かに生きていくことができたのだ。だから、この現実が理想から大きく離れているとしても現実に戻れ。この現実もそこまで悪くないと経験的に言っているのだ。
しかし、今の若者が社会に不満を持ち「異議申し立て」を行い、独自のやり方で生きて行った末に、果たして豊かな暮らしを手に入れることができるのだろうか。もちろん、どんな時代であろうとそれができる人はいるだろう。ただ現実は彼らの時代のそれとはもはや大きく違ったハードモードだ。少なくとも経済成長に合わせて自然と収入が増え、一戸建ての庭付きの家をローンで買って夫婦と子供二人と愛犬と暮らすというような、彼らの時代に誰もが出来た暮らしは理念を妥協し社会への迎合がないと(場合によっては社会へ迎合したとしても)難しい時代になってしまっているのだ。
「街」を組み込んだ最初の長編である『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の最後で<僕>は「街」から脱出する方法を見つけながらも土壇場でその世界にとどまることを選ぶ。そして、こちら側の<私>は死を受け入れる。『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は1985年に書かれた作品であるが、その結末の方が「外側」を求める今の気分に合っているのではないだろうか。
そしてもっと言えば、あちら側やこちら側のような二項対立に持ち込むのではなく、リアリズムの呪縛を超えて、あちら側やこちら側の垣根を壊すべきではないか。それがこれまでに村上や宮崎が行い文学の、映画の世界を前に推し進めて来たことであり、読む/見る我々の現実をも変えて来た、フィクションのファンタジーの力ではないだろうか。

category:COLUMN
tags:Thinking Framework
RELATED
-
2023/11/07
Thinking Framework – 考える枠組み vol.8
8. 取り戻すべきは過去か未来か Text : Naohiro Nishikawa Photo : Daiki Miyama 2010年代初頭に生まれた音楽のジャンルにVaporwaveがある。Vaporwaveはインターネットのコミュニティーから生まれたジャンルであり、Vapor(霧や蒸気の意)という名の示す通り、実体のない作られたジャンルだ。2000年後半に盛り上がりを見せたChillwaveの音楽ブログ主導という非権威主義を更に推し進め、コミュニティー主導、匿名性そしてインターネット特有のミーム感あるいは悪ふざけから作られたものだ。 Vaporwaveの特徴はDTM黎明期のMIDI音源をそのまま使ったようなチープな打ち込みによるエレベーターミュージックやシティーポップを当時流行していたポストインターネット的な意匠とバッドテイストによりパッケージングしたものと言えるだろう。このジャンルを代表する作品であるMacintosh Plusの『Floral Shoppe(フローラルの専門店)』のジャケットやコンピュータ翻訳調とも言える壊れた日本語を見ればこのジャンルの感覚や美学が伝わるはずだ。 そういった表面的な特徴以外に、Vaporwaveにおいて特筆すべきことは、すべてが過去と結びついていることだろう。それは先代のChillwaveからの流用であるダウンテンポと哀愁漂うシンセサウンド由来のところもあるが、彼らが使う意匠やモチーフは、16bitゲーム風のスプライト、3DCG黎明期のレイトレーシングやローポリゴンで描かれた静物。郊外型のショッピングモールやヤシの木への情景など過去を連想させるものばかりだ。 そのVaporwaveを代表するアーティストの一人がESPRIT 空想ことGeorge Clantonだ。ESPRIT 空想はその漢字を取り入れた名義からも明らかなように、2014年のアルバム『Virtua.zip』のジャケットは『バーチャファイター2』の今の目で見ればポリゴンも解像度も足りないアキラが使われるなど、Vaporwaveの様式を用いている。 しかし、その4年後の2018年に本名George Clanton名義でリリースした『Slide』では旧来のVaporwave的様式は影を潜めることになる。ジャケットに写る本人のブリーチされたジーンズとロンT、ハイテクスニーカーの組み合わせは90年代初頭のダンスカルチャーやその後のレイブカルチャーを思わせるものであるし、鳴っている音はロックとダンスが融合したセカンド・サマー・オブ・ラブなマンチェスターや、それを通過した91、2年頃のシューゲイズとダンスを混ぜたギターバンドと同じ音だ。タイトルからも分かるように当然後期のFlipper’s Guitarからの影響もあるだろう。 このアルバムもVaporwaveだと捉えるのであれば、Vaporwaveは何にでもなれる自由なジャンルだと言うことができるだろう。唯一、Vaporwaveというジャンルを規定するものがあるとすれば、それは過去の何らかの様式を取り入れているということだけだ。*1 Vaporwaveの例を持ち出すでもなく、音楽は過去の様式を引用し発展してきた。それは常に新しいムードを取り入れてきたK-POPでも例外ではない。 K-POPにおいてもっとも過去に接近しているアーティストと言えば、2022年7月に『Attention』でデビューした5人組のガールズグループNewJeansだろう。NewJeansが所属するADORの代表であり実質的なプロデューサーであるミン・ヒジンは、グループの名前を老若男女みんなに愛されてきた「ジーンズ」のように日常に密接し、時代のNew Gene (新たな遺伝子)になる覚悟が込められていると説明している。そして現在において、彼女たちの世代の日常に密接したファッショントレンドと言えばY2Kだ。 デビュー曲の『Attention』のMVで5人は、ジャージ、ジーンズ、サッカーシャツ、モトクロスジャージ、ワークブーツにストライプのニーソックスと様々なルックを矢継ぎ早に見せているが、それらはどれもY2K的なスタイルと言えるだろう。またこのビデオで特徴的なのは、寝起きの髪に止められたヘアピンや有線のポータブルヘッドホンなどの小物が、Y2Kを通り越し90年代や80年代をも思わせるところだ。 つまり彼女達において、Y2Kのカルチャーは2000年代という特定の時代のファッショントレンドを指すというよりもレトロでかわいいもの一般という感じなのだろう。日常でレトロでかわいいものという価値基準は日本のアイドルカルチャーから見るとごくありきたりなもののようにも見えるが、近年のK-POPのガールズグループのコンセプトとしては異質なものだ。 2020年11月に『Black Mamba』でデビューしたaespaは「自分のもう一人の自我であるアバターに出会い、新しい世界を経験する」というコンセプトのもと、メンバー4人の各々に対応するアバターがバーチャルなメンバーとして存在し、合計8名のメンバーが現実世界と仮想世界の両方で活動するとしている。 NewJeansよりも4ヶ月ほど早く2022年3月に『Tippy Toes』でデビューしたXGはXtraordinary Girls (extraordinary 並外れた、規格外の意)から来ており、常識にとらわれない規格外なスタイルの音楽やパフォーマンスを通じて、世界中のさまざまな境遇の人たちをエンパワーしていくとしている。 このようにaespaもXGにも日常やレトロというキーワードはなく、ロゴもAcid metalやAcid graphicsと言われるサイバーで未来志向なもので、よりパキった*2 表現を行っている。これは彼女達がデビュー時にベンチマークとしたのが、世界的な成功を収めたBLACKPINKだったからだろう。BLACKPINKは、最も綺麗で女性的な色とされてきたピンク(PINK)と、それを否定する意味で黒(BLACK)を前に付けて、「美しいもの(現存する女性らしさ)が全てではない」ことを主張するとのことだが、その黒の部分のコンセプトを更に推し進めたのが、aespaのメタバースであり、XGの規格外のギャルであったのだろう。 しかし、それらのコンセプトもNewJeansの成功によって若干の軌道修正が行われているように見える。これまでのパキったEDMを軸に強めのビートやトラップ、トランス感あるシンセサウンドが売りだったaespaは、23年のサマーソングとしてリリースした『Better Things』では夏休みを感じるトロピカルでリラックスした楽曲でカムバックしてきた。MVもこれまでになくリラックスした雰囲気で、メンバーが過ごす部屋には時代遅れとも言える大型のステレオやカセットテープ、ポラロイドなどのレトロなものが配置されている。CGの熱帯魚に連れられて日常からあちら側の世界に行くという描写がなんとかaespaのメタバースのコンセプトを保っているところだが、それを除くと暖色にカラーコレクションされたビデオの質感も含めて実にNewJeans的世界観と言えるだろう。 aespa – Better Things もう一方のXGがリリースしたサマーソングである『NEW DANCE』も、これまでのK-POP的EDMや『MASCARA』で聴かせたSophieを思わせるハイパーポップとも言える楽曲から方向を変えて、ギターのリフが入ったR&Bハウスとでも言えるような楽曲に仕上がっている。MVもこれまでの戦隊モノやディストピア感さえ漂うパキった表現は後退し、スタイリングはNewJeansの『Super Shy』のMVでも使われているY2Kを取り入れた人気ブランド『Mowalola』であるし、後半で唐突に登場しズームインされるモニターは、VHSビデオを一体化させたブラウン管のテレビデオというレトロ具合だ。一番最後でそのレトロな世界から元のXG的空間に戻るのは夏休みに時空を超えて2000年代初頭に遊びに行っていたということなのだろうか。 XG – NEW DANCE K-POPは商業音楽であり、外貨を稼ぐためにUSを始め様々な国のマーケットを狙ったという出自からしても、売れたものが正義というカルチャーである。よって、NewJeansのK-POPのEDMを基調としラップや高音パートが入るお約束を捨てて、インディーR&Bとでも言える楽曲と日常でレトロでかわいい意匠での成功は、K-POP業界に新たな潮流を産んだと言えるし、他のガールズグループの新しいベンチマークになるのも理解できる。 しかし、過去だけを見ていて良いのだろうか。確かにY2KやレトロなものはNewJeansを消費する若い世代にとっては目新しいものと写るかもしれない。それでも、それはやはり過去のものだ。2020年代としての新しい何かを産まなくてもよいのだろうかと思う。 前述したようにVaporwaveは過去の何らかの様式を取り入れているジャンルだ。しかし、そこで使われている意匠やモチーフをよく見てみると、実は未来を志向していることに気づく。16bitゲーム風のスプライトや3DCG黎明期のレイトレーシング、ローポリゴンは今の目で見れば時代遅れのものであるが、その当時としては最新のものであり、より良いものを求めた中での進化の通過点だ。George Clantonが『Slide』で参照した80年代の終わりから91年頃のロックとダンスの融合や続くシューゲイザーのダンス化もそうだ。当時は1年ごとに、ともすれば数ヶ月ごとに新しい音が鳴らされ、多くのバンドがそれに追従し、また新しい音を発明する未来があった時代なのだ。 つまり、Vaporwaveは新しいものが登場しない、すなわち未来がない2010年代の状況を未来のあった過去に求めた、失われた未来を過去に希求したジャンルと言えるのではないだろうか。未来がない現在ではなく、未来があった過去を現在に立ち上げて未来を幻視したのだ。 夏の終わりとは言えまだ猛暑が続く9月の終わりにリリースされたXGの1stミニアルバム『NEW DNA』のコンセプトは「常識にも枠にも囚われることのない『新たな種族』であるという表明を果敢に作品に込めた」とのことである。『新たな種族』というのは、全員日本人であり韓国のスター育成システムというフレームワークを使ったK-POPともJ-POPとも厳密には言えないXGの立場をフィクショナルに表したものだろう。その『NEW DNA』というコンセプトの通り、一曲目は『HESONOO』(へその緒)という攻め具合であるし、二曲目も『X-GENE』と未知な遺伝子を表したトランスヒューマン的なものと言えるだろう。 『NEW DNA』のリリースと同時に公開された『PUPPET SHOW』のMVは、『NEW DANCE』の日常のそれとは違い、白に包まれた未知の種族の住む惑星に神として降臨し祝祭を受けるような、外側を目指したものだ。イーロン・マスクのスペースXの火星移住計画や長期主義者の宇宙主義、地球とは大きく環境が違うところでも宇宙服のようなものを着ることなく活動できているところを見るとトランスヒューマニズムにも通じるものがある。これが未来として正しい方向かどうかは分からない。分からないが、分からないからこそ、それは一つの予測不可能な未来を示すものだと言えるのではないだろうか。 XG – PUPPET SHOW *1 George Clantonの最新作『Ooh Rap I Ya』のレビューとして吸い雲は「特定の時代の美学を取り出すアプローチ」と称している。これは本稿で取り上げた『Slide』についても言えることだと思う。https://turntokyo.com/reviews/ooh-rap-i-ya-george-clanton/ *2 パキるとは一般に市販薬をオーバードーズ(OD)し意識を変容した状態を指すが、ここではそこから転じて尖ったあるいは覚醒している状態を指す動詞として用いている。
-
2023/09/01
Thinking Framework – 考える枠組み vol.6
6. 常識の外側へ Text : Naohiro Nishikawa Photo : Daiki Miyama 音楽のカルチャーはドラッグと分かちがたく結びついてきた。古くは1950年代のバッブとその後のハードバッブのジャズプレーヤーのヘロイン。60年代のヒッピームーブメントでの大麻やLSD。ギャングスタのクラック。セカンドサマーオブラブのエクスタシーつまりMDMAと、時代やシーンによって使われるものは違うが、ドラッグは音楽とそのカルチャーに分かちがたく結びつき、シーンを形成してきた。 現在の日本で、音楽とドラッグの関係をもっとも色濃く反映させたアーティストとして真っ先に思いつくのは、舐達麻をおいて他にいないだろう。麻を舐める達人というその名前の通り、大麻は彼らの存在において中心的なものとなっている。 それは、もちろんリリックにおていも顕著だ。「何処にも行かず此処でマリファナを嗜んだ/誰が居ても構わず/煙を吐いた」(GOOD DAY)、「毎日毎日スモークするマリファナ/俺が育ててる/俺と仲間達で育ててる」(BUDS MONTAGE)というように、彼らの世界において大麻は日常的にそこにあり、自分達で育て毎日使うものなのだ。 また、彼らの大麻に対する考え方は、典型的な大麻解禁論者とは一線を画す。多くの大麻解禁論者は、大麻は健康に対する害が少なく、依存性が低く安全だと説明し、大麻を禁止することに合理的な理由はないと主張する。しかし、舐達麻は違う。「依存性あり、だから何」(BLUE IN BEATS)である。依存性があろうが、安全性が低かろうが、法律で禁止されていようが、そんなことは彼らが大麻を吸う上では何ら関係ない。それが舐達麻を舐達麻とたらしめるアウトローの生き方なのだ。 大麻の栽培と所持は日本では犯罪とは言え、誰かに直接迷惑をかけるような種類のものではないとも言えるだろう。一方で、舐達麻は過去に金庫破りを行い警察に追われ、車で逃走時にコンクリートに激突しメンバーの104を亡くすという痛ましい事件を起こしている。この事件をリリックにしたのが『FLOATIN’』だ。 尾崎豊が『15の夜』で唄った「盗んだバイクで走り出す」というフレーズは、学校や家庭に縛られて自由にならないと感じる若者が、その自由に憧れや共感を示すものだが、現代の若者は「盗んだバイク」という時点で拒否反応を示し共感ができないという話がある。この話がどれくらい本当で普遍性のあるものかは定かではないが、法を破ることや、他人に迷惑をかけることを極端に嫌う今の日本社会に、なぜ舐達麻のアウトローは受け入れられたのか。YouTubeの『BUDS MONTAGE』が4600万回再生*1されているのみならず、なぜ地上波のテレビ番組*2 にも出演することができたのだろうか。 それはポピュラー音楽研究者の大和田俊之が言う*3ように彼らの持つ<詩情>、つまりポエジーの力に他ならないのではないか。社会と反社会という二項対立において、近年、強く嫌忌される反社会的な行動であっても、その<詩情>によって、幅広いリスナーからの支持を集めることができることを示したのだ。つまり、舐達麻は自身のアウトローとして生きる哀愁とビート、リリックが一体となった<詩情>の力によって、この二項対立を脱構築し、常識の外側に行くことができたのだ。なにも法を破ることやアウトローであることが常識の外側ではない。法を破ってもアウトローであっても世間に受け入れられたことが常識の外側なのだ。 ALLDAY / 舐達麻(prod by GREEN ASSASSIN DOLLAR)。2023年7月時点での最新曲。BUDS MONTAGE以来2年ぶりのGREEN ASSASSIN DOLLARのビート。7/11のMI_Dのトークによると曲は常に作っており、10曲程度が同時進行中とのこと 舐達麻のそれとはまた違った方法で、常識の外側を目指すアーティストがいる。それが食品まつり a.k.a Foodmanだ。食品まつりは、あらゆる音楽が出尽くしたと言われ、過去のスタイルからの引用と組み合わせのセンスでなんとか新しいものを生み出そうとしているこの時代において、未知の音楽、ビートを探し続けているアーティストの一人だ。 食品まつりは誰の真似でもないユニークな音楽を制作するために、自身が起こすエラーを活用すると話す。「すごいエラーが起きやすい人間。エラーが音楽的にいい方面に転ぶときがあって、そのエラーを別の視点の自分で編集する」*4と語っている。つまり自身のこれまでの蓄積や常識からは出てこない音を機材の操作ミス等によって偶発的に発生するエラーに求め、そのエラーを自身の音楽的な感性で編集するということだろう。 しかし、いくらエラーを起こしやすい人間と言ってもユニークなエラーというものがいつも起こるものだろうか。また、音楽的には外れ値であるエラーを自身の価値観のままで音楽的に良いと受け入れられるものだろうか。もし意図的ではなくエラーを多発させ、それを受け入れる自身の価値基準を変える方法があるとすれば、例えばそれはドラッグを使うことだろう。ドラッグでの酩酊により機材の操作ミスを起こしエラーを発生させ、意識を変革させ音の感じ方を変え価値基準を変えるのだ。そして食品まつりにおいてのドラッグとは、2016年にそのヤバさに気づいたというサウナだ。 食品まつりはTimeoutのインタビュー*5 で初めて正しい入り方でサウナを体験したときのことを、これは現代のサイケデリックカルチャーだと発言している。また、イギリスのメディアFACT magazineの人気企画『Against The Clock』*6には横浜のサウナから出演しており、「サウナで頭の中を真っ白にしてそこからトラックメイクをするといい曲ができる。いつもそんな感じでやっている。」との発言もあれば、LAの<Sun Ark Records>から2018年にリリースされた『Aru Otoko No Densetsu』ではそのものずばりの『Sauna』という曲や、ニューヨークの〈Palto Flats〉より2018年にリリースされた『Moriyama』には『Mizuburo』という曲もある。 こうした発言や曲名からも分かるように、食品まつりは自身の音楽と現代のサイケデリックカルチャーだと言うサウナを完全に結びつけている。そして、そのサイケデリック体験を引き起こすべくドラッグとなるものは、舐達麻や多くの先人達が使った法で禁じられたものではなく、むしろ健康的なイメージさえあるサウナだ。つまり、彼は音楽とドラッグというカルチャーを継承しながらも、ドラッグを使用することの社会/反社会という二項対立をサウナという反社会ではない手段によって軽やかに脱構築しているのだ。 サウナ以外にも食品まつりが関心を寄せるものは、最新アルバムである『Yasuragi Land』のリードトラックでもある『Michi No Eki』(道の駅)や、『Minsyuku』(民宿)、最近本人がSNSでも盛んに言及している『Aji Fly』(アジフライ)と、サウナと同じように日本の地方都市にも見られる土着的でクールと呼ぶには程遠いものばかりだ。 それでは、食品まつりがドラッグであるサウナを用い、道の駅や民宿、アジフライという非都会的であり、非システム的かつ非資本主義的なものを持ち出し、目指ものとはなにか。それはやはり現在の我々に不可避なシステムとして存在する資本主義の外側ではないかと思う。 それは『Yasuragi Land』がKode9主催の<Hyperdub>からリリースされたことからも見てとれる。Kode9ことスティーブ・グッドマンはウォーリック大学で哲学を専攻しており、「加速主義」の提唱者として知られるニック・ランドに師事し、ランドと彼の学生の哲学の実践の場であったサイバーネティック文化研究ユニット(Cybernetic Culture Research Unit: CCRU)*7にも参加していた。最終的に同大学で哲学の博士号を取得しているKode9は、食品まつりの音楽のユニークさのみならず、システムの外側を目指すその態度をも感じとっているのではないだろうか。 いずれにせよ、食品まつりは既存のシステムに対して反システムとして二項対立に持ち込むのではなく、誰もが見逃していたあるいは見捨てていた土着的でかつ非システム的なものを持ち出し、軽やかにシステム/反システムを脱構築することで、この世界のシステムである資本主義の外側、常識の外側を目指しているのだ。それは資本主義のプロセスを加速することによって資本主義を破壊しようという試みよりも、より実践的な外側を目指す試みではないだろうか。 Foodman, Michi No Eki feat. Taigen Kawabe。1:40では「あ、間違えた」と作為的に起こしたと思われるエラーを取り込んでいる。 *1 2023年7月時点 https://www.youtube.com/watch?v=zaBp1Jh3Bkc *2 2023年7月11日の深夜にフジテレビで放送された M_IND https://www.fujitv.co.jp/m_ind/ *3 日本語ラップの現在(3)大和田俊之 舐達麻
-
2024/07/22
Thinking Framework – 考える枠組み vol.9
9. システムと非システムの構造と力 Text : Naohiro Nishikawa Photo : Daiki Miyama 現在に続く日本の一般層での現代思想の受容*1の源流ともいうべき浅田彰の『構造と力』が発売されて今年で41年になる。昨年は出版40周年を記念し文庫化もされた。そこから遡ること10年、2013年には30周年を記念して電子書籍版も出版されている。浅田は刊行30周年を記念した朝日新聞のインタヴュー*2で、現代の「どうせ資本主義しかない」というシニズムを批判し、別の現実を構想するヴィジョン、それらを総合した「思想」が必要だとし、次のように述べている。 現在、「難解」な理論や思想はもはや求められていないように見える。しかし、本当にそうか。グローバル資本主義が成立した結果、反資本主義の運動も世界中で激化している。もはや部分的社会工学ではカヴァーできない矛盾が噴出しているわけです。(引用者略)。利口ぶったプラグマティストは「あんなナイーヴなことを言って」とシニカルに構えるけれど、それは間違っている。原点に帰って現実を批判し、別の現実を構想することが、求められているのです。 『構造と力』はプレモダンからモダンの構造を説明し、それを乗り越え次の段階であるポストモダンに行くために現代思想、とりわけドゥルーズとガタリのリゾームをヒントとして提示する。ただ、このインタビューで浅田は、そこでやりたかったことは哲学や現代思想それ自体ではなく、それをヒントにあるいは道具にして世界を変革することだと言っているのだ。 このインタビューにもあるように、今から10年前と言えばグローバル資本主義の弊害が叫ばれ、反グローバル主義の活動が激化した時期だ。2008年のリーマンショックに端を発した世界金融危機とそれに伴う不景気は、その要因となった金融業界はもちろん普段はマクロ経済や金融投資から直接恩恵を受けていない多くの市民が影響を受けた。2011年の秋にウォール街を占拠せよ(Occupy Wall Street)の合言葉を元にニューヨークのウォール街でアメリカ経済界に対する大規模な抗議行動が起こったのを覚えている人も多いだろう。 では、そこから10年経った現在、世界を取り巻く状況はどのように変わったか。グローバル資本主義は更に加速し、もはや資本主義と呼んでよいのかどうかすら怪しいプラットフォーム資本主義に移行している。 プラットフォーム資本主義とは、企業がデジタルデータを基本とする広義の商材を売買するプラットフォームを提供し、その上で他の企業や消費者が活動する経済モデルを指す。GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)に代表されるテクノロジー企業がなぜ時価総額の上位を占めているのか。それは彼らがプラットフォームを構築し、その領域において独占的な事業を展開しているからだ。 グローバル資本主義においては、多国籍企業がその資本力とグローバルなオペレーションによる合理化を後ろ盾に多くの国に進出しローカルな環境に競争を持ち込み、多様な文化を破壊することが問題とされた。スターバックスやマクドナルドの進出が分かりやすい例だろう。彼らがローカルなカフェやハンバーガーショップをいくつか殺したのは確かだろう。しかし、彼らは労働集約型の産業であり現地での雇用を生むし、同じようなチェーン展開を行っているのはグローバルな企業だけではなくローカルな企業でも同じことだ。彼らは競争しローカルな企業に負けることもある。 プラットフォーム資本主義の問題はデータの独占とネットワーク効果により一つの領域の市場を1社ないしは少数の数社で専有することだ。そして独占的な支配力によって、資本主義の利点とも言える競争を無効化し、彼らの原理をすべての人に押し付けることだ。 例えば、誰でもなんでも発言できる民主主義のためのツールだともてはやされたTwitterはイーロン・マスクに買収されると、マスクに批判的なジャーナリストのアカウントは停止され、「From the river to the sea」*3と発言したアカウントも停止すると警告された。Twitterに対抗して作られたInstagramのThreadsも一見オープンな姿勢のように見えるが、サービスを提供するのはFacebookのMeta社だ。Facebookの初期の大株主であり取締役はマスクと同じペイパルマフィアのドン、ピーター・ティールである。今ではティールとFacebookとの関係は薄くなってきているようだが、保守系のリバタリアンであるティールとその思想を共有するマスクとザッカーバーグが、我々の言論プラットフォームでの言論の自由を握っているのだ。つまり、マイクロブログサービスという言論プラットフォームにおいては、資本主義は加速し、右派加速主義が実現したと言える状態になっているのだ。そして右派加速主義とは言論の自由が抑制され、見たい情報ではなくプラットフォーマーの見せたい情報だけが流れる管理社会、プラットフォーマーによる封建主義のことだ。 Visaをはじめ、MastercardやAmerican Express、Diners Clubなどのグローバル資本のクレジットカードがニコニコ、DLsite、FANZA同人などの取引を停止していることも、プラットフォーマーによる言論の自由の抑制の一例だろう。国家が直接、国民の言論の自由を抑制するのは憲法違反となるし、他の国家に対しては内政干渉となり難しいが、プラットフォーマーを使えばそれが可能になるのだ。日本にはJCBがあるから安泰と言っていられるのも時間の問題かもしれない。決済系のサービスは金融庁の言いなりであるし、この国の官公庁が外圧に弱いのは説明するまでもないだろう。 グローバル資本主義では、例えばスターバックスが労働組合のパレスチナ支援を妨害したり、マクドナルドがイスラエルを支援したりすることに、消費者は不買運動という形で抗議ができる。ドトールやモスバーガーという代替もある。しかし、プラットフォーム資本主義の時代となるとこれはとても難しい。例えばGoogleをボイコットしようとして彼らが提供するサービスを一切使わず生活することができるだろうか。AmazonをボイコットしようとしてAmazonから本や日用品を買うことを辞めることができても、Webサービスや銀行の基幹システム、携帯電話の仮想ネットワークから行政サービスにまで使われ始めているAWSはもはや社会インフラであり、それをボイコットすることは現代的な生活を営む限り不可能だろう。開発拠点をイスラエルに置くIntelも、PCやスマートフォンは非Intelのそれを選ぶにしても、このWeb/銀行/行政サービスが使っているサーバーがIntelかどうかなんてのは調べようがないし、もしIntelだと分かったとしてもボイコットのしようがないのだ。 Uber Eatsらによるデリバリープラットフォームにも多くの問題がある。彼らは、配達員に好きなときに好きなだけ仕事ができ、人間関係にも悩まされることがない労働システムを提供しており、従来の人による支配/被支配の関係から労働者を解放しているとも言える。配達はすべてスマートフォンのアプリの指示に従えばよく計画経済の計画の部分をコンピュータに任せた左派加速主義の実装と見做せなくもないだろう。しかし、その実態は配達業務の低賃金化でしかない。配達員は配達のみに賃金が支払われる業務委託契約であり収入に保障がないばかりか、配達員同士の配達の取り合いという熾烈な競争にさらされている。配達件数よりも配達員が多いときにプラットフォーマーは、最も安く配達される金額まで配達料金を下げることもできるだろう。配達員が余っているときに、プラットフォーマーが配達員に必要以上の賃金を支払うインセンティブなどどこにもないのだ。逆に配達員の賃金を抑えられれば、配達料金を下げることができ、その結果、注文数が増えシステムの利用料金を増やすことができる。現在のデリバリープラットフォームは大量の投機資金で成り立っており、その投機を成功させることが最優先であり、左派方向に加速することなど絶対にないのだ。 デリバリープラットフォームの一番の問題は、その地域の貧富の差を利用していることだろう。レアジョブが日本とフィリピンの経済格差を利用して日本人に低価格の英会話レッスンを提供したり、「甘栗むいちゃいました」が中国農村部の安い労働力によって実現されていることが、国内の同じ地域の貧富の差を利用して行われているのだ。そして配達員は業務委託契約であり、配達に使う設備も配達収入の中から自分で用意する必要がある。つまり、彼らはAppleやGoogleが提供する別のプラットフォームであるスマートフォンの代金や通信費用も自分の収入の中から支払う必要があるのだ。 そういう視点で見ると、デリバリープラットフォームという一つのプラットフォームに関わる全てのアクター、料理を注文する人、注文を受けて調理する人、配達する人、そのシステムを運営する人、全てが、AppleやGoogle、バックエンドを支えるAmazonやMicrosoftに依存し、システム利用料という名の税金を払っているのだ。つまり、GAFAMのような巨大なプラットフォームはプラットフォームをも一つのアプリケーション、データ、ユーザーとしてデリバリープラットフォームで言うところの配達員として競わせ、働かせ、システム利用料を徴収するメタプラットフォームというべきものに変貌し、この世の中に偏在しているのだ。これがプラットフォーム資本主義の実態であり、浅田が『構造と力』で描いたクラインの壺の循環モデルの最新の形態なのだ。クラインの壺において循環する貨幣の外側がないように、プラットフォームの外側もないのだ。 * * * 再開発の進む渋谷*4の駅周辺を歩いてみると、新しく出来た高層ビルはGoogleやAbemaのプラットフォーマーのもので、プラットフォーム資本主義による市場の支配が現実のストリートにも侵食し始めていることに気づく。それらはまるで彼らの売上や時価総額を示すグラフのように上へ上へと伸びている。地下鉄に乗り換えるために地下に降りれば、壁一面の広告と柱に取り付けられたデジタルサイネージによる動画広告が否が応にも目に入る。歩くために見ざるをえないそれらはまるで、Webページに貼り付けられて読みたい記事を覆い隠す動画広告のようだ。 広告プラットフォームは検索や動画やSNSのタイムラインにだけではなく、移動にまで広告を仕掛けてきている。我々はもはや彼らのサービスを使っているわけでもないのに広告を見せられるのだ。こうして世の中に偏在するプラットフォームは、デジタルやネットワークの領域にとどまらずリアルな都市に染み出してきている。リアルとネットという二項対立は終わり、インターネットがリアルに染み出す時代を予言したポストインターネットは10年かけて、たぶん当初の目論見とは大きく違った形で現実のものになったのだ。 ゴールデンウィークの最終日である5月6日、プラットフォーム資本主義が可視化されたその渋谷で<Protest Rave>が行われた。「ダンスは抵抗である」というメッセージを掲げ、ストーリートでゲリラ的に活動を続ける彼らの今回のスローガンは「End Them All」というものだ。ここで終わらせたいものとは虐殺、占領、アパルトヘイト、シオニズム、人種差別、植民地主義、帝国主義、ファシズムのことで、今も解決されていない人が自由に生きる権利を脅かすシステムが作り出した問題と言えるだろう。『構造と力』の言葉を借りるなら人間の過剰なサンスであり欲動がもたらしたカオスだ。 ホームセンターで手に入れたような白木の木材をDIYで即興的に組み上げて作られたDJブースとその上に組まれた矢倉は、雨を避ける屋根もなく風が吹けば飛ばされるような頼りのないものだ。周囲を見渡す限りのRGBの原色の広告に包まれたハチ公前に、その矢倉はいかにも不釣り合いで、非システムを象徴した異物と言えるだろう。一方でDJが使うパイオニアのCDJとミキサー、PAシステムとそれによって鳴らされるFunktion Oneのスピーカー、コールに使われるマイクやそれを加工するエフェクタ類は、企業の大小はあるが資本が投下されシステム側が作ったものだ。 これで気づくのは、非システムはシステムが作ったものも使うことができるが、システムは非システムが使えるものが使えるとは限らないということだ。非システムはそこでレイブを開きみんなで踊りたいときにDIYでDJブースを作りシステムが作ったスピーカーを鳴らすことができる。しかしシステムは、例えばスクランブル交差点のビルにあるスターバックスが客の椅子が足りないときに、東急ハンズで木材を買ってDIYで即席のベンチを作ることはできないだろう。 もし非システムに勝ち目があるなら、このシステムと非システムの非対称性を利用することではないか。使える手段で言えば、非システムの方がシステムの手段に加え非システム固有のものが使える分、システムが使えるよりもずっと多いのだ。使える資金や量で負けたとしたも手段の数では勝てるのだ。これはシステムをプラットフォーマーに置き換えても同じことが言えるだろう。つまり非システムはプラットフォームを批判して使わないのではなく、批判して非システムのために利用するのだ。そしてそこにシステムが使えない非システムの手段を差し込み、プラットフォームのシステムを内側からコントロールするのだ。<Protest Rave>がプラットフォーム資本主義が現実に出現した渋谷のハチ公前に、非システムのDIYのレイブ空間を、つまりシステムの外側を作り目指したことはそういうことではないか。 レイブの終盤、みんなのきもちがかけるトランスに合わせたパレスチナの解放を求めるコールと踊るクラウド。そしてDIYで作られた頼りない矢倉の上に立ちパレスチナの国旗を高らかに掲げるMars89。それがどんなに頼りなく弱いものであっても矢倉は絶対に崩れないし、Mars89は絶対に落ちない。極彩色のシステムの広告に取り囲まれたハチ公前に作られた外側は、そういった楽観的な確信とユーフォリアに包まれていた。 同じ時期に出版された、ナージャ・トロコンニコワの『読書と暴動 プッシー・ライオットのアクティビズム入門』(野中モモ訳)はフェミニスト・パンク集団プッシー・ライオットの創立者である筆者がこれまでの政治活動を記した自伝であり、その背景にある思想とそれを彼女に与えたヒーロー達の列伝であり、サブタイトルにもあるように力なき個人が政治活動を行うためのハウ・トゥー本としても読めるだろう。 本書で重要なところは『暴動』だけでなく、『読書と暴動』であるところだ。お騒がせ集団としてメディアに取り上げられることも多いプッシー・ライオットであるが、なんの手がかりもなく闇雲に行動して世界を変えようとしているのではなく、先人の活動家や思想家の著作から知恵や思想を学び、インスピレーションを受けて実際の行動に移していることが分かる。そうした点で本書は『構造と力』と目的を共有する書物であり、『構造と力』が描ききれなかった世界を変革するための実践の書と言うこともできるだろう。本書は次の言葉で締めくくられている。 最後にこれは覚えておいて。トランプに反対するツイートをした全員が路上に現れてそこを動かなければ、トランプは1週間もせずに辞任に追い込まれるだろう。力なき者は力を持っているのだ。 力なき者は力を持っている。The powerless do have power. もう一度、僕らはその力を信じるときなのではないかと思う。たとえ目の前に見たくもない現実が突きつけられたとしても。 *1 このあたりの流れは佐々木敦著『ニッポンの思想』に詳しい。 *2 『構造と力』刊行30周年 https://realkyoto.jp/blog/kozotochikara/ *3 From the river to the sea (川から海まで)とはヨルダン川から地中海のこと。もともとパレスチナと呼ばれた地をパレスチナ人が取り戻すための政治的なスローガンとして使われている。https://en.wikipedia.org/wiki/From_the_river_to_the_sea *4 蓮實重彦も渋谷の再開発に苦言を呈しているが麗郷が再開発でなくなるのは間違いなので訂正してほしい。 https://www.webchikuma.jp/articles/-/3242
FEATURE
- 2026/01/14
-

-
BALMUNG / chloma / GB MOUTHとAVYSSのコラボアイテムの詳細を公開
ルックをキャラ化した「Curated by AVYSS」の新ビジュアル公開
more
- 2026/01/06
-

-
個を起点に装いとして立ち上がる|POP-UP STORE「Curated by AVYSS」が開催
BALMUNG、chloma、GB MOUTH 参加
more
- 2025/12/29
-

-
AVYSS ENCOUNTERS 2025 vol.3
2025年記憶に残っている5つの何か more