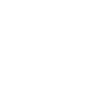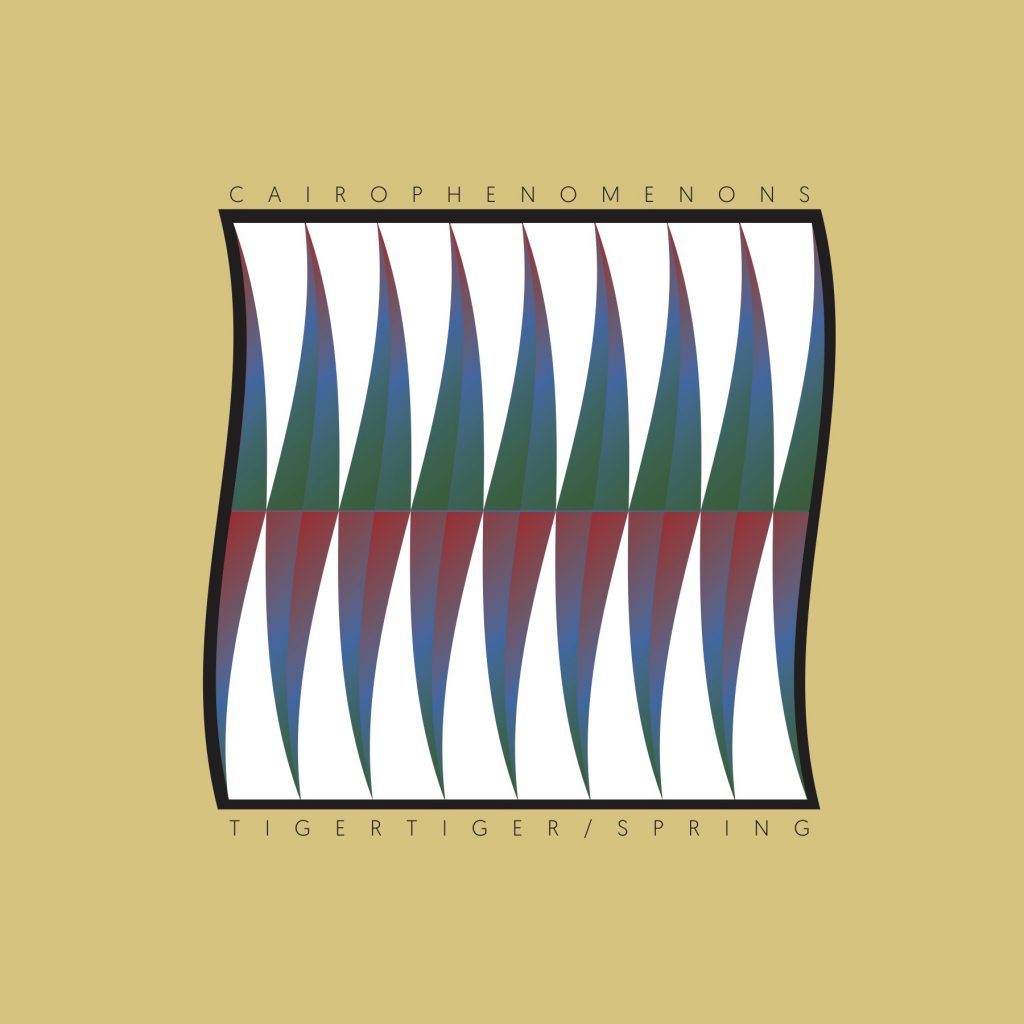Cairophenomenons interview
2019/07/29
心地良さの中に潜む奇妙な違和感。

今年3月から3ヶ月連続でシングルを配信リリースした東京拠点に活動するインディバンドCairophenomenons。MV撮影の合間に行ったインタビューは、結成から6年に及ぶ活動について、そして楽曲の奥に漂う奇妙な違和感について。
photo by Yuki Kikuchi
– 結成の経緯から教えてください。
Nakamura – 僕とArayaは同じコピーバンドのサークルで、音楽の話はしてたんですけど、1回も一緒にバンドをしないまま彼はサークルを辞めてしまいまして。
– なんで辞めたの?
Araya – お金ないし、DJとかやってみたいなって。高校生ぐらいからエレクトロとかテクノのほうが好きだったんで、そっちやりたいなと思って辞めたんです。
Nakamura – だけどそれをよそに僕がオリジナルで、ほんと8小節ぐらいのデモで聞かせて、一緒にバンドしないか?って言って。で、一個上の先輩で音楽の話できる人がいて、その人がドラムで入って、ちょうどその時に僕とRinkaiくんは地元が一緒で。
Rinkai – 2人とも鹿児島で。
Nakamura – (Rinkaiが)高校の先輩なんです。ちょうど彼は就職で上京して来てて。
Rinkai – とりあえず1年働いて、勤務先をちょっと変えようかなと思って、退職してた時に声かけてくれて。じゃあもっかいバンドやろっかみたいな感じで。バンド名も最初はあったような、なかったような状態で始めて。
Nakamura – 名字の頭文字、KAT-TUNみたいな感じで名字の頭文字取ろうって話で。Sは、そのときドラムがサトウさんだったんですよ。ArayaのA、NakamuraのN、Rinkai MaenoのMで、sanmって。
Araya – ちょっと待って、Endless Summerは何だった?
Nakamura – Endless Summerは、ややこしくなる、まじで。
Rinkai – 最初、Endless Summerってバンド名でいろんなライブハウスにデモとかを送ってて。
Nakamura – いや違う。1回sanmで初めてのライブ出たんですけど、さすがにこれかっこ悪いぞみたいになって。
Araya – え、そうだっけ?
Rinkai – いやいや、Endless Summerが先。Endless Summerで、なんかどのライブハウスからもメロコアのバンドだと思って聴かなかったみたいな話とか、いや聞いたら全然メロコアじゃないんだね、みたいな。
Araya – あれ、どっちだっけ。分かんねえ。
Nakamura – いや、ちょっともう謎だ。まぁEndless Summer期もありました。
– それは全然知らなかった。
Rinkai – それから、S、A、M、Nで、どう並べようかってなって、それでsanmになったんですよ。
Araya – 深い意味はないね。
Rinkai – 全くないね。
Nakamura – 深い意味は本当にない。Jesse Ruinsもないんですか?
– 人の名前みたいでもあるし、グループ名みたいでもある名前にしたくてJesseとRuinsを適当に選んで、そしたら友人に教えてもらったのが「Jesseは古い意味で神が存在するみたいな意味」があると。Ruinsは破滅。で、その当時イギリスのザ・ガーディアンっていう新聞に取り上げられた際に「明るい要素と暗い要素が一つの曲に共存している」って書かれてて、対極にあるものが一つのものとして共存しているってのは名前の意味に繋がってくるなと。たまたま意味が繋がってた感じ。
Araya – 名前からして、なんか持ってたってことか。
Nakamura – そもそも、結成前に僕やArayaはHotel Mexicoの追っかけみたいな感じだったので。東京にHotel Mexicoが来たら、来るぞっつって行ったりして。Cuz Me Painとかもかっこいいなと思って聴いてて。そういうのもあって、バンドしたいっていうのがあった。
Araya – こういうことをやってみたいよねっていう。

– 調べたところによると結成が2013年。
Araya – もうそんな昔だったんですか。
Rinkai – 6年か。
– 最初は今とは違う音楽性だった?
Nakamura – 最初はあの頃の〈Captured Tracks〉とかチルウェイヴとかがすごい流行ってた時だったので、もろそんな感じでしたね。
– 当時からDYGLとかはすごく近い存在だったの?
Nakamura – 最初全然繋がってなくて、それこそRhyming Slangで。
Rinkai – 当時のドラマーがDYGLのサンクラのリンクを僕らのバンドのLINEに送ってきて、まじ最高だよみたいな。
Nakamura – 違うよ。DYGLじゃなくて、アキヤマくんの個人名義で、何だっけな。それはHi-Hi-Whoopeeに載ってて。
Araya – 懐かしいな、やば。
Nakamura – すげえなと思ってたら同い年ぐらいだったって後から知るんだけど。
Rinkai – いざ対バンした時に、アキヤマくんが今すぐにでも改名した方がいいってめっちゃ言ってくれて。sanmっていう名前と曲のイメージ合わな過ぎてるからって。
Nakamura – すごい真剣にね。プールの楽屋でね。で、初めてRhyming出た後ぐらいにそのドラムのサトウくんって人が抜けて。その次のケイくんが入った。
Araya – ケイくんが、S、A、N、Mの中に俺いないじゃんって。
– ケイくんきっかけだったんだね。
Nakamura – 順序的に言うとその前にJesse Ruinsのリミックスに参加させてもらって。リミックス盤が〈MAGNIPH〉発売だったので、それで春日さんに聞いてもらってら、アルバム出しましょうってなったんですよ。
Araya – ケイくんが、改名するなら頭文字が最初の方がいいって言ったんだよ。あと国名の縛りがあって。で、アルバムのタイミングでCairoになったと。で、ケイくんも脱退して、さらに名前を変えたと。
Rinkai – エゴサができなかったんですよ。自分たちでライブ終わって、Cairoで調べてもエジプトの情勢ばっか出てくるんですよ。
Araya – もうCairoって呼ばれ始めてたから、Cairoは残したくて、かつ省略してもCairoで呼べるやつで。
Nakamura – WOOMANのリリパが渋谷HOMEであって。その時に「今日は大事なお知らせがあります。Cairophenomenonsに改名します。」って言って。sanmからCairophenomenonsにかけての経緯はこんな感じかな。
Rinkai – Cairophenomenonsになった時はまだ僕ら3人なんですけど。サポートメンバーとしてMizukiがレコーディングも参加してて。MizukiはYkiki Beatもまだやっててたんですけど。

– なぜMizukiくんが参加することになったの?
Rinkai – モトくんってTENDOUJIのライブ写真撮ったりとか、いろんなバンドのMV撮ったりしてる子なんですけど、その子に何度かサポートドラムで入ってもらってライブしてて。その時期に僕がDYGLのリリパを観に行ったらMizukiがいて、ドラマーが抜けたみたいな話とか近況報告みたいな感じでしたら「いや、全然叩くんだけど」みたいなことを言ってくれて。で、スタジオ入ってみようかって。で、ちょうどモトくんも映像が忙しくなってたんですよね。じゃあ、Mizuki入れて今後活動していこうかみたいな。とりあえずサポートですけど。
Araya – 俺知らねえな、その辺。
Rinkai – いや、絶対知ってるよ。
– Mizukiくんにも話を聞きたいけど、今撮影中なので後で話を聞きましょう。(Mizuki、MV撮影中)
Rinkai – だからsanm期は〈Miles Apart〉のカセットと、Jesse Ruinsのリミックスに参加したのと、あと〈Niw! Records〉から7インチリリースしました。あれたまにメルカリとかで高値で見るんですけど、普通にJETSETでまだ在庫あります。
Nakamura – Cairoはアルバム1枚と、Batman Winksとスプリット。

– Mizukiくんが戻ってきたので、Mizukiパートやりましょうか。
Mizuki – ちょうど僕もドラムを叩けるバンドがなくなったというか。Ykiki Beatの終わりが公表される前に、じゃあドラムを続けられる環境を探さなきゃなみたいなところで、ちょうどまだそんなに面識がなかった気がするRinkaiとライブハウスで会って。新代田FEVERの、しかもDYGLの公演ですかね。ドラムを叩けるとこを探してるんだよね、みたいな話をRinkaiさんにしたら、うちもドラマーがいないんだよねみたいな話になって。じゃあ、やるやるみたいな感じでね。
– メンバー役回りとしてはNakamuraくんとArayaが曲を作ってるのかな?
Araya – 主にそうですね、2人で作ってって、スタジオで合わせてみて変えるところがあれば必要に応じて変えるっていう感じ。もうある程度は形になってて、やってみて納得いかなかったら、その納得いかない部分を試行錯誤するって感じですかね。曲が出来て、自分でいいなと思ったらみんなに聴かせる。だから聴かせない曲のほうが多いっていう感じだな。
Nakamura – 僕は結構逆かもしれなくて、バンド4人いるんで、自分の中でちょっとでも形作ったものは誰かに聴かせて、何か生まれたらそっちのほうが面白いなっていう感じで。僕はArayaよりは数は多く出しますね。
– シーンの潮流みたいなものはバンドとしてはどう消化してる?
Nakamura – 結構コードをあらったりして、それを自分なりに並べ替えるじゃないですけど、自分なりのコード感を出せないかなみたいな。
– ベースとドラムの2人はスタジオで考えていくみたいな感じかな?
Rinkai – そうですね、結局デモで大きく変わるのはどっちかのギターなんですけどね。
Araya – え、そうか。ベースも変わると思うけど。
Rinkai – よくお尻が伸びるとかあるね。
– 今回の3ヶ月連続でシングルリリースについて聞かせてください。
Nakamura – 実は今まで配信だけでリリースってしたことがなくて。何かしらフィジカルがあって、配信もあるっていう感じだったんですけど、今回はなんか逆でやってみたくて。まず配信して、ちゃんと曲聴いてもらってから、後でまとめてフィジカル出すみたいな形にしてみたくて。バンドとしてはもっとバンド名の露出を上げたいっていうのもあるし、もっといろんな人に聴いてもらいたいっていうのもあって、とりあえず1曲1曲出すってことによって、それだけでバンドの名前が出る回数も増えるし、それに対してのプロモーションもできることもあって、3ヶ月連続で配信しようっていう形で進むことになりましたね。「In The Pye」のMVはミツメの洋次郎さんに頼んで。
– 洋次郎とはどういう経緯で一緒にやることになったの?
Nakamura – Rinkaiくんが、橋本竜樹さんのレーベル〈de.te.ri.o.ra.tion〉の手伝いをしてるんですよ。
Rinkai – 手伝いと言えるのか分からないですけど。そこで洋次郎さんと会うことがあったり、それこそミツメのライブ行ってしゃべったりとか。その3ヶ月配信の話もしてて、1曲づつビデオも付けようと思ってるみたいな話をした時に、お願いしたら、タイミングさえ合えば是非と言ってもらえたので、ありがとうございます!という感じで。
– 他の曲のMVを撮ってる人を紹介してもらえますか。
Nakamura – 「Prochet」はレイチェルさん。なんか前から知ってて、いい感じだねとは言ってたんですけど、全然つながりがなくて。そしたらMizukiの先輩のバンドのMVを撮ってたんですよ。それでお願いしたら、引き受けてくださったって感じですね。「In Ten Years」はナカムラミキさんっていう。今イギリスに住んでるんだっけ?くまちゃんシールっていう人のMVを全部作ってる方で、Arayaがいいって言ってて。
Araya – Emerald Fourとか撮ってる方だよね。
Nakamura – さっきも話したんですけど、今まで自分達で映像作ってたんです。iPhoneで撮ってiMovieで編集してみたいな。だけど、ちょっと違う世界観っていうか、違う人の視点から作ってもらいたいなと。
– ジャケットや他のビジュアル全般はどうですか?
Nakamura – カセットは違う人にお願いしたんですけど、この前出した7インチとかは自分が作ってて。今回のジャケットも、もう本当に外部の、シバタリョウさんっていうイラストレーターの方にお願いしました。バンドの中で新しい試みをしてみたいなっていう感じですね。

– 結成から6年も経つと自分達も周りも変化していくと思うけど、今バンドの原動力ってなんでしょう。
Nakamura – いい曲ってちょっとなんかニュアンスがすごいフワっとしますけど、すごいいい曲を作りたいんですけどまだ作れてないので、それですね。
Araya – 自分で納得できてないっていうのは一つは、作るほうとしてはあるかな。でも、6年やってる感覚ないよね。体感2年くらいだよね。
– 2年は短くないか。
Nakamura – あんまりまだ満足感がないっていうか、それですね。続いてけてる理由としては僕はそれがありますね。
Araya – でも売れたいっていうのはあるよな。まだ売れたいっていう気持ちはある。
Mizuki – 僕はあんまり売れることには興味ないけどね。結果として売れたらそれはそれでいいけどね。
Araya – でもね、まぁそうなんだよ。
Rinkai – こう言ってるけど、結果として売れればいいって思ってるでしょ。
Araya – 自分がいい曲だと思うのが世の中に認められたら。
Mizuki – 売れたいからが入っちゃうと。
Rinkai – いや、考えてることは一緒だよね。
Araya – 夢はあるっていうこと?
Mizuki – まぁそうですね。夢は持ってる。
Araya – I have a dream.
Mizuki – うん、キング牧師ね。
Araya – なんとかかんとかだよね。
Mizuki – だから「いいもの」を作りたいですよね。それが評価されたらいいなぐらいの。
Araya – やっぱり生きていくこととさ、音楽をすることの葛藤は常にあるかな。
– 葛藤?
Nakamura – ボーカリストとして葛藤は常に抱えてるよね。
Araya – どうしたらいいかなって。分かんない。だからいずれにせよ、結局その曲を作るとかっていうのが、どこか認めてもらいたいっていうところじゃないの。だから英詞であれ日本詞であれ、認めてもらいたいのは認めてもらいたいから。だから自分でもね、よく分かんなくなる時があるんだよな。
– 誰に認めてもらいたい?
Araya – それはね、じゃあ誰に認めてもらいたいんだろうっていうさ。でも何だろうな、何かこう社会的にあれなんじゃないかな。どうも満たされないとか欠落してる何かがある部分を多分補おうとしてるんだと思うんだよね。
Mizuki – 音楽活動によって?
Araya – 人間のコミュニティの中でこう。ただ、だからそう、じゃあ何で英詞かって言ったら、もうフワフワッと口ずさんだ時の気持ちの良さっていうか、結局聴いてる音楽に寄っちゃうのかな。
Nakamura – そうだよね。どうしても日本語だと違和感があるっていうか。

– ちなみに歌詞はどんな内容なのかな?
Mizuki – それこそArayaの承認欲求と生活に即した不満からきてる歌詞が多いよね。
Nakamura – 歌詞に関しては、僕が作った曲もArayaが書いてるので。
Araya – 不満から来ますね。だから1回ハッピーな歌詞の曲を作ってみたいけど、現状では絶対できない。
Mizuki – 歌詞の翻訳するの僕がやったりするんですけど、不満だ。で終わるんですよ。だからこうしたいとか、こここうしたいとかじゃなくて。
Araya – 結局止まってるんすね。ここが嫌だっていう、ちょっと村上春樹とかね、エヴァとかね、じゃあそのクライマックスどうなるのっていったら、何も変わってないからね。
– 結局現実は…。みたいな。
Nakamura – そういうのは僕も持ってるもんね。「結局現実は」って。だから曲のメロディーとか音色とかエフェクトとかは気持ちよさ重視なんですけど。結局逃げ切れないっていうのは分かってるっていう。
– 楽曲自体にも出てるような気もするけどね。気持ちよさだけじゃない感じ。
Mizuki – 奇妙さとか違和感とかが多分出てると思いますね。
– 抜け切らない何かみたいな。
Mizuki – ありますあります。
Araya – だから俺が、自身で何かを超えればってことだ。多分解決したいんだと思うんすよね、自分でも。俺が変われば曲も変わるみたいな。
Nakamura – 曲は変わるでしょうね。
Mizuki – 書く歌詞も全然変わるでしょ。
Araya – そういうことか。今、しっくりきましたね。すげえな、これ。
Nakamura – なんか良かったね。
Mizuki – 僕、わりと完結したデモをArayaに送った時に、もっと変えたほうがいいって言われて。僕としてはすごく歌モノのポップスで、音楽的に完結したデモを作ったつもりだったのに、そのときArayaの中では腑に落ちなかったっていうのは、なんか今話してたとこもあったのかなって思った。

– 結果的に今のCairophenomenonsの音楽性を決定付けてるって事でもあるというか。
Mizuki – ってことはバンド的にはArayaがそんなに解決しないほうがいいのかな。
Araya – え。
Mizuki – 今後どうしていくかっていう話にもつながってくるから。
Araya – ただね、やっぱりでも結局自分の違う面も見たいっていうか、多分このままじゃ駄目だなっていうところにずっといるっていう。なんかこれでいいんじゃんって思ったら終わりか。どうなんだろ。
Mizuki – これでいいんじゃんでやってみて、先が見えてきたらまた先に行くんじゃない。
Araya – そうだな。分かんないけど、違う景色っていうか違う所に行ってみたいなっていう。
– その意思はあったほうがいいんじゃない。
Araya – じゃあプライベート面での俺は何を解決すればいいんだろう。
Nakamura – 知らないよ。
Rinkai – それは今言わなくてもいいと思う。
Mizuki – むしろ言わないほうがいい。
Araya – なんでなんで。

– この話を読んだら、曲の聴こえ方が変わってきそう。
Nakamura – 今後、突き抜けるかもしれないですしね。
Mizuki – やっぱり、ばっちり人間性が出てるってことだね。こういうのを言語化したことはなかったよね。
Araya – だね。インタビューって、そういう側面もあるのかと思ってさ。
Nakamura – じゃあ今後について相談を。インタビュアーに相談をするっていう。
Mizuki – 完全にもう先輩と後輩の尺図そのまま降りてきてるっていうね。僕はでも歌ものがやりたいな。歌が映える曲をやりたい。
Araya – 自分ではね、映えてるつもりなんだけどね。
Mizuki – だんだんと最近はそういう感じになってきてるなっていう気はしますね。
– 歌が輪郭が出てきてる?
Rinkai – 「In The Pye」とか「Prochet」とかは特にそういう感じが出てるような気がする。
Mizuki – 前はもっと歌が楽器の鳴り方に近いところがあった。
Rinkai – 確かにPAにもそういう注文してたしね。歌はもう聴こえてるか聴こえてないかぐらい、楽器の一部だと思ってくださいみたいなことを言わなくなったね。
Mizuki – やっぱり僕は途中から入ってるので、何となく若干客観視をしてしまうというか。
– それって前のいたバンドと比べてしまうものなの?
Mizuki – いや、そこも僕の音楽的趣向の変化もあるような気がしますね。Cairoに入ってまた違う音楽に触れて、僕もだんだんCairoに染まっていって、こういうベースがあるならこういうふうな音楽やっていきたいな、みたいなのが最近徐々に出てきてる感じですかね。とりあえずは、その配信の3曲のフィジカルリリースと、その先には一応ミニアルバムを制作する予定があるので。
Araya – SakumaさんはJesse Ruinsの時とか、今のソロのあれもそうですけど、曲できたけどJesseっぽくないなみたいな、そういうところで却下するみたいなことってあります?今のプロジェクトっぽくはないなっていうところでボツにするっていうか。
– それはないかな。やりたいことがある意味ではっきりしてて。
Mizuki – そういうのがあるの?
Araya – うん、だからなんかCairoっぽくないなっていうところでさ、ボツになってるのよ、生み出されたものが。だからそれを取り払えば、変わるんじゃないかな。
Mizuki – いや、そうでしょ。
– それを受け入れるようになれたらってことかな。
Mizuki – これでArayaがそういうのがなくなって、Cairoが突然売れたらなんか嫌だな。
Araya – 成長の先に成功があったらいい。
Mizuki – いや、まぁそうだけどね。

– 少し思ったのは、Mizukiくんが入って雰囲気変わったところはありそうだね。
Rinkai – それは大いにあると思います。
Araya – でも、どう変わったかっていうと分かんないな。
– 結構口出すのかな?
Mizuki – 口出してますね。
Rinkai – そう、今までそういう人はいなかったバンドなので。リハ中も、ライブ後とか。こうだったよねみたいな指摘とか。
Araya – 俺はその、安心感みたいなものを感じましたね。
– 安心感というと?
Araya – これは難しいな。んー例えば演奏中だったら、自分のプレイにより集中できるっていうか。
Rinkai – ドラムに対する安心感っていうことね。
Mizuki – それもっと早くたどり着けたでしょ。
Araya – でもどうかな、全体的な安心感が増えた気がするんだよね、プレイだけじゃなくて。
Mizuki – 活動内容とかってこと?
Araya – いや、分かんない。これ分かんねえや。
– また悩みが一つ増えたかもね。

Mizuki – そのプレイに対するっていうのは、ずっと歌もの歌ものって言ってるんで、歌が映えるように、Arayaが歌いやすいように、弾きやすいようにドラムを叩くようには一応意識してるつもりではいます。
Araya – ドラムの音数は減ってきてるよね。
Mizuki – うん、減らす意識はしてますね。
Rinkai – ビートで持ってく音楽じゃないんじゃない。いかに上が映えるかで。
Araya – ビートで持ってくほうに変わってったらどうですか、これが。
Mizuki – でも元々僕はそっちの音楽、R&Bとかのほうが好きなので。ジャズとかボサノバとか。そうなったらそうなったで全然やれますよ。でも、僕いろんなバンドの人と話すんですけど、Arayaってすげえリズム感いいんですよね。多分本人全然自覚ないと思うんですけど。
Araya – 分かんないね、それは。自分では分かんないね。
Mizuki – ちゃんとこの音楽はどのテンポで弾いて、どういう感じでやると気持ちよくなるのかっていうのを、直感的に分かってるタイプなんですよ。なので僕もそれに即してプレイするというか、それを邪魔しないようにうまく盛り立てられるように意識はしてるつもりです。
Rinkai – この間、Arayaと話してたことがあって。昔ってもっとライブバンドみたいな扱いされること多かったよねって。ライブで、意外と荒ぶるバンドだよねみたいな位置にいたけど、そういえばいつの間にかそこにいないねみたいな話をしてて。結局Mizukiの次に長いのが恐らくケイくんがいた時期で、割とテンションで行くタイプの人だったので、そこの変化はでかい。で、さっき言ったMizukiが入ったことによってバンドの雰囲気が変わったみたいなところでも、今日のライブこうだっただろみたいな話をMizukiが言ってくれるので、そこ僕が一番いろいろ言われてるんですよ。だからそういう意味でも自分を見直すことができるきっかけにもなりました
Mizuki – 多分一番口うるさいのが僕なんじゃないですかね。ですし、バンドとしてこう見えてほしいみたいなのを多分、余計なことをいろいろ考えているんだと思います。好きな音楽が洋楽だっていう話があったじゃないですか。で、いろんな日本に来てくれる海外のバンドのライブとか見てて、それらがやっぱりどっしりしてる。海外のバンドってすごいどっしりしてるなっていつも見てて感じるんです。そういうところをやっぱり自分たちも出していきたいなって。憧れみたいなものなんですけど、それをするにはどうしたらいいかっていうのをライブ見ていろいろ分析して、自分のバンドに持って帰ってきて、こうなんじゃないの、もっとこうしたほうがいいんじゃないっていうのを言っていった結果こうなってしまったっていう。
Rinkai – 「なってしまった」って。
Mizuki – そのライブバンドだったバンドがそうじゃなくなったっていうのは、ちょっと今ああ、そうだったなって、後悔じゃないですけど。
Rinkai – それは全然マイナスのつもりで言った話じゃないんだけど。
Mizuki – Cairoのそういう一面を自分が消してしまったような気がするので、ちょっともったいないことしたのかもなって今思いましたね。
– それはでもケイくんのドラムがってこともあるもんね。
Rinkai – まぁそうですね。それこそ「Clash The Truth」みたいな曲やってた時期だから。そういうテンションで持って行けていい曲だったけど、そういう曲がもうなくなっちゃったしね。
Mizuki – 音楽性がCairoもだんだん変化して落ち着いてきてるっていう言い訳もできるけど、やっぱりそういう一面は消さないで、もっと理解して消さないでおけばよかったかなって思いますね。振れ幅を小さくしてしまったって感じですかね。
Rinkai – それでも今までなかった振れ幅が入ったでしょ。ここからここになったみたいな話。
– そうだね。横に移動したみたいな感じ。でも重なってる部分はあるでしょ。
Rinkai – そう、オーバーラップしてここをこうみたいな。
Araya – 自分が曲を作る時にメンバーのスタイルとかを意識するかっていうと、俺はそうじゃないからさ。あんまり関係ないかな、そういうところは。まぁ俺が突き抜ければ、曲も突き抜けるはずっていう。
Rinkai – 出た。これがインタビューの見出しになってたら嫌だな。でか字で「俺が突き抜けたら曲も突き抜けるはず」って。
Araya – 俺の部屋に飾っておこう。
Rinkai – じゃあ見出しにしてもらう?
Araya – いやいや、それはちょっと恥ずかしいんだけど、でも何か今、新しいヒント得た気がするな。何か来そうな気がする。

category:FEATURE
tags:Cairophenomenons
RELATED
-
2019/03/18
Cairophenomenonsが新曲「In The Pye」をリリース
『TIGER TIGER / SPRING』に続くニューシングル。 東京を拠点にするバンド、Cairophenomenonsが新曲「In The Pye」を3/15(金)にリリースした。「In The Pye」は、昨年に新作7インチ『TIGER TIGER / SPRING』に続くニューシングルとなる。作詞作曲を手がけたのはギターボーカルのYuichiro Araya。カイロ的なサイケサウンドスケープとビターなメロディが心地良い。ドゥドゥッピドゥ。 今回のアートワークはイライストレーターのシバタリョウが担当しており、3/22 – 4/21の期間に開催される同氏の個展最終日にCairophenomenonsのインストアライブも決定している。
-
2018/10/01
Cairophenomenonsが7インチのリリースを発表
ドリームソフトサイケインディのCairophenomenonsが昨年のカセットEP『Cue-EP』以来の単独作が7インチでリリース。 Miles Apartのカセットシリーズ『Cassette Tapes Club』で最初にリリースしたバンドだったsanm。その後Cairo、そしてCairophenomenonsと改名を繰り返した。彼らが、昨年リリースしたEP『Cue-EP』以来の単独作となるシングル『TigerTiger / Spring』が7インチでリリースされることが発表された。 リリース元のMagniphのサイトには”過去最高”と書かれている。期待したい。 ”TigerTiger”は、これまで彼らが展開してきたローファイ〜ソフトサイケな音楽性を過去最高にポップに昇華した名曲。 Captured Tracksに代表される10年代の海外インディ・ロック・シーンとも共鳴するドリーミーでサイケデリックな質感と、センチメンタルなソングライティングに心揺さぶられます。 B面”Spring”は、ノスタルジックなギターの音色とマスロック的アプローチのリズムを融合させた、 爽やかな甘口インディ・ポップ。スペーシーに展開していく中盤からの浮遊感たっぷりのアレンジも心地よいナンバーです。 7インチは12月上旬リリースとのこと。詳細はこちら。
-
2021/02/24
Yung Kiss interview
『Z-POP』 – 生活のリアリティと音楽 – 2020年、コロナウイルスの感染拡大によるロックダウンが続く東京で発足したアーティストたちによる「今を生き抜く」プロジェクト2021survive。Yung Kissは2021surviveメンバーのLingnaとKen truthsによって結成された、Z世代によるJ-POPユニットである。リアルな場での露出は一度もないままに1st Album “Z-POP”をリリースした彼らに話を聞いた。 取材・構成:木下真紀 – 『Z-pop』のリリースおめでとうございます。本アルバムはいつ頃制作されたものなのでしょうか? りんな – ありがとうございます。2020年の6月にKen truthsとYung Kissを始めて、そこから2021年の始めくらいまで作り続けてた感じですね。 – 2020年6月といえば、緊急事態宣言が出た後のタイミングですね。二人の生活や環境はどのように変わりましたか? Ken – 宣言が発令されてからはみんなと同じで、家の中で過ごす時間がほとんどになりました。それまでは遊びに行ったりクラブで音楽聴いたりしていた時間も、曲を作るかUber Eatsを頼んでNetflix観るしかない、みたいな。 りんな – ライブもできなくなったし、友達とも会えなくなった。でも曲はとにかくたくさんできてたから、表現の場所とか方法は自分たちで作り出すしかなかったです。 – コロナ禍ではスタジオに入るのも難しくなっていると思います。具体的に、二人はどのように制作を進めていったのですか? りんな – 基本的に僕が一人でビートを作って、やばいのができたらKen truthsに送ったりしてました。二人とも家が近いから、緊急事態宣言が明けてからは僕の部屋で遊びながら作ることが多かったと思う。 Ken – 俺は2019年くらいまではバンドをやってて、ちゃんとDTMをやり始めたのが去年からだったので、いわゆる宅録ってこんなもんなのかって思ってました。 りんな – 人と関わることが減ったから、ノイズが減ったのは良かったかもね。流行りとか気にしないで好き勝手気持ちいいことをやってた感じで。家のスピーカーで鳴る音とクラブのでかいスピーカーで鳴る音って違うから、気持ち良さ自体も変わってくるんですよね。ビートとかベースの置き方とかは特に変化したところかもしれないです。 – いざ『Z-POP』をリリースしてみて、自分たちのなかでどのようなアルバムになったと感じていますか? りんな – 2020年のロックダウンから2021年にかけての生活に記録みたいな感じですかね。クラブとかライブとか大音量で音楽を聞くような体験と離れたから、暮らしのグルーヴ感とすごく近いところに鳴ってる音楽を「いいな」って思うようになって。だから自分たちでつくるものも暮らしと共鳴するものにしたかった。 Ken – 例えばですけど、TikTokの15秒のバズよりももっと長いスパンでリスナーの人生に寄り添えるような作品を作りたいと思っていて。1ヶ月単位でトレンドが変わっていくような流動的な音楽シーンのなかでも、普遍的にいいと思えるような曲を集めたのがZ-POPだと思います。 – 二人が「Z世代のJ-POPデュオ」を謳う一方で、実際にアルバムを聴いてみるといろんな音楽ジャンルの要素が混ざり合っているような印象を受けました。それぞれの音楽的なルーツについて聞かせてください。 りんな – 僕の場合は家の車でかかってたミスチルのALIVEとかRadioheadのairbagとかが根本にある感じがします。カーステレオから流れるデッドなキックの感じが印象に残ってて。それでミスチルをギターで弾きたくて、貯めた小遣いでハードオフに売ってた7000円くらいのレスポールをこっそり買ってきたのが音楽やり始めた最初ですね。 Ken – 初めて買ったアルバムがYUIさんのI LOVED YESTERDAYで、同時期にRed Hot Chili PeppersのBy the Wayに出会ってから意識して音楽を聴くようになりました。小5のときに初めてギターを買ってもらったけどずっとホコリをかぶってて、中学生でOasisとかを練習し始めてからどんどん音楽にのめり込んでいった感じです。ティーンの頃も今と同じでカッコイイと思うものはなんでも聴いてました。インディーロックが多かったんですけど、当時流行ってたOdd FutureとかFlying Lotusとかもチェックしてましたね。高校でUKのロック中心にコピーバンドをやってて、上京してからは3年くらいパンク系のバンドで活動してました。 りんな – By The Way俺もめっちゃ聴いてた!でもKen truthsがUKにはまってた頃僕はandymoriとかハヌマーンとか国内のロックバンドにめっちゃはまってて、曲作り始めたのもandymoriのアルバム聴いたのがきっかけなんですよね。その後はBurialとかNicolas JaarとかSOPHIEとかエクスペリメンタル寄りのダンスミュージックにはまっていって、その辺のルーツが全然かぶってないのも面白いなって。 – 二人が「Z世代のJ-POPデュオ」を謳う理由は? Ken – シンガーとかラッパーとか色んな言い方があるなかでも、単純にそれが一番しっくりきました。 りんな
FEATURE
- 2026/03/03
-

-
「森、道、市場2026」にてAVYSS企画「AVYSS Body」が開催
5月23日 MORI.MICHI.DISCO.STAGE (遊園地エリア)
more
- 2026/02/16
-

-
交差する円、重なる身体|AVYSS Circle 2026 photo report
アビサー2026の記録写真 more
- 2026/02/02
-

-
渋谷から新木場廃倉庫レイヴへ|「AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding)」開催
2/13(金) 渋谷から新木場へ座標を再設定
more