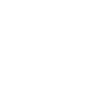Thinking Framework – 考える枠組み vol.5
2019/07/07
5. バーニング

村上春樹の短編小説『納屋を焼く』を原作としたイ・チャンドンの『バーニング』は独特のトーンに覆われた静かで美しい映画だった。
原作は小説家であり妻帯者である物語の語り部となる<僕>と、たまにモデルの仕事をしているが自由人である年が一回り下の女の子<彼女>との都会的でカジュアルな関係から始まる。
あるとき彼女はバーのカウンターで僕と世間話をしながら、実際には無い蜜柑をむいて食べるパントマイムを行う。その動作に「まわりから現実感が吸い取られていくような」特別なものを感じ関心する僕に彼女は説明する「こんなの簡単よ。そこに蜜柑があると思いこむんじゃなくて、そこに蜜柑がないことを忘れればいいのよ」と。
「ない」ということを忘れる。この実在と非実在の関係がこの物語では重要なテーマとなる。
その後、親の遺産を手にした彼女はナイジェリアに長い旅行にでかけ、現地で知り合った日本人のボーイフレンドと帰国する。その貿易商を営んでいるらしい男が加わり物語は別の方向へ進み出す。
映画もこの実在と非実在の関係をテーマに原作と同じように物語が進む。ただ映画と原作では大きく異なるところがある。それは社会との関係であり距離の取り方だ。
村上春樹の作品群は、社会との関係によって大きく二つの期間*1 に分けることができる。最初はなるべく社会との関わりを持たないようにした期間で、デタッチメント期と呼ばれる。この期間は彼がデビューした1979年から1993年頃まで続く。長編で言うと『風の歌を聴け』から『国境の南、太陽の西』がこの期間に書かれた。次の期間は社会との関わりを積極的に持とうとした期間でコミットメント期と呼ばれる。コミットメント期は1994年頃から始まり現在も続いている。長編で言うと『ねじまき鳥クロニクル』からとなる。
原作の『納屋を焼く』は1983年に書かれたデタッチメント期の作品であり、80年代という時代性もあるが、現実の社会と切り離されたどこか浮世離れした世界の物語だ。それに対して映画は舞台を現在の韓国に移し、積極的に現実の社会と地続きである現在の韓国とその中で生きる若者を描こうとする。
物語の視点となる<僕>は小説家でもなければ妻帯者でもない。素朴な風貌の兵役帰りで小説家志望ではあるが、まだ何も書いていない無職の青年ジョンスに。<彼女>は年の離れた女の子ではなくジョンスの幼じみのヘミになる。二人の関係もカジュアルなものではなく、量販店のコンパニオンと客として再会するとすぐに恋仲となる。
ヘミがアフリカへの旅行中に知り合い一緒に帰国する男ベンだけは原作と同じ設定であるが、原作ではフラットであった僕ジョンスとの関係は映画では少し異なる。ジョンスがニートのような生活をしていることやヘミへの思いが強いことからか、ジョンスは若くして金持ちのベンを訝しがり、ヘミを取り合う三角関係のようになる。
原作には仕事をしているようでもなく、何をして金を得ているか分からない男に対して僕が「まるでギャッズビーだね」とつぶやく描写がある。映画でもジョンスは同じセリフを吐くが「韓国にはギャッズビーが多い」と付け加える。
これは、日雇い労働のようなことをしながら日銭を稼ぐジョンスからみた韓国の富裕層の姿であり、どちらか一方に固定化してしまった格差社会を揶揄しているのだろう。そういった原作には無かった現実の社会問題の描写が映画には随所に散りばめられている。
映画の中盤のハイライトで物語が動き出す、ジョンスの実家の庭で三人が大麻を吸うシーンもそうだ。ジョンスの暮らす誰もいなくなった実家は北朝鮮との軍事境界線の近くにあり、日中は北朝鮮のプロバガンダ放送が休みなく聞こえる。
ヘミが大麻を吸ってリラックスし上半身裸になって踊り出すシーンは、この映画でもっとも美しいシーンの一つであるが、ヘミが空中に投げ出す両手の先にはマジックアワーの幻想的な夕焼け空をバックに韓国の国旗が映る。
更に面白いのは、この作品は原作の『納屋を焼く』ではなく村上春樹がデタッチメント期からコミットメント期に移行する最初の長編小説である『ねじまき鳥クロニクル』から着想を得たと思われるシーンをいくつか盛り込んでいるところだ。
『ねじまき鳥クロニクル』では猫がいなくなるところから物語が始まるが、ヘミが飼っている姿を見せない猫もやはりいなくなる。ジョンスの実家ににかかる無言電話も最終的には妻クミコからだと気づくことになる謎の女からの電話や、取られることの無かった電話を思わせる。
極め付けはヘミが幼い頃に井戸に落ちているということだろう。『ねじまき鳥クロニクル』で井戸とは、ノモンハンで間宮中尉が銃殺の代わりに落ちることになった井戸であり、主人公のオカダトオルが自ら下りた世田谷の井戸だ。冷たい井戸の底でオカダトオルはひとりでじっと考える。考えることによって現実の壁を抜け、時空を超えて様々なものと繋がることになる。それは行方不明の妻であり、ノモンハンから現在に形を変えながらも続く絶対的な悪、現代の日本社会が未だ清算することのできていない負債の一部だ。
昨今、ラジオDJを務めるなど小説や翻訳以外での活動も慌ただしい村上春樹は、朝日新聞の「平成の30冊」の企画で、自身の作品が1位に『1Q84』と10位に『ねじまき鳥クロニクル』と二作が選ばれたことで、インタビュー*2 に応じている。
この自身の活動を振り返るインタビューで、『ねじまき鳥クロニクル』の『壁抜け』を語ったあと、95年に阪神大震災と地下鉄サリン事件が起こります。という社会との関係を問われた質問に村上春樹は以下のように答えている。
「個人的な信念として、小説家は作品がすべてで、正しいことばっかり言っていると作品はろくなことにならないと思っている。ただ、作家といっても一市民であるわけで、小説家としてのアイデンティティーやレベルを保ちつつ、市民として正しいことをしないといけない。正論ばかり言ってイマジネーションが壊れないよう、バランスを保つのが大事だけど。」
正論ばかり言っていると想像力が壊れる。インタビューを書き起こした文章なので、どれくらい本気で言っているかが分かりにくいが、こういうことを何のてらいもなくさらりと言えるところが、村上春樹の強さであり資質であるように思う。
そして『納屋を焼く』の物語と『ねじまき鳥クロニクル』の想像によっ壁を抜けて現在の社会を描くことができるという力を借りて、韓国の現代社会を描こうとしたイ・チャンドンもまた、この正論よりも想像こそが大切だということを信じている一人であり、イ・チャンドンが村上春樹の作品から読み取り自作に反映したかったことなのではないかと思う。
この映画の最大の謎であるヘミの喪失は、見るものに想像力を働かせることを要求する。ジョンスから見た視点は一方的な視点であり本当に正しいのか。その正論は本当に正論であり正義なのかということを見る我々に突きつける。その視座が出口のない物語と同じように不条理と感じる、この現実社会に有効なのは正論ではなく想像力だということに気づかせてくれるのだ。
Text by Naohiro Nishikawa
(Thinking Framework 2018-2019 前編完)

*1 村上春樹本人はデタッチメント期を更に二つに分け、物語を指向する前の作品をアフォリズム(格言)の時期としている。この期間に書かれた長編作品『風の歌を聴け』と『1978年のピンボール』を本人は習作として気に入っていないようで、この二作を別の期間だったと定義しているのではないかと思う。本人が気に入っていなかったことは、英訳があるにも関わらず長らく英語版が日本国外では発売されていなかったことからも分かる。
category:COLUMN
RELATED
-
2019/04/11
Thinking Framework – 考える枠組み vol.1
1. 2018年代 by Daiki Miyama 現代史は10年を単位としたディケイド、つまり年代で区切られ語られることがある。特に音楽やファッションなどのカルチャーはその様式の記号として年代が使われる。このスネアのリバーブは80年代っぽいとか、このスニーカーのハイテク感は90年代っぽいといった具合に。 しかし変化の進みが早く多様な音楽やファッションの様式を10年という単位で区切るのは無理があるように思う。音楽で90年代と言って思い浮かべるのはグランジだろうか、アシッドジャズだろうか、それともドラムンベースだろうか。ファッションにおいてもそうだ。90年代に今につながるハイテクスニーカーの多くが発明されブームになったのは確かだ。ただ 90年代の足元がすべてハイテクスニーカーだったかというと、当然そんなことはなく、ドクターマーチンなどの定番はもちろん、レッドウイングのエンジニアブーツや UGGのムートンブーツなどもブームになりよく履かれていたように思う。 それでも、10年という区切りが有効な分野もある。そのひとつが進みの遅い音楽メディアの物理フォーマットだ。リスナーが音楽を安心して購買し収集できるようにするためには、音楽メディアの物理フォーマットはファッションのトレンドのようにシーズン毎に変わるわけにはいかない。 レコードブームと言われて久しい昨今だが、アメリカに端を発するレコードブームはがいつから起こったかを考えるとそれは 2008年頃であったように思う。アメリカのレコード会社の業界団体であるアメリカレコード協会(RIAA)のデータによると CDの登場により落ち続けたレコードの売上が初めてプラスに転じるのは 2008年からだ。 USでのレコードの売上枚数。濃い青はアルバムとEP、薄い青はシングル盤を示している。これを見ると90年代のレコードはシングルで成り立っていたことがわかる。参照元:https://www.riaa.com/u-s-sales-database/ その 2008年に何が起こったかを振り返ると Captured Tracks、Mexican Summer、Acéphale、Big Love, The Trilogy Tapesや PANなど今に繋がるインディーシーンを作り上げたインディーレーベルがこぞって設立されたのが、この年だということに気づく。その前後も含めると Italians Do It Better、Secred Bones、DAIS、Burgerなどが2007年で一年早く、Posh IsolationやR.I.P Societyが2009年となる。これらのインディーレーベルの主要なメディアがレコードであることを考えると、2008年から続くレコードブームは彼ら新興のインディーレーベルが主導したブームであると言えるのではないだろうか。 また、スマートフォンや音楽関連のサービスを眺めてみると、世界で最初のスマートフォンであるiPhoneが登場したのが 2007年で、日本ではじめて発売されたiPhone 3Gが2008年。対抗する Androidも2008年に登場している。インディーレーベル御用達の Soundcloudと Bandcampができたのは共に 2007年なので、2008年は今に続く環境が一通り揃った年だったとも言える。 本連載『Thinking Framework – 考える枠組み』では、今に続くレコードブーム/インディーシーンの起源である 2008年をひとつの時代の始まりと捉え2008年代と呼ぶことにする。そうすると 2018年は必然的に 2018年代という新しいディケイドの最初の一年ということになり、今年 2019年はそのディケイドの二年目ということになる。 これは自分だけではなく、多くの人に共感してもらえる感覚ではないかと思うのだけどここ1、2年で何かが大きく変わるんじゃないかというゲームチェンジの予兆みたいなものがある。『10年後から振り返ればここが節目だった』本連載では、そういった視点で現在を捉え、ひとつの目として感じたことを伝えていければと思う。今の時点で振り返れば2008年がいろいろな始まりであったように、2018年は今後の 10年の方向性を決定付ける新しいディケイドの始まりとして後年に記憶される年となるような何かを。 Text by Naohiro Nishikawa
-
2019/04/19
Thinking Framework – 考える枠組み vol.2
2. すべてのことはメッセージか by Daiki Miyama アメリカは私は何者であるというアイデンティティの国であり、私の主張はこうだというメッセージの国でもある。ドナルド・トランプの「Make America Great Again」という選挙のスローガン、Nikeの「Just Do It」や Appleの 「Think Different」のキャッチコピーは当然として、音楽界隈でもこうした メッセージが溢れている。 古くはウッディ・ガスリーのギターに書かれた「This Machine Kills Fascists」。なぜかノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの『Subterranean Homesick Blues』のミュージックビデオに見るメッセージボード(これはピチカート・ファイブのそのものずばり『メッセージソング』のミュージックビデオでも少しだけ引用されている)。最近 Vetementsがコピーして話題になったカート・コバーンのTシャツ「Corporate Magazine Still Suck」もそうだ。 「目にうつるすべてのことはメッセージ」と歌ったのは荒井由実で、この歌は小さい頃は感受性が高くすべてのものからメッセージを受けとることができたという受けて側の話だが、子供でなくても感受性がそれほどでなくても、すべてのものがメッセージを発している。それがアメリカという国だ。 アメリカがシンプルな言葉を使った直接的なメッセージで溢れているのであれば当然それを逆手にとった表現もある。60年代から活躍するアーティストであ るエド・ルシェはシンプルな言葉をキャンバスに描いているが明確なメッセージを意図的に排除した作品を制作してきた。「Japan Is America」のような戦後の日本を批評的に表したような鋭い作品もあるが、多くの作品は抽象的で多 義的であり言葉の意味性を曖昧にしている。 アンディー・ウォーホルの『129 Die in Jet!』は129人が飛行機で死んだと衝撃的な文字が飛び込むが、これは1962年に実際に起きた飛行機事故を報じた New York Mirrorの紙面をそのまま模写したものだ。シンプルで強い言葉が並びなんらかのメッセージを示したサインボードのようにも映るが、そこにある のはメッセージではなく揺るぎない事実だ。 左からEd Ruscha、Andy Warhol、Barbara Kruger 言葉を使ったアーティストと言えば、バーバラ・クルーガーにも言及すべきだろ う。彼女の代表作であるデカルトの「I think, therefore I am(我思う、ゆえに我あり)」をもじった『I shop therefore I am』は消費主義を批判したメッセージ性の強い作品だ。しかしその赤のボックスに白のFuturaフォントを Supremeがロゴとしてコピーし、(もう誰も覚えていないと思うが佐藤可士和も スマップのキャンペーンでコピーしていた)商品として消費されることで、本 来の消費主義批判が消費主義賛歌のスローガンのようにも見える面白さがある。 私は買い物する、ゆえに私である。高額なブランド品を買う動機付けのマントラとして、メッセージは逆転する。 これら先人が行ってきた言葉とメッセージの関係の解体をさらに推し進めるの が、現行のアーティストであるLAのカリ・ソーンヒル・デウィットだ。彼の代表作である事件現場や動物、薬や札束などの強い写真の上と下に写真との関連 が不明確な一見ランダムとさえ思える強い言葉を配置したサインボードは、見る者の社会性や政治的な志向、過去の経験などを通じて様々な事象を思い起こさせる。そして、その強い写真と強い言葉の関連の不明確さに、本来そこにあ るはずのメッセージの不在に見る者は戸惑い揺さぶられる。 Cali Thornhill DeWitt OFF-WHITEのヴァージル・アブローは、このメッセージなき言葉をファッションに持ち込む。Nikeの Air
-
2019/05/02
Thinking Framework – 考える枠組み vol.3
3. ダークウェブと新しい実在論 by Daiki Miyama ティム・バーナーズ=リーがワールド・ワイド・ウェブの元となるハイパーテキストシステムを構想し今年で30年になる。彼はウェブの30年を記念した書簡で現状のウェブには次の問題があると述べている。*1 1) 国家ぐるみのハッキングや攻撃、犯罪行為やオンラインハラスメントのような計画的な悪意 2) ユーザーの利益を犠牲にして誤ったインセンティブを生み出すシステムデザイン、例えば広告売上モデルで商業的報酬を狙ったクリックベイトや偽情報の拡散 3) 暴力や偏見に満ちた調子や性質を持つオンラインでのやりとりが、優れたデザインに反して負の結果をもたらすこと しかしこれらは本当にウェブ、つまりインターネットだけの問題だろうか。1)は反社会的な国家が秘密裏に核爆弾や覚醒剤を製造したり、現実から犯罪やハラスメントがなくならないことに、2)は例えばクレジットカードの情報弱者を騙すリボ払いや面倒だが使わないと損をするポイント制度に、3)は学校の教室や職場などいろんな人間が集まり「自由に議論ができる」とされる場所に普通に見られることであり、どれも現実にある問題と同じではないかと思う。 ティム・バーナーズ=リーのようなシステム屋はこれらの問題をシステムで解決しようと考える。しかしインターネットは彼の構想した様々なテキストを横断的に参照することができるハーパーテキストシステムを超えてもはや現実の一部だ。よってインターネットが現実と同じ問題を持つのは当然の帰結であり、もしこれらの問題を解決したいと思うなら、現実こそを変えるべきではないか。そうではなく、もしインターネットだけをシステムで行動に制限をつけ、彼の考える負の部分をごっそりと削り落としたなら。それは『CODE』でローレンス・レッシグが警告するように現実とはまた別の息苦しい世界となってしまうだろう。 一方で、インターネットは現実とは違うもう一つの世界だと考えたい人達がいるのも事実だ。テレビや新聞などの旧来のメディアが伝える「ネットの声」というのもその一つだろう。それとは別に、現実世界と違いインターネットに行動の匿名性、現実世界では犯罪となるようなものを含めた最大限の自由を求める人達もいる。 もちろん、通常のインターネットでは多くの人が知るように本当の意味での匿名性は担保されていない。もしあなたがインターネットの匿名とされる掲示板に犯罪予告を書けば、次の日曜日の朝に警察がインターホンを鳴らすことになるだろう。これはその掲示板のサーバに書き込みを行ったIPアドレスと時刻が、インターネット・サービス・プロバイダにはそのIPアドレスをその時間に使ったのが誰かがそれぞれ記録されており、警察の要請により開示されるからだ。 逆に言うとこの「IPアドレス」と「そのとき誰が使ったか」という関係を誰にも分からないようにすれば、インターネットでの通信を匿名にすることができる。それを可能にするソフトウェアの一つが2012年に起きた「パソコン遠隔操作事件」でも使われたTorだ。 Torには匿名でインターネット上のサーバーに接続するという機能だけでなく、Torのネットワーク内にTor経由でのみアクセス可能なサーバを匿名で立ち上げることができる。この機能を使って構築された誰が開設したのか、誰がアクセスしたのかが分からないサーバ群が「ダークウェブ」と呼ばれる、完全な匿名性が保たれた現実とは違うもう一つのインターネットだ。 この完全に匿名なインターネットが手に入ると人は何をするのか。木澤佐登志著の『ダークウェブ・アンダーグラウンド 社会秩序を逸脱するネット暗部の住人たち』はダークウェブとその基盤となる暗号学の基礎的な説明*2 から始まり、その住人たちの行動とその変遷を書き記す。 大方の予想通りというべきか、最初に書かれるのは現実のインターネットからは排除された違法な行為だ。特にBitcoinに代表される仮想通貨による金銭の受け渡し手段が確立されると、無料でコピー可能な情報の交換だけではなく物質と金銭の交換。つまりは違法な物の販売も可能となる。 それは法律で禁止された違法薬物の販売から始まり、現実世界からは見放された児童ポルノ、臓器売買、人身売買、殺人請負と真偽が疑わしいものへとエスカレートしていく。そこにはなんでもありだった現実になる前のインターネットや海外のパソコン通信がその過激さだけが誇張され伝えられたあの雰囲気。『危ない1号』や今でもクーロン黒沢が描き続けるあの世界が続く。 本書の見所は、そういった見世物やタブロイド紙的な下世話さだけに止まらず、その根底に流れる思想に行き着くところだ。それも新しい技術が正しい未来を作る『Wired』誌的な思想とは真逆の、民主主義やリベラルを否定する陽の光の下では育たないダークな思想、とりわけ現在のアメリカが突き進む新反動主義(Neoreactionism)へと誘う。 もともとの反動主義とは、革命や終戦で成立した体制を批判し、素晴らしい時代である過去の体制に戻そうとする思想だ。フランス革命を否定し王政を復古したい。共産主義革命を否定し君主制に戻りたい。戦勝国に押し付けられた民主主義を否定し軍国主義に戻したいなどがそれだ。 では、新しい反動主義である新反動主義が否定する現在とは何か。それは行き過ぎたとされる民主主義であり、誰もが平等であるべきという考え、つまり狙われるのはポリティカル・コレクトネスでありリベラルだ。 この新反動主義は Alta-right(オルタナ右翼。つまりはアメリカ版ネトウヨ)と言われる層の基盤となり、ドナルド・トランプを生み出すことにも繋がる。トランプの「政治的な正しさに構っている暇はない」という発言や「Make America Great Again」というスローガンは実に新反動主義的であると言えるだろう。 さらに特筆すべきは、この思想的潮流はなにも新しい技術と産業によって好景気を維持するアメリカから取り残された、田舎に住む白人男性の昔は良かったというノスタルジックな願望だけから生まれた訳ではない。こういった考え方がある程度以上の地位にあるエリート層からも発せられるところだ。例えばPayPalの創業者であり、シリコンバレーのテック業界に多大な影響力を持つPayPalマフィアのドン、ピーター・ティールはリバタリアンでありトランプ支持者だ。 こういった反リベラル主義者やトランプ支持者に対して、リベラルの側は彼らの言説、政策にはエビデンスが無い。感情が優先された間違った言説により世論を間違った方向に導いている。ポスト・トゥルース、真実に基づかない政治だと批判してきた。 それに対する反リベラルの側からの「知的」とされる反論も当然ある。そのリアクションの一つが科学的エビデンスを重視し反リベラルな主張をインターネット上で展開する学者や言論人のネットワーク、「インテレクチュアル・ダークウェブ」*3 だ。 彼らは、ジェンダーや人種の間には乗り越えがたい生物学的差異が存在しており、それは諸々の科学的、統計学的エビデンスによって証明されている。よって行き過ぎたリベラル社会、例えば、IT企業においてプログラミングが不向きとされる女性の雇用を促進することは非合理であり、不利益をもたらすと主張する。 しかし、当然ながら思想であるリベラルに合理性を示すエビデンスなんてものは無い。リベラルの思想の中心である自由であり平等というコンセプトは合理的だから採用されている訳ではない。たとえ全体としては不合理であったとしても誰もが自由に生きるためにはどうすべきかを考えた上でのコンセプトだ。それは決してエビデンスで測れるようなものではないのだ。 生物学的な差異や、自然の摂理、自然界で見られた現象などをエビデンスとして、人間や人間社会に当てはめることがなぜ間違っているのか。それを説明するのがドイツの哲学者マルクス・ガブリエルの近著『なぜ世界は存在しないのか』だ。 ガブリエルは本書の中で、全ての物は実在すると説明する。例えば山手線は実在する路線でありそこを走る電車のことだが、ある人が乗る山手線も、その車両を別の人が外から見たものも、また別の人が空想した山手線も等しく実在するとすれば、創作に登場する山手線もまた創作として実在するとする。 このようにガブリエルは本当にあるものは当然として、その別の見方も、ある人の想像の中にあるものも、創作の中に登場するものも全て実在するとする。ただ一つ、それら全てをまとめる世界というものだけは存在しないと言う。 例えば人間を語るとき、物質として見ると全体の60%が水で酸素が25%、炭素が10%というような分析が可能である。医学的には体重や体脂肪率、血圧や肝機能で人間の健康状態を測ることができる。一方、文学では登場人物として恋をしたり振られたり、誰かを恨んだり恨まれたりもするだろう。 これらは物質という世界、医学としてみた世界、文学としてみた世界とそれぞれ独立した小さな世界の中での人間であり、同じ人間というものを扱っていても、それらを混ぜることはできない。人間の60%は水でできているから恋は冷めるのだと説明することもできなければ、登場人物の体脂肪率が低いからストイックな文学作品だということもないのだ。 つまり、エビデンスで測れる世界と人間社会がどうあるべきかという思想の世界は別の世界であり、一方の物差しによってもう一方を測り説明することはできない。こういった至極当然であるが、当然であるだけになかなか説明の難しいことを事例を交え丁寧に説明する本書は、一段上のメタな抽象度の高い世界で考えることが時に現実の具体的な問題を説明するということを教えてくれる。 Text by Naohiro Nishikawa *1 30 years on, what’s next #ForTheWeb? *2 本書の第1章でダークウェブの成り立ちを現代の暗号学の基礎から語り始める導入は非常にセクシーであるが、数学的という説明は少し誤解を与えるように思う。なぜなら現在使われる暗号の解読に必要な計算量は数学的には証明されていないからだ。公開鍵暗号で使われるRSA暗号は巨大な合成数の素因数分解の難しさに依存するため、その計算量は数学的に証明はされてはいないものの、その難しさはこれまでの数学の歴史によってある程度は担保されると思ってよいだろう。しかし現在、一方向ハッシュ関数としてもっとも使われているSHA-2を数学的というのはかなり怪しい。実際のところその前身であるSAH-1は脆弱性が見つかっている。そもそも一方向ハッシュ関数のあらゆるデータを衝突のない固定ビットで表すというコンセプト自体に無理があるようにも思う。 *3 「インテレクチュアル・ダークウェブ」に関してはダークウェブ本の著者である木澤佐登志氏の『欧米を揺るがす「インテレクチュアル・ダークウェブ」のヤバい存在感』https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59351に詳しい。本稿の「インテレクチュアル・ダークウェブ」に関する記述はこの記事から引用している。
FEATURE
- 2025/06/18
-

-
iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」がWWWにて開催
1stアルバム『混乱するアパタイト』CD版発売決定 more
- 2025/06/05
-

-
誰でもない私になるための方法|iiso interview
最新EPから「Ash」のアコースティック版がリリース more
- 2025/05/27
-

-
もうひとりの私と出会う|nyamura『Seraphim March』レポート
Text : つやちゃん more