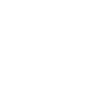ジャパニーズ・クラブの10年|「CIRCUS Tokyo 10th anniversary」Official Report
2025/11/18
全22組からハイライトをピックアップ

「クラブ・カルチャーの主体はいったいどこにあるのか?」と訊かれたら、それはもちろんフロアで揺れ動く観客やパーティーそれ自体を取り巻く空気そのものであって、決してアーティストが100%主導権を握っているわけではない。それこそがクラブを軸とした音楽文化の特異な点だろうと思う。
そうした普遍的な価値観を継承しつつ、斬新な切り口から日本のシーンに新風をもたらしてきたクラブが、大阪・アメリカ村にて2012年にオープンしたCIRCUSだ。設立以来日本だけでなく世界各地のアンダーグラウンド・シーンの潮流をいち早くキャッチし、アップカミングな新星からクラブカルチャーの伝説までを幅広く招聘し、いくつもの夜を彩ってきた。
そんなCIRCUSの姉妹店として2015年に渋谷にてオープンしたCIRCUS TOKYOが設立10周年を記念し、独立系のクラブとしては類を見ない規模の都市型音楽フェス「CIRCUS -CIRCUS Tokyo 10th anniversary-」を10月4日に開催。会場はお台場の野外イベントスペース。東京のなかでも殊更に人工的な質感を帯びた街で、一昔前のゲームのグラフィックのような無機質さが漂う区画。
今回AVYSSでは11時間にわたる当日の模様をオープンからクローズまで密着取材。3フロア・全22組におよぶラインナップから一部をピックアップしてレポーティングしていく。
Text : NordOst / Telematic Visions
Edit : NordOst
Photo : 添田ゆかり
okadada


曇り空を気にしつつ、街というにはいささか無機質すぎる土地を歩き会場に向かっていると、遠くからうねりのような重低音が響いてくる。CIRCUS TOKYOでも名物パーティー〈AUDIO TWO〉を開催しているokadadaによる、セカンドフロアでの2時間セットでオープンを迎えた。
サウンドシステム・カルチャー誕生の契機となったダブを中心としたセレクトで場の整地を試み、じっくりと後に続く流れを組み立てていく。そこから徐々にダブテクノ~ディープハウスといったサウンドへと展開。時折降りはじめた小雨とも噛み合うような雰囲気を感じさせる名人芸だった。
とにかく音響が素晴らしく、さすがにクラブが主導する野外フェスなだけはある。ほかの大規模フェスと比べても、全フロアの出音が常に一定以上の品質に保たれていた点にも、CIRCUS TOKYOの10年の矜持を感じた。なにより、CIRCUS名物のイギリス・VOID acoustics社のサウンドシステムは野外と合う。
ちなみに後で話をうかがったところ、okadada氏は前日に出演していた代官山ORD.のパーティー(Skaai × KM “Podium” RELEASE PARTY)から直行してそのまま2時間セットへなだれ込んだとのこと。鉄人の背中は今日も頼もしかった。
PAS TASTA


okadadaによるセットアップが折り返しを迎えた11時、メインフロアがPAS TASTAからオープン。入場してすぐ広々としたセカンドフロアとCIRCUS名物の「VOID」を主としたサウンドシステムのクオリティに驚かされたが、メインフロアはそれをさらに上回るスケール感。この後に続く豪華極まりない面々を迎えるための万全の体制が築かれていた。
今回のPAS TASTAはDJセットを軸にしつつ自曲のライブも披露するハイブリッド構成。hirihiri、Kabanagu、phritz、quoree、ウ山あまね、yuigotそれぞれの個性が色濃く出力された選曲のデジタル・コラージュ感に、このグループが「プロデューサー・ユニット」であることを改めて感じ取った。

メンバー各々のスタンスを表明するかのようなDJパートからライブに移行し、ウ山あまねがマイクを握る。それにしても、この日のPAS TASTAの勢いと観客の期待感は凄まじかった。1st、2ndの収録曲からアンセムが次々と披露され、フロアの熱は高まり続けていく。生憎の空模様を跳ね除けるように盛り上がる様子は、まさしく野外フェスのそれだろう。
lilbesh ramko


「CIRCUS -CIRCUS Tokyo 10th anniversary-」の翌日には同会場で渋谷・clubasia発のフェス〈暴力的にカワイイ 2025〉が開催された。kawaii future bassに端を発するムーブメントを象徴する「暴カワ」と、クラブ・カルチャーに根ざした本回を結びつける唯一のアーティストこそがlilbesh ramkoであり、彼の表現がいかに現場を越境してきたかを物語る動き方だといえる。
CIRCUS TOKYOはクラブ・ミュージックの窓口だけでなく、コロナ禍以降デイタイムでデジコアにはじまる新しいライブアクトの躍進を牽引してきた側面もあり、その代表的存在としてもlilbesh ramkoという存在が自然と連想されるはずだ。

全国各地のさまざまなロケーションで活躍する彼の今回のセットは、今年リリースされたミニアルバム『生活*1』を基調とした内容。野外フェスという環境、クラブ寄りのシチュエーションにも合致していた。1曲目の「Porsche/暮れ」からほどなくして、曇り空を飛行機が横切り、雨が降りはじめる。エンジン音とベース、ハイハットがクロスして轟音となり、悪天候を跳ね除けるようなエネルギーを発していた。ハイエナジーなだけでなく、肩の力を抜いてリラックスしていこうと観客に提案するようなアプローチも光る。いつ何度観ても素晴らしいし、あれだけの活動ペースでありながら引き出しが尽きることはない印象。アーティスティックでありつつも、サービス精神にあふれている。
HEAVEN


lilbesh ramkoに続くライブはlil soft tennis、RY0N4、aryyらによる関西発のコレクティヴ・HEAVEN。バックDJにはasterisk*が参加していた。彼らもメンバーそれぞれがコロナ禍に発生した新たなムーブメントから躍進を遂げた出自を持ち、CIRCUS OSAKA主導のヒップホップ・フェス〈CIRCUS×CIRCUS〉などへの出演経験も豊富だ。
デイ/ナイトを行き来しながら数々のステージを賑わせてきたHEAVENは観客と固い信頼関係を築き上げていて、流動性の高いフェスという環境ながらにフロアから人を離さない。セットのなかではメンバー各々のソロ曲も披露され、三者三様の魅力を存分に発揮するショーケースとなった。

なにより、HEAVENのアンセム「mörita」「AQUA (feat. RY0N4, JUMADIBA, LINNA FIGG, aryy & Lil Soft Tennis)」はいつどこで何回聴いても名曲であることは間違いないが、それをこのロケーションで観るのは格別だった。HEAVENとしてのこれからの活動やリリースにも期待したい。ゆっくり待っているファンは、数え切れないほどいるはず。
Peterparker69


フロアをそろそろ回遊したいところではあったものの、PAS TASTAから続くメインフロアの一連の流れからは目が離せなかったというのが正直なところ。前述の通り、おそらく前半パートでは20年代以降CIRCUSが下支えしてきたシーンの変革期を象徴する国内アーティストたちが集う形となり、その流れを締めくくったのがJeterとY ohtrixpointneverによるデュオ・Peterparker69だった。

今年アルバム『yo,』を発表して以降、海外での公演機会もさらに増えライブにもますます磨きをかけた印象で、新鋭ながらある種の貫禄すら身につけはじめている。大規模な野外ステージをも軽やかに掌握して見せ、かといってスター性に偏らずMCを交え観客と交歓を重ねていく。この日Jeterは本調子ではなかったようだが、そうしたマイナス要素を一切感じさせず、遊び心とともにフロアを一段階上の熱狂へと導いていった。
Vegyn


不動のグルーヴでokadadaのセットアップを引き継ぎ、セカンドステージを完全にダンスフロア化してみせたSAMO(彼女もまたCIRCUSを牽引してきたローカル・ヒーローのひとりだ)から、VegynのDJセットがスタート。転換時にはこちらにピースサインを向ける茶目っ気も見せてくれて、この日をとても楽しんでいることが伺えた。

しかしプレイが進むとその顔つきはクールに。アップリフティングな雰囲気のハウスを軸に、四つ打ちのリズムを徐々に横展開してグラデーションのように展開をつけてフロアを彩っていく。自身のグッズTシャツにプリントされた「PLEASE」の文字も意味深だ。
最後にはフランスのバンド・Phoenixのアンセム「If I Ever Feel Better」をプレイして、SAMOと同じくCIRCUSと二人三脚で歩んできたryotaへとバトンタッチしていった。展開や思考の読めなさが終始観る者を飽きさせず、世界でも指折りの支持を誇るDJながらクラブ的な遊び心も十分で素晴らしかった。上品にチョケられる人は凄い。
Qrion


通り雨を乗り越えて、メインフロアにスペシャルゲスト・Qrionが登場。札幌を拠点に10代のころからキャリアを始動、DJ/電子音楽家としての才能が世界に発見されてからはSkrillexの〈Nest HQ〉やA-Trakの〈Fool’s Gold〉といった海外レーベルからのリリースを重ね、〈Anjunadeep〉との契約以降はアメリカを拠点に活動を続けるトップDJのひとりだ。
QrionとCIRCUSの関係は長いようで、首都圏進出の早期から彼女のキャリアをバックアップしてきた。いわば10周年を飾る凱旋公演ともいえる今回のギグに並々ならぬ情熱を注いできたことは間違いなく、しかしトップランナーの余裕と貫禄を感じさせる堂々たるプレイでフロアを魅了していった。
世界のビッグルームを巡る存在へと駆け上がりながらも、日本のローカルシーンに出自を持つ氏のプレイは、大局から細部までを見通すレンジの広さを感じさせるものだった。力強く、それでいてしなやかにトラックを紡いでいく彼女は、常にステージからじっくりとフロアを見つめていた。

後続のDJ Seinfeldとお互いを称え合い、ステージを去っていく。どんな現場であったとしても、前後のアーティストとのこうした交流を目にするたびに胸が熱くなる。余談ではあるけれど、なんと今回の来日タイミングは誕生日と重なっていたらしく、出番を終えた彼女が家族や友人と仲睦まじく過ごしている様子も遠目に見えた。無機質な空間で築かれたフェスだからこそ、アーティストの人間的な温かみがビビッドに映るのかもしれない。
DJ Q


結局のところ、音楽フェス的な催しに何が求められるかというと「楽しさ」に尽きるはず。圧倒的な表現を巨大なスケール感で浴び、受け止めるという体験ももちろん素晴らしいけれど、やはり解放感のある環境では楽しげに過ごし、熱狂したい。
そんなニーズをこれでもかと掴んで畳み掛けるようなDJ Qのプレイングはまさに圧倒的だった。UKダンス・ミュージックのテクニカルな部分をトップレベルの技量でこれでもかと放出する景気の良さに、立ち寄った人々は釘付け。筆者もそのひとりで、ほかにも行きたいフロアがあるのに離れられず、気づけば小一時間が過ぎていた。

フェスで日中に踊ってクタクタになるのはいいもので、気づけば雨もやみ着ていたマウンテンパーカーも邪魔になるほど。無限に感じられるほどの手数の多さに反して音圧・音量の管理は完璧と断言でき、テクニカルなアプローチを下支えしている不動のグルーヴには開いた口が塞がらなかった。いつかRoyal-T、Flava Dとのスペシャルユニット・TQDのギグも味わってみたい。それまでにもう少し体力をつけておこう……。
FUMIYA TANAKA (*Written by Telematic Visions)


田中フミヤさんへのイメージは、主にアルバム『Unknown Possibility 1』(1997)や〈Tresor〉〈Torema Records〉期、そこからのミニマル路線など。最近はMIX「RA.964 Fumiya Tanaka」で披露されたような、ガラージハウスみたいなものをかけていることも知っていた。
けれど、ステージに来てみるとBPM140以下ぐらいのブレイクビーツがかかっていて意表を突かれた。そこからレゲエ・サンプリングの大バンガー、Mark V. & Poogie Bear「Da Boy Is Bangin」(1991)がプレイされて驚いた。最近のUKダンス・ミュージックに初期のブレイクビーツを混ぜてる感じだろうか。うっすらUK Funkyぽいけどキックの重心が絶妙な四つ打ちなどもミックスされていた。それでもハットのドラムマシン感やスネアのサンプルが、ちょっと昔っぽくてかっこいい。野外だからか、サウンドシステムが良いのか、クラシックスと最近の曲を混ぜているのにかなり今っぽい音像で聴けた。
ガラージ主体だけど、DJ QやSeinfieldよりもハウス的な粘り気のある選曲で、少し異質に聴こえるものが多かった気がする。しかしハウス・マナーで各パートのズレからグルーヴを作るというより、丁寧なビートマッチとグルーヴ管理によって塩梅を調整していた。音を止めて一拍目だけ出すカットの精度も高く、これがトッププロか……と改めて思わされた。こうしたテクニックをまあまあの頻度で織り交ぜていて、スリリングだった。途中からはアシッドハウスやハードテクノをかけたりもしていて、音像は若干RAWではあるけど聴きづらさは無い。すごかった……。
Iglooghost


日が暮れてからの後半戦には、イギリスの電子音楽プロデューサー・Iglooghostが登場。IDMをキャッチーかつキッチュな切り口で解釈してきた才人はレーベルを〈Brainfeeder〉から〈LUCKYME〉に移して以降、より実験的でダーク、それでいてグルーヴィーな作風へと徐々にスライドしていった(昨年発表されたアルバム『Tidal Memory Exo』以降のリリース作を、ぜひ一聴いただければ)。
この日披露されたセットは2025年9月にリリースされたばかりのEP「Bronze Claw Iso」をフィーチャーした内容。Iglooghost本人がPCでマニピュレーションを実行しつつ自身も歌い上げるスタイルに。Post-Club的な質感とトラップ以降のSwag感を他に無い配分でブレンドしたかのような雰囲気で、緊迫感とカタルシスが、荒々しさと美しさとが同居する素晴らしい内容だった。


Iglooghostの表現の核をなすSF的感性とUKならではの陰のあるレイヴ感覚が溶け合い、IDMを軸にSwagしていく……という今のスタイルはある種の発明のように映る。〈Hyperdub〉のProc Fiskalがそうであるように、グライム~ドリル経由でヒップホップを飲み込んだ現行の実験的なUKベースは、もしかすると今世界で一番スリリングな電子音楽なのかもしれない。ただただ「また観たい」と思わせる圧巻のライブだった。この路線でのフルアルバムにも期待したい。
underscores


とにかく圧巻だった、というほかない。今回が2度目の来日となるSoundCloud発のニュースター・underscoresのライブは、間違いなくこの日のハイライトだったといえる。
本回のヘッドライナーであるunderscores(Milkfish名義でも知られる)について簡単に整理をすると、もともと10代のころからEDMに感化された諸作をリリース、ハイパーポップ・ムーブメントの勃興とともに2021年に名盤『Fishmonger』を、2023年にコンセプト・アルバム『Wallsocket』を発表。100 gecsの登場以降、トラップとEDMを飲み込んだハイブリッドなポップスの雛形を形成したシーンの立役者といえるアーティストだ。
Iglooghostと同様、今回のunderscoresのセットは現在制作中の新作を軸とした内容だったように思える。おそらくアルバムの先行シングルとして公開中の「Music」ほか、新旧さまざまなトラックを織り交ぜて歌い上げる。とにかく発声、立ち振舞といったパフォーマンス面のクオリティだけを切り取っても頭抜けており、このフェス全体はもちろん筆者が今年観たすべてのライブのなかでも3本の指に入る内容だった。

セットの途中には同じく来日中だった盟友・gabby start (fka knapsack)も客演として登場。SoundCloudとDiscordが下支えした2020年代初頭のことが走馬灯のようにフラッシュバックしていった。
キャパシティや規模感にかかわらず、120%のエネルギーを注いで楽しみながらギグに向き合う姿勢も素晴らしい。underscoresほどの規模感のアーティストが偶然にもCIRCUS TOKYOで初来日を迎えたことが今回のライブに繋がっていると考えると、やはり日々のクラブの営みこそかけがえのないものだと思える。彼女は昨年の来日時、そして今回の大阪公演でも共演したlilbesh ramkoから教わったという日本語「飛び跳ねろ!!」を要所要所でスピットしていて、バイブスは海を超えて共鳴するということを改めて感じさせてくれた。

ライブが進むにつれ、underscoresはLEDライトの柱を刀のように抱えたり、ステージに横たわったり、キャリーケースを手に取ったりと多彩な演出を繰り広げていく。11月現在客演で参加したDanny Brownの新作『Stardust』に伴うツアーに帯同している彼女は、いまも長旅を続けているということだろうか。まだ全容が明かされていない次作のヒントなのか、果たして?
こうした謎も含め、釘付けにさせられてしまった。締めくくりはもちろん新世代のクラシック「Spoiled little brat」。最高だった。


以上はあくまでも「CIRCUS -CIRCUS Tokyo 10th anniversary-」のハイライトの一部でしかない。言うまでもなく、ここでレポートした以外のアクトも掛け値なしに素晴らしかった。
たとえばサードフロアを盛り上げていたBeginningは最新形のエネルギッシュなドラムン・ベースやダブステップを、RIPはUKガラージにはじまるベース・ミュージックを、ENSITEはヒプノティックなミニマル・テクノを、そしてFULLHOUSEはジャングル、ダブ、ハウス、あらゆるダンス・ミュージックを終日披露していた。いずれもCIRCUSを拠点に数々のパーティーを開き、多種多様なゲストをローカルと接続してきた立役者であり、その功績が先に挙げた数々のスペシャルゲストとの交歓につながっている。
どのようなパーティーも必ず終わりを迎えるけれど、それは次のパーティーへ備えるためのこと。終わらないパーティーは無いけれど、クラブ・カルチャーは終わらない。人と音楽は(いつかCIRCUSでvqがそうしていたように)か細い糸で繋がっている。点と点に線を引き、結び続けてきたCIRCUSの挑戦をこれからも応援したい。








CIRCUS -CIRCUS Tokyo 10th anniversary-
DATE:2025 / 10 / 4 (SAT)
OPEN:10:00 / CLOSE:21:00
VENUE:お台場青海地区P区画
LINE UP:(A-Z)
FUMIYA TANAKA
HEAVEN
Iglooghost
lilbesh ramko
okadada
PAS TASTA
Peterparker69
DJ Q
Qrion
ralph
ryota
SAMO
DJ SEINFELD
SKIN ON SKIN
SOICHI TERADA
Tohji
underscores
Vegyn
Beginning
ENSITE
FULLHOUSE
RIP
category:REPORT
tags:CIRCUS Tokyo
RELATED
-
2025/08/04
CIRCUS Tokyo 10周年アニバーサリーイベントのフルラインナップが公開
10/4 お台場青海地区P区画 お台場野外特設会場で開催するCIRCUS Tokyoの10周年を記念するアニバーサリーイベントのフルラインナップが公開。 第一弾ラインナップで発表したTohji, SKIN ON SKIN, underscoresに加え、国内外のダンスミュージックシーンを賑やかす、強力なアーティスト陣が集結する。 – TITLE:CIRCUS -CIRCUS Tokyo 10th anniversary- DATE:2025 / 10 / 4 (SAT) OPEN/START:10:00 CLOSE:21:00 LINE UP:(A-Z) FUMIYA TANAKA HEAVEN Iglooghost lilbesh ramko okadada PAS TASTA -DJ SET- Peterparker69 DJ Q Qrion ralph ryota SAMO DJ SEINFELD SKIN ON SKIN SOICHI TERADA Tohji underscores Vegyn Beginning ENSITE FULLHOUSE RIP VENUE:お台場青海地区P区画 〒135-0064 東京都江東区青海1-1-16 最寄駅: ゆりかもめ / 台場駅 ゆりかもめ / 東京国際クルーズターミナル駅 りんかい線/東京テレポート駅 前売り券:¥9,000 ※入場時、別途1ドリンク代(¥800)を頂戴いたします。 チケットプレイガイド: ぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2528328 ※雨天決行・荒天中止 【チケットに関する注意事項】 ・本券は1名様のみ有効です。 ・再入場の可否は後日公式SNS・HPにてご案内いたします。 ・出演者の変更・キャンセルによる払い戻しは行いません。 ・会場内の映像・写真が公開・使用される場合があります。あらかじめご了承ください。 ・チケットの再発行はできません。紛失・破損にご注意ください。 ・チケットの転売・譲渡は禁止です。発覚した場合は入場をお断りいたします。 【開催に関する注意事項】 ・屋外開催のため、雨具・防寒具・熱中症対策を各自ご用意ください。 ・ゴミは必ず指定の分別回収場所へ。持ち帰りのご協力をお願いします。 ・会場内外で発生した事故・盗難・怪我等に関して主催者は責任を負いかねます。 ・ペット同伴での入場はできません(介助犬・盲導犬は除く)。 ・喫煙は所定のエリアにてお願いいたします。 【未成年者のご来場について】 ・小学生以下の入場はできません。 ・中学生は保護者同伴に限り入場可能です。 ・中学生以上はチケットが必要です。 ・飲酒・喫煙は法律で禁止されています。違反行為が確認された場合は即時退場いただきます。
-
2024/11/28
ジャパニーズ・ヒップホップの正統性|温故知新 Vol.4がLIBROを迎え開催
日本語ラップオンリーパーティー 「温故知新」は阿佐ヶ谷DRIFTにて2022年より不定期開催されている、100%ジャパニーズ・ヒップホップオンリーのデイパーティー。 各回ともにリアルかつ切実なラップ愛を持つヘッズがビギナーからレジェンドまで分け隔てなくラインナップされており、これまでサイプレス上野、MACKA-CHIN、ZEN-LA-ROCK、DJ Slowcurv a.k.a.仙人掌、G.O (ICE DYNASTY)、MEGA-G、okadadaといったアーティストが参加している。 Vol.4となる今回のスペシャルゲストには、ライブアクトに日本語ラップの金字塔的作品『胎動』をはじめとする諸作や90年代末期より各所でリアルな活躍を続けるレジェンド・LIBRO、飾らないクラシック・サウンドを標榜する5MCクルー・Flat Line Classicsを招聘。 DJにはヒップホップ・レーベル〈Summit〉主催・DJ Not For Saleと日本語ラップシーンと黎明期から併走し続けるOG・原島”ど真ん中”宙芳がラインナップされている。 また、ゲストDJにはBatsu、HIGH-TONE、mizuo、MPEG-7、WACKOZAKIと、コンシャスなヒップホップからネットラップ・シーンまでに幅広く点在する日本語ラップ・ヘッズを各所から招いた。VJとして参加するMockin、レジデントDJを務めるJ.A.N.E、szkPP、ricebowlも、エッジーなセンスで局所的に厚い信頼を集めている説明不要のリアルヘッズ。100%の純度で長年ヒップホップと日本語ラップに情熱を注いできたアクトが集う一日となる。 新たな文化の発信地としてコミュニティ的支持も集める阿佐ヶ谷DRIFTにて、あえて古くを訪ねることで生まれる発見もあるだろう。そんな思いを込めての開催となる。 – 12/21(土) 温故知新VOL.4 at阿佐ヶ谷DRIFT OPEN16:00 CLOSE23:00 DOOR:¥3,000+1D ADV:¥2,500+1D 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXtLgu6gf5BZNK0-RAguZdg_rg6eLVOzPy8w85GvUnG1Z5A/viewform 【SP GUEST LIVE】 LIBRO Flat Line Classics 【SP GUEST DJ】 DJ Not For Sale 原島”ど真ん中”宙芳 【guest DJ】 Batsu HIGH-TONE mizuo MPEG-7 WACKOZAKI 【resident DJ】 J.A.N.E szkPP ricebowl 【VJ】 Mockin
-
2023/04/21
00sジャパニーズ・エレクトロニカの傑作、aus『Lang』が初のLP化
現行20sエレクトロニカと静かに合流 「 “ラング” はエレクトロニカがどれほど有意義でエキサイティングな音を表現することが出来るかを示した素晴らしい見本と言えるでしょう。ausは細かなディテールと、哀愁と楽観的な感情を同時に呼び起こす素晴らしいメロディーで感覚的に構築したアレンジを組み合わせている。」 – ウルリッヒ・シュナウス 2006年にリリースされた今作でエレクトロニカの世界に魅了され、同時期に盛り上がったポストロックやその後のポストクラシカルの世界にどっぷりと浸かった人も少なくない。メロディアスで耳に優しく残るグリッチサウンドと柔らかなドラムンベースのリズム、そこにフリージャズやアブストラクト・ヒップホップを彷彿とさせるドラムのサンプリング。水面にキラキラと輝く陽の光を想起させる透明感のあるエレクトロニカサウンドは当時大ヒットし、ausの名をこのシーンを牽引する存在へと引き上げた。今回リマスタリングはRothkoとしての活動でも知られるMark BeazleyがLP用に仕上げている。当時のCD盤と同じくアートワークをAkihiro Moritaが手がけ、写真はRyo Mitamuraによるもの。 一新したデザインで登場。現行20sエレクトロニカと静かに合流する。 aus – Lang 2023年5月26日リリース フォーマット : 国内盤LP 価格 : 4,730円(税込)/4.300円(税抜) レーベル : p*dis ■初回完全生産限定盤 ■リマスタリング http://www.inpartmaint.com/site/37382/ A-Side 01.Clocks 02.Halo 03.New Look 04.Beyond The Curve B-side 01.Double Talk 02.Opaque 03.Aslope 04.Headphone Girl 05.Moraine
FEATURE
- 2026/03/03
-

-
「森、道、市場2026」にてAVYSS企画「AVYSS Body」が開催
5月23日 MORI.MICHI.DISCO.STAGE (遊園地エリア)
more
- 2026/02/16
-

-
交差する円、重なる身体|AVYSS Circle 2026 photo report
アビサー2026の記録写真 more
- 2026/02/02
-

-
渋谷から新木場廃倉庫レイヴへ|「AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding)」開催
2/13(金) 渋谷から新木場へ座標を再設定
more