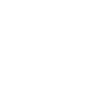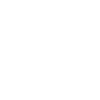ART-SCHOOL「絶望の反復と停滞の強度」─ 死と孤独をシミュレーションする25年
2025/10/01
ART-SCHOOLの美学をライブ現場から読み解く

祝祭の夜に響いていたのは、希望ではなく「同じ絶望」の再演。その反復がなぜ強度へと転化したのか──25年を貫くART-SCHOOLの美学を、スタイリストのTatsuki Itakuraがライブ現場から読み解いたレポート+論考です。
Text : Tatsuki Itakura
Visual : JACKSON kaki
ART-SCHOOL 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 「1985」のライブへ
2025年9月21日、梅田クラブクアトロ。ART-SCHOOLの25周年ライブには、ユース層のオーディエンスから結成当時を知る世代まで幅広い人々が集まっていました。開演5分前の会場を包んでいたのは、熱狂ではなく静かな緊張でした。
Aphex Twinの「Girl/Boy Song」が開演の合図。ミニアルバム『1985』の1曲目と同じ「Trust Me」で幕が開きます。戸高賢史氏のギターがノイズを操り、クラブクアトロの音響を揺らす。木下理樹氏のボーカルは少し後ろに聞こえ、それが厚みと奥行きを増幅させているように感じました。
「スカーレット」「MISS WORLD」では、音に耳を澄ます姿が目立ちました。サポートを務める藤田勇氏のドラミング、中尾憲太郎氏のベースの力強いサウンドと同期するように拳を突き上げる人々。その姿を横目に、僕自身は戸高さんのギター音に集中していました。轟音の塊でありながら、ノイズ的に揺らぎ続け、エモーショナルさを感じる音像。しばし目を閉じ、サウンドスケープへと没入していきました。
「クロエ」では場内が沈黙に近い集中に包まれ、かすれながらも鮮明に木下さんの声が響きます。「1985」や「Just kids」と続き、病からの復帰後に作られた楽曲がかつての名曲たちと並置されることで、過去と現在が同時に呼び出されるようでした。
終盤、「FADE TO BLACK」や「BOY MEETS GIRL」といったアグレッシブな初期曲が披露されると、視界に入る人たちのほとんどが木下さんの歌声に声を重ねシンガロングしていました。しかし、祝祭の熱気の中で響いていたのは「死」「孤独」「消えたい」という変わらぬ言葉。この矛盾を前に、僕は「美学の持続」という言葉を思い浮かべました。
多くのアーティストは年齢や立場に応じて言葉を変えていきますが、木下さんはそうはせず、25年を経ても同じテーマを歌い続けている。本稿ではその特異性を掘り下げていきます。
1. 変わらない言葉が、音を更新し続けた
ART-SCHOOLのサウンドは、時代ごとに変化してきました。初期はグランジのざらつき、中期は叙情性や繊細さを重視していて、近年はシューゲイズ的に受け取れる音像へとシフトしています。それは木下さんと戸高さんという核がありつつも、レコーディングやライブを支えるサポートメンバーの演奏、そしてプロダクションの更新によってもたらされた変化といえるでしょう。
たとえば中尾憲太郎さんのベースの強度や藤田勇さんのダイナミックなドラミングは、現行のART-SCHOOLにはっきりとした輪郭を与えています。MCでも触れられていましたが、ライブでは木下さんが歌に集中するためにギター演奏でカバーできない部分などを、Cryffのyagihiromiさんが要所を支えています。歌に主軸を置く今の編成を、ライブ現場で機能させる設計ということです。
しかし、その変化を越えて揺らがなかったのが詩作のスタイルでした。たとえば「死にたい」「消えたい」「孤独」「少年」「夜」。こうしたモチーフは、25年前からリリックに繰り返し現れ続けています。音像が変化しても、言葉が不変であるがゆえにART-SCHOOLは同じ美学を持続できていると考えられます。
ここで浮かび上がるのは「シミュレーション」という視点です。25年間歌われ続けた「死」や「孤独」は、もはや木下さんの個人的感情を表すものではなく、反復により「ART-SCHOOL的な死」という記号に置き換わっています。観客が耳にするのは、現実の死ではなく「シミュレーションされた死」です。
実際に生じた感情を一度きりで消費するのではなく、記号化されたテーマに昇華した上で新しい音像に乗せて繰り返す。ART-SCHOOLが25年にわたって同じ美学を貫けた要因には、こうした姿勢が深く関わっているのではないでしょうか?
2. 内面に刻まれた絶望のループ
ART-SCHOOLの歌詞は、社会批判や外部の出来事に向かうことがほとんどなく、描かれてきたのは一貫して「自分の中の孤独」や「消えたい」という衝動でした。対象は常に内面です。たとえば「死にたい」という言葉は、初めて歌われたときは木下さん自身の感情を表したかもしれません。しかし繰り返されるうちに、それは「ART-SCHOOLの象徴」として定着しました。
観客が体験しているのは個人的な告白ではなく、反復によって「絶望が記号化されたもの」です。つまり、観客は「絶望のシミュレーション」を共有することでART-SCHOOLのライブを通して一体感を得ているとも言い換えられるでしょう。
ここで言う「シミュレーション」とは、単なる模倣やコピーではありません。かつて哲学者・思想家のジャン・ボードリヤールは、コピーが繰り返されることで元の現実よりも「コピーのほうがリアルに感じられる」状態について論じました。
ART-SCHOOLの「死にたい」という言葉も同様です。木下さんの内面から生まれた表現が25年にわたる反復のなかで個人的感情から切り離され、「ART-SCHOOL的な死のモチーフ」として独立しました。観客がライブで受け取るのは、現実の告白ではなく、この虚構化された「死」の像です。
3. 虚構の死が鳴り響く音
「虚構化された絶望」は、サウンドの質感にも刻み込まれています。ART-SCHOOLのギターサウンドは、厚みを持ちながらもRideやMy Bloody Valentineのような没入感を生む轟音ではありません。むしろざらつきや切断感を保つことで、聴き手を現実に引き戻す力を持っています。
シューゲイズが「音に身を委ね、意識が拡張していく快楽」を提供するのに対し、ART-SCHOOLの音は、聴き手を醒めたまま目眩に誘います。轟音に包まれながらも、歌詞の言葉が鋭く突き刺さることで、没入と覚醒が同時に訪れる。その矛盾した体験こそが、絶望を「音響的に反復」するART-SCHOOL独自のスタイルなのではないでしょうか?
4. 祝福と絶望の同居
MCのなかで、木下さんは幼少期に他人と違いすぎる自分を意識し、本当に生きていていいのだろうか? と感じていたことについて語りました。その悩みを打ち砕いたのはART-SCHOOLというバンドを続けることだった、とも。その言葉にフロアからは拍手が送られました。
しかし曲が始まれば、響いてくるのはやはり「死にたい」「消えたい」「孤独」といったモチーフ。喜びを口にした直後に、絶望を歌い続ける。この矛盾こそがART-SCHOOLの本質でしょう。
ボードリヤール的に捉えれば、観客が目の前で見ているのは「現実の木下理樹」ですが、耳にするのは「死を歌う虚構の木下理樹」です。ART-SCHOOLのライブは、双方が同時に存在し、重なり合う場とも捉えられます。
重要なのは、観客がその矛盾を違和感ではなく「らしさ」として受け止めていることです。「死を歌う木下さん」は現実ではなく、ART-SCHOOLから生まれた虚像であること。だからこそ、「現実的な祝福」と「虚構としての絶望」が矛盾なく共存し、独特なコントラストを演出しています。
この共存は、観客側の心情が投影されることで支えられているとも考えられます。ファンによるART-SCHOOLへの想いなどをSNS上で読み込んでいくと、それぞれ個々人が目指す「何か」を志しながらも、今は別の場所で生きている人々、あるいは「叶わなかった夢」や「言葉にできない思い」を抱えている人々がこの会場にはいる、ということが伝わりました。そうした思いが木下さんの言葉に託され、会場全体に共鳴として立ち上がる。そのとき、矛盾は矛盾のまま肯定されるのです。
実際、木下さん自身もインタビューで「今のART-SCHOOLでただただ悲しいだけの曲を作るのは違う」と語っています。絶望を繰り返しながらも、そこに喜びや切なさ、ノスタルジーを混ぜ込む。その矛盾こそが一貫性であり、人間そのものへの愛着なのだと。ライブでの「喜び」と「絶望」の同居は、まさにその思想の具現化でした。
5. 再演される絶望を欲望する
なぜ観客はその木下さんが描き続ける「絶望のシミュレーション」に惹かれ続けるのでしょうか。
現実の絶望は耐えがたい。しかしART-SCHOOLの絶望は、記号化され、反復されることによって「虚構としての絶望」へと変質しています。観客は木下さんの個人的告白に触れているのではなく、「ART-SCHOOL的死」というイメージを受け取っている。だからこそ、それは現実の痛みを背負うことなく共有できます。
映画や小説の悲劇に涙するのと同様に、この虚構化された絶望は「繰り返し触れられる悲劇」として作用します。観客にとってそれはトラウマの再現ではなく、むしろ「再び会える絶望」への期待すら伴う。
死や孤独といった「絶望」を「シミュレーション」として提供し続けることで、聴き手は現実の痛みに溺れることなく、絶望を美学として享受できる。過去を思い出へと塗り替えることも可能になっていく。その虚構性の徹底こそが、ART-SCHOOLが25年にわたり魅力を維持し続けた理由なのではないでしょうか?
6. 美学の持続という逆説
ART-SCHOOLの25周年を振り返って最も鮮烈に突きつけられたのは、『停滞の強度』という逆説的なイメージです。
通常「変わらないこと」は退屈や停滞を意味します。しかしART-SCHOOLは、25年間同じテーマを繰り返し歌い続けることで、退屈や停滞を「表現の強度」へと転化させました。
「死にたい」「消えたい」「孤独」という言葉は、個人的な一瞬の痛みであればすぐに風化するはず。けれど木下さんはあえてそれらを反復し、結果として時代を超えて持続する美学へ昇華させました。ここに“停滞の強度”の正体があります。
木下さんの言葉を借りれば、人間は本来「矛盾を孕んだ存在」です。だからこそ、ART-SCHOOLの音楽に流れる矛盾は不自然ではなく、むしろ人間の本質に忠実です。光だけの人生は存在せず、影があるからこそ生がリアルに感じられる。木下さんはその「陰影の共存」を25年間反復し続けてきました。この構造こそが、ボードリヤールのいう「シミュレーション」と重なります。現実を模倣するのではなく、反復が新しい現実を置き換えてしまう。
7. 25年目に見せた「停滞の強度」
観客は現実の死や孤独に触れるのではなく、ART-SCHOOLが生成してきた「記号としての絶望」を共有します。今を生きる木下さんを祝福するオーディエンスと、死や孤独を歌い続ける虚構の木下さんの対比。その二つが矛盾なく同居する場こそがライブであり、観客はその矛盾を違和感としてではなく、むしろ待ち望む光景として受け止めている。孤独や死への想いに囚われていた人々が、木下さんの作る世界観に共感していく。
ART-SCHOOLは救済を約束しませんが、変わらないテーマを徹底して歌い続けることで、時代を超えて虚構の絶望を持続させました。彼らの歌に内包される、様々な陰。その陰の中に微かに射す光を味わいに、ライブへ向かうオーディエンス。変わらないことが停滞ではなく、シミュレーションとしての更新になる。僕がこのライブから受け取ったのは、その逆説の確かさでした。
–
✍️ イタクラタツキ
instagram:https://www.instagram.com/tatsuki_itakura/
category:REPORT
tags:ART-SCHOOL
RELATED
-
2021/05/12
Walliceが人生シミュレーションゲームに影響を受けた「Off the Rails」のMVを公開
デビューEPより LA拠点のシンガーソングライターWalliceが、6月4日にリリースするデビューEP『Off the Rails』からタイトル曲のMVを公開。昨年デビューし、これまでの3作のシングルに続く今作の映像は人生シュミレーションゲーム『The Sims』シリーズにインスパイアされており、Walliceは不運な主人公を演じている。 「自分の人生をコントロールすることができず、世界が敵に感じること、そして、それを感じているのは自分だけだということを歌っています。人生には、自分の人生が崩壊して、それを解決することができないと思ってしまう時期があります。時には自己憐憫に浸っていてもいいと思いますが、同時にそれをコントロールする力もありますし、ある程度は自分の行動に責任を持つこともできます。時に困難な状況に陥ることもありますが、そこから抜け出すために最善を尽くし、パンチを受け流し、嫌な人間にならないように努力しなければなりません」と、Walliceは語っている。 Wallice – Off the Rails Release date : 11 May 2021 Stream : https://wallice.ffm.to/offtherails
-
2021/04/19
FNMNLがキュレーションするイベントシリーズ『3S』がWWWにて開催
出演はbutaji, Le Makeup, SPARTA 『3S』は異なる個性を持ちつつも、共鳴するアーティストを、FNMNLがキュレーションするイベントシリーズ。 第一回目にはフォーキーなものからエレクトロまでバラエティに富んだスタイルのトラックと強度のあるボーカルで注目を集める“butaji”、昨年リリースした1stアルバム『微熱』で見せたモダンなビートとユニークなリリックの融合や、Ryan Hemsworthのコラボシングル「Moon Hit」も話題の“Le Makeup”、実直なリリックと抜けの良いメロディで知られる“SPARTA”の3人が登場。音楽のスタイルは異なりつつも、「うた」の力を持ったアーティストたちが揃った。 なお、前売りチケットは、本日4月19日(月)19時からe+より発売中。フライヤーデザインはKei Sakawakiが手掛けた。 タイトル:FNMNL Presents 3S 日程:2021年5月23日(日) 会場:WWW 出演:butaji / Le Makeup / SPARTA 時間:OPEN 16:30 / START 17:00 料金:¥3,000(税込 / ドリンク代別 / オールスタンディング) 問合:WWW 03-5458-7685 チケット:4月19日(月)19:00〜 e+ ※本公演は「ライブハウス・ライブホールにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に基づいた対策を講じ、開催いたします。 チケットのご購入、ご来場の際は「新型コロナウイルス感染拡大予防対策の実施について」を必ずご確認いただき、ご同意の上でチケットのご購入とご来場をお願いいたします。 公演詳細:https://www-shibuya.jp/schedule/013505.php
-
2020/06/15
アジアの前衛芸術をキュレーションするUltrastudio Tokyoが創設
予告動画公開 Ultrastudioはイタリアのぺスカーラで創立され、アメリカはロサンゼルスにも支部があるアートディレクションスタジオ。これまでに数々の展覧会のキュレーションを手がけており、アート雑誌や専門家より高い評価を得ている。 そんなUltrastudioが東京支部を新たにスタート。代表をMIRA新伝統 (Raphael Leray、Honami Higuchi)が務め、 アジアの前衛芸術シーンに特化した展覧会・イベント・出版物のキュレーションを行なっていく。また、2020年〜2021年はぺスカーラ・ロサンゼルス・東京の3スタジオの共通テーマを”Body”として各地で展覧会を開催予定だ。 〈English ver〉 Ultrastudio is a curational platform originally founded in Pescara, Italy and established a new office in Los Angeles, USA last year. It has curated numerous exhibitions so far and as been regularly coveraged by leading art magazines. A new branch will now start in Tokyo with MIRA 新伝統 (Raphael Leray, Honami
FEATURE
- 2026/02/16
-

-
交差する円、重なる身体|AVYSS Circle 2026 photo report
アビサー2026の記録写真 more
- 2026/02/02
-

-
渋谷から新木場廃倉庫レイヴへ|「AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding)」開催
2/13(金) 渋谷から新木場へ座標を再設定
more
- 2026/01/25
-

-
渋谷の路地裏に出現する未来都市ALLEY108にて「AVYSS RAVE」開催
2月14日(土) 渋谷センター街の路地をジャック
more