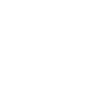無機物への愛をそのままに、有機的な身体性を考える|パソコン音楽クラブ x tomad interview
2024/08/29
内省的空気と身体性ハイブリッド

「DTMの新時代が到来する!」というテーマでパソコン音楽クラブが発足したのは2015年のこと。あれから9年が経ち、コンスタントに作品を送り出すなかでふたりは「インディー的な宅録作家」という枠組みの外側へとひたすら躍進していき、エレクトロニクスとクラブ・ミュージック、そしてポップスをパソコン音楽クラブにしか実現できないバランス感で結びつけ、日本における電子音楽アーティストの新たなロールモデルを切り拓いた。
そんなパソコン音楽クラブは8月7日、5thアルバム『Love Flutter』をリリースした。音響機器の回転ムラに起因する音の歪みを意味する「フラッター」という語句にはときめきやざわつき、といった細かな心の揺れ動きのような意味合いも含まれており、無機質なガジェットから有機的な感情を引き出すというパソコン音楽クラブが一貫して挑戦し続けてきた美学を改めて総括したかのようなタイトルに思える。
本作『Love Flutter』の特徴は、パソコン音楽クラブとしての作家性を継承しつつ、サウンドデザインの面においてより身体性に訴えかけるようなフロアライクな作風へと進化したこと。「今後の方向性を規定するかのような作品を目指した」と自信を持って発表された力作について、今回AVYSSでは最初期からパ音と並走してきたtomad(Maltine Records)氏を迎えクロスインタビューを実施した。ゆっくりと、しかし確実に時の流れは進んでいき、皆少しずつ大人になっていく、そんな心の揺れ動きについて。
取材・構成:NordOst (松島広人)
──おそらく、パソコン音楽クラブは来年で10周年を迎えますよね。これまでを振り返ると、やっぱり変化っていうのは大きかったですか?
西山:もちろん変化っていうのはお互いあると思いますけど、やっぱ僕と柴田くんがあまのじゃくだったから僕らも変わっていった、ていうのも大きいと思います(笑)。でも、ここ最近大きく変わったなと思うのは、昔に比べて身体性のある音楽をやろうって意識しはじめたことで。
──最近はクラブでもよく西山さんにお会いしますし、そのあたりのムードの変化はなんとなく感じてました。
西山:コロナ禍における内省的なリスニング・ミュージックみたいなものは『See-Voice』で結構手応えもあったし、とはいえいわゆるツール・ミュージックを作るのは僕らの仕事じゃないな、とも思うので。今までの感覚を引き継ぎつつ、もっと身体性に訴えかけるダンス・ミュージックを今ならハイブリッドな感じで表現できるかな、って挑戦してみたくなったのが今回の『Love Flutter』ですね。
柴田:シンプルに技術的なレベルも上がったとは思いますし。昔はホンマに何も知らなくて、いい意味でアクセルベタ踏みで危険運転してる音楽だったな……って思ってて。世の中のこと何も知らないし、音楽の作り方も知らないし。(初期作は)あの頃しか作れなかったと思います。
西山:いわゆるDTMとかのtipsとかも初期はそんなに無かったんで、めちゃくちゃな音してますよね、音質も悪いし(笑)。だからこそ面白い作品だなって今は思いますけど。
──初期は意図的にLo-Fiなサウンドデザインに近づけていたのではなく、初期衝動的なものが大きかったって感じなんですかね?
柴田:使ってる機材とかも音悪かったですしね。すごい覚えてるのが、サンレコ(Sound & Recording Magazine)に『DREAM WALK』を出したときインタビューしてもらって、そこで「どうしてこれらの音は歪んでるんですか?」って聞かれたとき、そもそも歪んでるってことが分かってなくて「何のこと言ってるんだろう?」と思ったぐらいでしたから(笑)。やっぱり今聴くと、あの頃は本当に何もわかってなかった可能性はありますね。リバーブのパラメータとかもめちゃくちゃだったと思います。
西山:すごい奇跡が起きてVaporwaveブームみたいなやつとの同時代性も生まれたし。リバーブでピチャピチャだったりLo-Fiな質感だったりっていうものが、自分らの美意識的にはカッコいいもので正解だと思って作ってただけなんですけどね。
──僕は『CONDOMINIUM. ー Atrium Plants EP』が好きで。あれもDJユースというよりはリバーブの効いたベッドルームっぽい余白のある音像で、逆にそれが良さにつながってる感覚もあって。今のパソコン音楽クラブにはフロアもリスニングも大事にする両義性がありますよね。
柴田:パソコン音楽クラブを始めたのが2013年とか14年とかの近辺で、その時期っていわゆる「東京インディー」ブームみたいなのがTwitterとか中心にあって。松島さんは世代的にわかりますよね? For Tracy HydeとかBOYISHとか……。
──大直撃ですね……!
柴田:そのとき、海外ではWashed Outみたいなチルウェイヴ的サウンドが流行ってたりして、リバーブの音像みたいなのをうまく使った面白い音楽が、ロウハウスだったりそれこそVaporwaveだったり、ムーブメント的に広がっていきましたよね。個人的にはそこがメロディじゃなく音像を聴く、ってことの原体験でもあって、そういうタイミングで始めたからこそ1stの『DREAM WALK』とか初期のものが受け入れられたのかなあ……と今は思います。でも、そういう感じの時期になぜか僕らはハード機材の方に行っちゃって。始めた頃はSC-88Proっていう音源モジュールのペラペラさが逆に新鮮で、自然とああいう感じになっていきましたね。
──スタート地点はそういった面白さをまっすぐ追いかけていたような感じだったと思うんですけど、明確に音楽の道へしっかり進んでいこうって決意したタイミングはどの辺りだったんですか?
西山:それはやっぱり1stの『DREAM WALK』ですかね。僕らは運が良くて、まだCDもそれなりに売れる時期だったしそういう意味での反響もしっかり感じられて。正直内容的にはあまりにも初期衝動全開というか、今振り返ってみると音楽的な面白さはもちろんあるんですけど、クオリティ的には本当にザ・インディーみたいな(笑)。それでも、あれを出した後には「こういう音楽ってこんなに聴いてもらえるんや」って感動したし、すごいやる気も出ましたし。今だともっと別のメディアで若い人は背中を押されるような感覚を覚えるのかな、って思うんですけど、自分らの場合は手売りの物販でCDを買ってくれる人が多くて、それはやっぱりピュアな感動でした。ね、柴田くん。
柴田:ありましたねえ、感動。自分らの良いと思ってることって伝わるんや、って。なんていうか、最初は「作って誰か聴いてくれたらいいなあ……」みたいな感じだったんで。音楽捨てたもんじゃないな、みたいな感動はあったんじゃないかなって(笑)。
西山:音楽で暮らしてくってなると、どうしても演奏がめっちゃうまいとか、パフォーマンスみたいなものが秀でてなきゃダメだと思ってたし。
柴田:一応お互いちょろっとピアノ弾けたりとかキーボード弾けたりとか、西山くんもギター弾けたりしますけど、もちろんプロのクオリティではないし、お互い演奏者を志したこともないので。そういう意味ではやってることが肯定されたっていうのはすごく喜ばしかったですね。で、まあそんな感じのきっかけをくださったのがtomadさんだったのかなと(笑)。
──tomadさんはかなり初期の頃から、ある意味かなり近くでふたりの成長をずっと見てきたわけじゃないですか。パソコン音楽クラブがスタートしてそろそろ10年近く経ちますが、そうした歩みをどう感じてますか?
tomad:うーん。でもなんか…ずっとやってて偉いですよね。
西山:それ最近めっちゃ言われますよ、人に(笑)。
tomad:ずっと飽きてないと思う。本当は飽きてるのかもしんないですけど、作品はコンスタントに出てるんで。やっぱりある程度まで出したら「もういいや」って燃え尽きる人もたくさんいますしね。
──「燃え尽き症候群」に陥りやすい時代ですしね。どうしてもいろんな数字がつきまとって、常に精神的なプレッシャーを抱え込んじゃうシステムがあって。
tomad:そうですね。なので、続けてるのがまず凄いというか。それしかやることがないのか……みたいなことは思いますけどね(笑)。
柴田:なんでそんなちくちく言葉を!
──パンデミックがあって、その間自室で音楽を作り始めた若い世代が爆発的に増えて、現場が戻ってきてからはそういう人たちが脚光を浴びてますけど、その下地を作ったのはそれ以前にずっと何かをコンスタントに続けてきた人たちですからね。そういう意味ではパソコン音楽クラブはもう先達みたいな存在になって、ユースに道を示してくれているのかなとも思います。
西山:そういう実感もあまり無いんですけど、そういう感じで思ってもらえてるんだったら嬉しいですね。
柴田:そういえば、tomadさん的に今回のアルバムってどうでした? さっきも言ってましたけど、僕らもそれなりにいろいろと作ってきて、今までと比べてどうなのかな、とか。
tomad:……いや、なんかまとまりあるっすよね、前作よりも。あとUKの感じもあって。けど、別にそこをただ追っかけてるって感じでもないと思うんで、ふんわりとしたUK感みたいなのと前々からあるジャパニーズ・テクノの要素に歌モノの感じが合わさってて、なんか意外と整ってるなというか。前作(『FINE LINE』)の方が模索感が高かったような気もして、もっとオムニバス的な感じだったと思うんですけど。とにかくまとまってますよね。
──日本でいわゆるUKダンスミュージック的なアプローチをしてる人たちって、割と忠実にUK感を出していくことが多いのかなって印象なんですけど、UK的なものに縛られてもいないな、っていう点でもありそうで無かった作品かもなと思いました。今までのパ音には無かったブレイクとかビルドアップ的な展開の作り方も、ポップスの意匠を残しつつダンスミュージック的なフォームに変わっていってるのが新鮮で。西山さんとは最近クラブで会う機会も増えましたが、そういう体験もやっぱり影響しているんでしょうか。
西山:おっしゃる通りかもしれないですね、ここ1年ぐらいまた結構クラブに行くようになったし。いわゆるダンスミュージック的なJ-POPって、歌がめっちゃ先行するものが多いと思うんですよね。そういうポップスとしての構造を今回はできるだけ抜きたいって思ってて。コード感とかメロとか展開とかのアプローチではなく、ビルドアップとドロップっていう発想でブリッジを作ってからフックを聴かせる、っていうことを意識した上でJ-POP的なサビに突入していくような構造を目指して、歌とオケの比率っていうのを考えるというか。言い方はアレですけど、歌のための添え物みたいな感じでビートがあるような感じにならないようにしたいな、っていうのを改めて思ったのが大きいかもしれないです。
──柴田さん的には今回どういう感じで作り込んでいきましたか?
柴田:前回『FINE LINE』を作って、正直まあ燃え尽き症候群といいますか、これから何やろう……みたいな感じになってたんですけど、西山さんが「ダンスミュージック」というお題をくれて。ビートと歌が対等な音楽をやろうっていうので始まっていって身体性みたいなものを意識していったんですけど、そもそも身体性とはなんぞや、ってところから考え直して。ダンサブル=身体的っていう単純な話でもないし、ダンスミュージックにも内省的なものはたくさんあるし、アンビエントにも身体を感じさせるもの、預けたくなるものもあるし。一概に対比できるものでもないから自分たちなりのテーマを見つけられたらな、って思って作りはじめました。今回に関してはビートの反復のなかでなにかをするみたいなテーマが一個あって、その上で有機的な揺らぎを表したい……みたいな。それが自分なりの身体性? なのかもな、と思いまして。これまでパソコンでやってきたのはMIDIのベタ打ちな感じの音楽が多かったので、今回の『Love Flutter』ではシンセサイザーとかのうねりに有機的な感じを前より意図的に持たせたりしましたね。具体的には実際にシンセを手弾きしたり、モジュラーを長尺で録ってそれを編集してみたりとか。
──ライブ感のある作り方、というか。
柴田:身体性って、楽器を実際に演奏するっていうのもありますよね。それは生楽器だけじゃなくて、もちろんシンセサイザーもそうですし。そういう有機性が引き出せたらなあ、とは思ってました。
──具体的に制作中に参考にしたり、リファレンスになったりしたようなアーティストや作品って挙げられますか?
柴田:改めて今Floating Pointsとか聴き返してみたりしてて。あの人のビート感もUKのビートが下地になってて、アブストラクトな響きだけど、実験に収まらずちゃんとポップに聴こえる不思議さはやっぱすごいなあ、って思いました。シンセサイザーのアーティキュレーションのつけかたも管弦楽器のそれに近いようにも感じます。ポップなフィールドにダンサブルな感じをちゃんと落とし込む、というような感じを今回は自分なりに課題として設定して、これまでパソコンでやってきたものと接続できたらいいなと思ってたんですけど、今回それを部分的には叶えられた気がします。あとは、最近だとスピーカーの標準サイズもデカくなってるなと思ってて。
西山:あと、お互いOvermonoの存在にはびっくりさせられたというか。直接的に、ではないですけど一番好きなアーティストではありますし。
柴田:Overmonoの曲ってフロアで聴いてもリスニングで聴いてもカッコよくて。あと、おかしいなって思うのはやたらノイズが多い点で。ビートとして身体にバンってくる音も気持ちいいし、リズムだけじゃなく細かいテクスチャーにも面白さがすごくあって。クラブのデカいスピーカーでも、イヤホンでもいける感じ。僕は昔から(Overmonoの)ふたりのソロ活動とかも追ってて面白いな、って思ってて。でも、リファレンスとして聴いたことはあんまり無いですね。なんというか、今までの感覚だと「The ピーズは好きやけど、自分の活動とは遠いよな……」みたいな感じで。ただ『FINE LINE』を作り終えたぐらいからは改めてこういう音像を作ることに興味あるかも、って急にバシッて意識が向きはじめて。
西山:僕は元々このアルバムを作ろうって思ったときの最初のコンセプトが「内省的な空気感と身体性のハイブリッド」みたいな感じで。そう最初に思ったのがFred Again..の『ten』とか『adore u』あたりの曲でした。元々ロウハウス的な音楽が好きで、でもあれはフェス的なサイズの場所では通用しなくてみんなやめたじゃないですか。Fred Again..はロウハウスは意識してないと思いますけど、リバーブがルームな感じで宅録っぽさがありつつも、ビートはモダンで。そういうバランス感の曲を聞いたのが、自分らもこういうのやってみたいなって思ったきっかけにはなりました。パソコン音楽クラブなりにああいう音楽を解釈していくと、こうした折衷的なダンスミュージックになっていくのかな。
──受けた影響をそのまま表現するのではなくて、一度自分たちの蓄積をフィルターとして通して変換してるような感覚ですね。だからこそ「UKに挑戦」みたいな感じでは語れないというか。
西山:自分らには自分らの表現したいことがあるので、あくまで何をどういう手法でやるかっていうのはツールですね。そういう意味で今回はこういうやり方がフィットしそうだなって思ったのも大きいですね。あと、今までの作品とかってライブのことをあまり考えてなかったんですよ。だからライブ用のリミックスとかを考えてたんですけど、今回は割とライブのことも考えて作った部分もあって。だから、今回のアルバム以降は次回作が全く違う作品になるようなこともあんま無いんじゃないかなって思ってて。そういう方向性を決める作品になったかな、って思ってます。
──ある種『Love Flutter』自体が今後の方針のベンチマークにもなるというか。そうして見てみると客演の人選も面白くて、改めてtofubeatsさんが参加していたりするなか、柴田聡子さんやMFSさんのようなやや意外性のあるゲストもいますよね。どういった形で決めていったんでしょうか。
西山:今回はいろんな角度があって、まずtofuさんとやろうと思ったのは、今までだとすごい距離が近いところにいるけど、一緒にやろうとは思わなかったんですよ。まだそのタイミングじゃないな、みたいな。それは柴田くんも僕も一緒で。
柴田:なんか、ヤマカン(※)みたいですね(笑)。もうちょい自分らのレベルを上げてからお誘いしよう、みたいな。やっぱりすごいリスペクトしてる先輩なんで。
※ヤマカン(山本寛)…アニメーション監督。2007年に『らき☆すた』の監督を「その域に達していない」という理由で降板
西山:普通にプライベートも含めてずっと会ってるし、すごく近いミュージシャンかもしれないけど、だからこそ一緒に何かをやらせてもらうタイミングは「仕上がってる」って自分らで思えるときにしようって思ってて、今回はお互いに良いんじゃないか、って自然発生的に浮かんでお声がけしました。それはさっきも言ったように、今後の方針を託すような作品にしたいっていうのもあったんで今かな、という。あとは、他の方に関しては今までよりも制作の相談をする人を増やして、外部の人に意見を聞いたりして広がりを意図的に作っていきました。だから、今までの流れからすると意外性のあるアーティストさんも入ってるのかなと思います。
柴田:「この人と曲作れたらめっちゃ幸せだけど、ちょっとね」と尻込みしてた名前を挙げてもらったりして、背中を押してもらったみたいな形ですね。柴田聡子さんなんか、本当に自分たちも本当に大好きなアーティストの一人なので今まではちょっと畏れ多いような感じでしたし。
西山:MFSさんもそうした流れでダメ元でオファーして、レコーディングのときに「なんで受けてくれたんですか」ってズバリ聞いてみたら「いや、トラックがカッコ良かったんで。」って言われて痺れましたね。自分のライブでもやってくれるって言ってくれて、本当にありがたいなと。
──そうした交流を介して作品がパソコン音楽クラブを知らない人がいっぱいいるフロアにも届くようになったら本当に最高ですよね。
西山:別に誰が作ったかとかっていうのは後から分かるみたいな感じでも良くて、曲が一人歩きしていくって面白いなって思うんで、自分たちがっていうより、あくまで良い音楽つぃて聴いてくれる人が増えたらいいなって思いますね。
──と、いう話をtomadさんも聞いてたと思うんですが、今作はどのあたりが特に良かったですか?
西山:tomadさん、なかなか褒めてくれないですからね。
柴田:ハハハ!(笑)。
tomad:もうなんか、あんまり別に言うこともなくなってきたみたいな感じですよ。でも、ダンスミュージックに向かっていったな、みたいな感じはあって。今まではどっちに向かうかな? っていうのも見てて思ってたんで。トレンド感も含めて真っ向からやっていく感じが良かった、という印象です。
西山:もうシーン側の意見になってるから(笑)。でもありがとうございます。
tomad:曲はどれも良かったっていうか、なんだろう、非の打ち所とかもあんま無いんじゃないかと思うんですけどね。渋いなあ、と。
柴田:なんで減点方式なんですか!
──非の打ち所がない、というこれ以上ない褒め言葉が。全体的に大人になっていった感じもあるように思えますが、どうでしょう?
西山:キックの重さとかは意識しましたね。もっと派手でゴリゴリテクノな感じにも出来たんですけど、それはちょっと違うかなと。
tomad:なんか抑制というか、激しすぎない、あんまり上げすぎないみたいな感覚は全編にありましたよね。
──理性的に気持ちよくなる感じっていうか。
柴田:めっちゃ抑制効いたアルバムですよね、たぶん。
西山:洗練された雰囲気を出したいっていうのもあったし、あとギミックっぽいエモさの演出みたいな感じになるのが嫌だったっていうのもあるかもしれない。理性的な気持ちよさっていうよりは、自分的にはもうちょっとリアルな上振れ感というか。そこでもっと演出するとバーンってなるんだけど、そういう装飾は取り払ってもう少しリアルな感情の動きみたいなものに近づけたいな、って思ったところがあるかなと。
──それこそ普段のクラブで感じるナチュラルな高まりというか。
西山:そうですね。言ったらものすごい感動的な映画で泣くっていうよりかは、何気ないシーンでこうジンとくるみたいな感情っていうか。ちょっと言葉を選ばないといけないですけど、どうしても今ってTikTokとかで「15秒で泣けちゃう」みたいな記号化された感情のギミックをみんな研究したりしてるところもあると思うんですけど、自分らが作るんだったらあえてそういうのは外したいな、って。こういうのって伝わんのかな? みたいな不安はもちろんありましたけどね。
──僕とか西山さん、柴田さんも93,4年の生まれじゃないですか。世代的には三十路に突入していって、やっぱりどこか今のトレンドみたいな意図的なマキシマイズには乗り切れないところもあるのかな、と思います。
柴田:ですよね。あえて言葉を選ばずに言うと、なんか年々不感症みたいになってる気がしてて。なにかにブチ上がっても、本当にはブチ上がれてないみたいな。新しい刺激に触れても自分の知ってるものにそれを当てはめてしまったりとか、そういう現象がめっちゃ起きてたり。かといって刺激を求めて外に出てもインプットが目的になっちゃってないか? とか、純粋に楽しめてない瞬間みたいなものを浅ましいなって自分に対して思っちゃったりとか……伝わるかわかんないですけど。
──いやいや……まさに僕も今めちゃくちゃ悩んでるところで。素晴らしいDJで踊ってるときにも「こうやってキックの重心ズラしてくんだ」とか、すぐ自分のことに応用できないか考えちゃったりしてて。
柴田:そういう楽しみ方は人それぞれですけども、不感症的な状態になってる中でなんとか題材になるものを探そう、みたいな自分の態度への自己嫌悪がピークに達した瞬間があったりして。でもそういう部分と向き合わないといけないな、みたいな……。
──なんていうか、泣ける映画観てるときに「泣けそうだからもう一気に涙腺こじ開けてみるか」みたいな心の動きって無意識的にしたりするじゃないですか。それに対して自分の中ではしたないと思う気持ちがあったりもするし。
柴田:本当にそういうことですね……。
──薄味の醤油ラーメンが二郎になっちゃうみたいに、あらゆる表現がマキシマイズ化していってて。それは進化だからむしろ肯定的には捉えてるんですけど、自分のためのものじゃないかな、と思うことも増えまして。だからこそ、自分のための音楽というか、ちょっとした感動やなんてことのないときめきみたいなものを求めてこういうアルバムを作るに至ったのかな? と僕は思いました。
柴田:まさにそうです。ブチ上がれそうだから思いっきりブチ上がるんじゃなくて、少しの幅の間で揺れ動くダイナミクスを大事にしよう、みたいな感じで、だから抑制っていうのがちょっとテーマになってたのかも。
西山:僕は柴田君ほどはまだ不感症じゃないです、たぶん(笑)。今言ってた話もあんま意識してなかったな。僕は抑制に関して言うと、普通に美意識でやった感じがあるんで。思いっきり突っ走るものよりも統制が取れてる感じの方が良いんじゃないか、ぐらいの感覚で、なんかそこが柴田くんの今の感覚ともハマったんだろうね。
柴田:そうかもね。
西山:まあでも、僕も不感症的な話で言うと、一曲を聴いて涙を流したりするようなことは難しくなって来てて。一曲のパワーで革命を起こすみたいなのって、もう期待できなくなってる時代な気もするんですよ。音楽を聴いてる人たちが自分で選んでないことも多いと思いますし。でも現場とかならまだまだ革命起こせるんじゃないか、っていう期待があって。たとえば出る人のことを何も知らないでクラブに連れてってもらったとき、回してるDJが誰かもかかってる音楽も何もわからないけど場は信じられないぐらい盛り上がって食らうことってあるじゃないですか。
──なにこれ!? みたいなことって、毎週DJとしても客としても通い続けててもいまだに全然ありますからね。
西山:それって音楽そのものよりはムードとかシチュエーションの積み重ねでそう錯覚させられてる向きもどうしてもあると思うんですけど、自分はもうそれでいいなって思っちゃってて。人の営みで化学反応みたいなものが起き続けてるって、やっぱりすごいことだし。だから、そういう意味で言うとその最初の接点として今はまだまだパイの小さい自分たちの音楽みたいなジャンルを聴く人が増えたり、当たり前になっていくきっかけになっていけたらいいな、っていうちっちゃい野心がありますね(笑)。

パソコン音楽クラブ – Love Flutter
Label : HATIHATI PRO. / SPACE SHOWER MUSIC
Release date : August 7 2024
https://ssm.lnk.to/LoveFlutter
1. Heart (intro)
2. Hello feat. Cwondo
3. Fabric
4. Child Replay feat. 柴田聡子
5. ゆらぎ feat. tofubeats
6. Observe
7. Please me feat. MFS
8. Boredom
9. Drama feat. Mei Takahashi (LAUSBUB)
10. Memory of the moment
11. Colors feat. Haruy
12. 僥倖
13. Empty feat. Le Makeup
category:FEATURE
RELATED
-
2022/03/01
パソコン音楽クラブ × リョウコ2000 interview 前編
私生活のムードからモードを鳴らす パソコン音楽クラブは3rdアルバム『See-Voice』で、誰もが自己内省を余儀なくされた日常の中に潜むミニマムなノスタルジーを奥ゆかしいソフトなサウンドに委ね描いた。パソコン音楽クラブのこれまでの作品群にはコンセプチュアルな情景が取り巻いているが、本作は近年のパンデミックの影響下における彼らの内面、閉塞感から一歩踏み出すかのような心模様がささやかに紡がれている。 先日リリースされたリミックス・リワーク集『See-Voice Remixes & Reworks』ではオリジナル曲に参加したボーカリストのリワークに加え、川辺素(ミツメ)、Aiobahn、ind_fris、リョウコ2000といったパソコン音楽クラブとシンパシーを感じるアーティストらが参加し、さらなる視点から心理的な像が結ばれた。今回、リミックス・リワーク集のリリースに際し公開された解説サイト上にて「完成前からリミックスを頼みたい」とパソコン音楽クラブからラブコールを受けていたリョウコ2000との対談インタビューが実現。昨今の私生活に漂うムードから両ユニットのコアとなる音楽性についてまで、日本の若手電子音楽家ユニット同士がゆるく深く語り合った。 Text by yukinoise 『See-Voice Remixes & Reworks』のリリースおめでとうございます。今回はリミックスに参加したリョウコ2000との対談ですが、制作のどの段階で彼らにリミックスをお願いしたいと思いましたか? 西山(以下:西):See-Voiceの制作中にリョウコ2000のEP『Travel Guide』がリリースされて、僕と柴田くんがすごい共感したんですよね。曲を聴いたときに立ち上がってくる音の質感や匂い、雰囲気とかが現に自分たちがやりたかったものに通ずる部分があったり、彼らのモードにシンパシーを感じたんです。『See-Voice』収録曲の『海鳴り』は手法的にも近いものがあって、ぜひリョウコ2000が触ったサウンドを聴いてみたいなと思ってリミックスをお願いしました。 noripi(以下:n):自分たちも『See-Voice』を聴いて共感する部分があったのでリミックスをお願いされて素直に嬉しかったです。 お互い共感しあう作品だったということですが、どのようなところに共感しましたか? n:作った側だからこそわかる部分かもしれないけど、2021年のムード感ですかね。 西:コロナ禍を音楽で表現したいわけじゃなくても、コロナ禍で暮らしたり制作をしている以上いまの状況やムードが自然と作品のモードに反映されてしまう気がしてて。僕らは淡々と自粛生活を過ごしていく中で世の中に対して何か発信するなら、コロナ禍で感じた抑圧や大変さではなく、柴田くんや自分自身に内省を投げかけて深みに入っていく作品を作ろうと思いました。リョウコ2000も同じようなアプローチでアルバムを作ってるなという印象を受けましたし、そういう作品が身近なところにはあまりないように感じたんです。 柴田(以下:柴):実は最初『See-Voice』のアートワークを『Travel Guide』やリョウコ2000のアーティスト画像を手掛けてるイラストレーターの竹浪さんに頼もうとしてたんですよね。制作を進めていくうちに水族館の建物のイメージがしっくりきて、僕らのアートワークは水族館の写真に決まりましたが、竹浪さんのイラストにあるフワッとした感じや言葉にできない感情を音楽でやりたいんだろうなというところに僕はシンパシーを感じました。ピアノ男さんがラジオ〈アフター6ジャンクション〉への出演時に『Travel Guide』について「心の旅行」って話してたじゃないですか、あの感じです。 ピアノ男(以下:ピ):このタイトルを名付けたのはnoripiなのでどういう意味なのかは本当のところわからないけど、個人的にはこのトラベルは実際の旅行じゃないんです。制作時は緊急事態宣言も出ててどこにも行けるような状況じゃなかったので、心の中への旅行のような意味づけですね。 n:EP自体には明確なテーマはないんですが、去年のはじめに自分の親が亡くなってしまって急遽実家に帰省していたんですがその移動の新幹線に乗ってる時にタイトルとトラック名が全部思いついてそれを使用してますね。個人的ではありますが自分の親に少なからず向けてるところもあります。あとコロナ禍の真っ只中なのでこのEPを聞いてどこか遠くへ意識を飛ばして欲しいみたいな気持ちもあります。 西:『See-Voice』のタイトルやテーマになっている海もまさに似たような意味づけなんですよ。コロナ禍で旅行にも行けないから海にでも行ってしんどいことから解放されたいなって願望や、エスケーピズムとはちょっと違う内的な感情のメタファーが海や水みたいなものでして。アルバムを通して自分たちの内省や曲ごとの変化を出しつつ、14曲を聴き終えた頃には聴く前より少し自分のマインドが変化しているなって感じを伝えられたらと思いました。『Travel Guide』の旅行感もきっとパソコン音楽クラブが『See-Voice』でやりたかったことと同じベクトルを偶然にも向いてる気がします。 偶然にも近しいムードを感じ取っていたんですね。両者の作品はコロナ禍に対するメッセージ性は前に出てないものの、自己内省的なテーマが強くありコロナ禍が避けても通れぬ道だった印象を受けました。実際、自粛生活や制作中にどのような過ごし方をしていたか知りたいです。 柴:僕はネットカフェばっか行ってました。家にいても気が滅入るだけなので、近所の漫画喫茶でNANAや東京リベンジャーズ、鬼滅の刃とかを全巻読んだりしてましたね。流行りもんなだけあってそりゃ面白いわって思いながら過ごしてました。音楽面だと、ここ1年は激しい音楽をあまり聴かなくなったなと。 n:僕もそうで、クラブで聴きたい音楽を家では聴かないようになりましたね。嫌じゃないんだけどクラブミュージックはクラブで聴きたいというような住み分けが自然とできてしまって。 西:僕はそれが加速しすぎて、家でモニタースピーカーでちゃんと音楽聴こうとするのがしんどくなってきました。最近買ったAppleのHomePodってスピーカーで適当に聴くのがちょうどいい。『See-Voice』や自分で作った曲をそれで聴くと、遠くから流れてくる余韻みたいな聴き方ができて楽です。 ピ:コロナ禍で在宅ワークしてるとしんどいし、しんどい時に激しい音楽なんて聴けるわけがないから自然と耳にするサウンドはそうなっていくよね。去年は特に久石譲の作品とかをよく聴いてました。 西:僕らも電子音楽ってよりかは宅録系やこれベース入ってるのかな?ってくらいのスカスカな音楽を聴いてた気がします。マスタリングされてないんじゃないかってレベルに音圧がしっかり上がってないようなコンピレーションとか。 柴:特に制作中は久石譲やゴンチチ、あと服部克久の音楽畑とかイージーリスニングが生活にフィットしてた。そういうモードや余韻がアルバムに反映されてると思います。 n:新譜ももちろん追ってたけど、中高生のころ聴いていた作品を振り返ってもう一度聴き直すことをしてました。元々好きだった分素直にいいなと感じるだろうし、今の価値観で聴いたらどうなるんだろうなって思ってハマったのが中谷美紀の『私生活』。 柴:あれは最高ですね、前noripiにオススメされて久々に聴いたらめっちゃ良かったですね。 n:去年からいまに至っても空気感を引きずってる。他にもサニーデイサービスみたいなバンド、クラブミュージック以外のサウンドから影響を受けました。唯一クラブ的な影響があるとしたらThe ChameleonのLinksやGood Looking Recordsとかかな。 西:電子音楽やクラブミュージック以外がリファレンスになってるのもお互い一緒ですよね。僕らも制作中はSKETCH SHOWや戸田誠司のソロ作品、柴田くんが勧めてくれたムーンライダーズの鈴木さんが主宰してた水族館レーベルの若手宅録家コンピとかで。イージーリスニングではないけど軽いリズムマシンの上でギターが鳴ってるような音源やMio Fouも聴いてました。電子音楽じゃないところからリバーブの感じを感じを勝手に電子音楽的に捉えて聴いてみたり、自分たちの制作において打ち込みで再現してみたり。生活にフィットする感じが本当に感動的で、まさに私生活ってフィールがありました。 柴:私生活で気になったんですけど、noripiさんの生活リズムって普段どんな感じなんですか? 西:確かにTwitter見てると朝めっちゃ早い生活してるよね。 n:多分ショートスリーパーなんだと思う、ここ3-4年は2時間の睡眠を3セットくらい繰り返してる感じ。なんでこんな生活リズムになったかわからないけどこれが一番落ち着くんですよね。 柴:どういう環境下でそのセットをしてるんですか?ベッドで? n:寝袋で寝てます…。 (一同大爆笑) 西:なんで寝袋になったんですか? n:断捨離にハマってた時期があって、全部捨てちゃおうってモードになってベッドまで捨てました。でも僕ミニマリストではないんですよ、頭をもっとクリアにしたかっただけで。 西:収集してた雑誌を断捨離してるとは話に聞いてたけども、ベッドまで捨ててるとは。 柴:なるほど、部屋にダンプデータが多かったってことですかね。僕も家にベッドがなくてソファベッドで寝てるから同じく2時間くらいで起きちゃうのはわかる。noripiさんも僕みたいに睡眠環境が普通とは違うタイプなんだろうなって思ってたんで、謎がいま解けました。ピアノ男さんは? ピ:普通にベッドです、寝袋は身体痛くなるでしょ。 私生活を含め近いムードを感じ取ってるだけあって、今回の制作にあたって影響を受けたサウンドの雰囲気もリンクする点が多かったんですね。他にも同世代でユニットとして活動されていたりとパソコン音楽クラブとリョウコ2000は重なる点があると思うのですが、両者の音楽的なルーツなどは異なるところにありますよね? n:ルーツでいうとハードコアが2人の基本にありますね。リョウコ2000も当初はいわゆるクラブ的なハードコアやブレイクコア、ガバをやっていくはずだったんですがいまは見え始めたいろんな音楽を自分たちのやれる範囲で取り組んでいます。 ピ:やっぱりハードコアが大きなルーツとなっているけど、僕もnoripiも相当いろんなジャンルの音楽を聴いてきたつもりではあるのでその幅広さも僕らのコアになっている。だから1作目と2作目ではサウンドが全然違いますし、それって触れてきた音楽の幅広さがないとできないことだと思いますね。 ハードコアを軸にしつつなかなかの幅広さがあるところがリョウコ2000の特徴だと思います。普段どのように音楽をディグっているんでしょうか? n:コロナ禍になる前はBandcampを中心にディグっていて、コロナ以降はあまり良くないかもしれませんがYouTubeにフルアルバムを違法アップロードしているチャンネルから探したりしてます。中谷美紀の「私生活」との出会いもYouTubeで、そういうチャンネルはチャンネルごとに色が違っていたり自分の中にない要素まで行き届くようなコンテンツが多くて。最近はYouTubeチャンネルから探すことが多いです。 西:YouTubeは場合によってはサブスクの限界を超えてきてますよね、中谷美紀は「私生活」だけ配信されてないし僕が聴いていたMio Fouもサブスクにはない。YouTubeの外国人のディガーのチャンネルとかはAIのサジェストよりもっと人間の有機的なセレクトがあるし、サブスクのサジェスト機能だけじゃたどり着けない領域まで探せる。 柴:色が強いチャンネルを見てると友達がたくさんCDを貸してくれたような気分になりますね。 ピ:僕は検索大好きなので、AIが気に入りそうなのを出してくれるよりかは友達のBandcampやTwitterのいいね欄から目ぼしいものを見つけて、関連ワードをどんどん調べていってます。友達のCD棚を勝手に漁ってる感覚に近い。 柴:パソコン音楽クラブのルーツはなんだろう…僕自身は音楽じゃなくて「ぼくのなつやすみ2」ってゲームが好きで、小学生の頃は将来これを作れたらいいなって思ってました。あれってストーリーはあるけどどちらかと言えば雰囲気のゲームで、いま音楽やってるのも雰囲気が作りたくてやってる感じです。打ち込みかつ2人だったらバンドよりも雰囲気作りができるなと思って。そういう話を西山くんとよくしてます。 西:ジャンルとかで音楽を理解してるんじゃなく、いろいろなものを聴いてそこから共通点を勝手に見出してその雰囲気の集合体から曲を作ってる気がしますね。イージーリスニングや宅録系のリバーブの感じを思い込みで電子音楽っぽくしたりしちゃっても、それを認めてくれるのが柴田くん。他のアーティストやちゃんとDJやってる人から見たら怒られそうだけど、パソコン音楽クラブはジャンルに根差しすぎすお互い自由にのびのびやれてるところがコアになってるかも。 柴:自分たちのフィール、モードでやってる感じですね。人が作品から何かを感じるときって、どうしてそういう感覚が立ち上がったのかを直線的に説明するのはあまりにパーソナルすぎて大変なんじゃないのかと思っていて。そのパーソナル具合を紐解いて行って音楽を作るとなると、どうしても音楽性みたいなものの幅は広くなってしまう。音から立ち上がってくる匂いや共通項で語りたい。 西:でもパソコン音楽クラブのテクノ感は柴田くんが作ってるよね。DJツール的なテクノってよりかもっとリスニングに接近した中域多めの、TRANSONIC RECORDSっぽさやフュージョン感あるような打ち込み要素が入ってくるジャパニーズテクノ。それからパソコン音楽クラブはいい意味でジャンルの意味やテクスチャーの解釈を勘違いしているような音楽を意識的にやっています、そういうアーティストがいてもいいと思うんです。 後編へ続く — パソコン音楽クラブ プレイリスト
-
2022/03/08
パソコン音楽クラブ × リョウコ2000 interview 後編
私生活のムードからモードを鳴らす パソコン音楽クラブは3rdアルバム『See-Voice』で、誰もが自己内省を余儀なくされた日常の中に潜むミニマムなノスタルジーを奥ゆかしいソフトなサウンドに委ね描いた。パソコン音楽クラブのこれまでの作品群にはコンセプチュアルな情景が取り巻いているが、本作は近年のパンデミックの影響下における彼らの内面、閉塞感から一歩踏み出すかのような心模様がささやかに紡がれている。 先日リリースされたリミックス・リワーク集『See-Voice Remixes & Reworks』ではオリジナル曲に参加したボーカリストのリワークに加え、川辺素(ミツメ)、Aiobahn、ind_fris、リョウコ2000といったパソコン音楽クラブとシンパシーを感じるアーティストらが参加し、さらなる視点から心理的な像が結ばれた。今回、リミックス・リワーク集のリリースに際し公開された解説サイト上にて「完成前からリミックスを頼みたい」とパソコン音楽クラブからラブコールを受けていたリョウコ2000との対談インタビューが実現。後編では、前編に引き続き若手電子音楽家ユニット同士ならではのしみじみとしたトークが繰り広げられた。インタビューに際し、前編ではパソコン音楽クラブがキュレーションを務めたオリジナルプレイリストも公開中。後編はリョウコ2000がキュレーションを務めており、両記事と併せて要チェックだ。 Text by yukinoise パソコン音楽クラブもリョウコ2000も、独自の音楽性が幅広いからこそできる遊び心のある音づかいをしてるなという印象です。ユニットとして活動している同士信頼関係やフィールの共有がしっかりできているのが理由だと思ったのですが、普段ユニットとしてはどのようなスタイルで制作のやりとりをされていますか? 西:そこは興味ありますね、僕らとリョウコ2000はお互い住んでる場所が西と東で離れてるし。コロナ前から遠距離で曲を作ってるのも一緒だし、二人組で音楽をやってるユニットも知り合いでは彼らしかいないから、リョウコ2000が出てきた時近い境遇のアーティストがいるとなって嬉しかったのを覚えてます。どっちかが骨組みやコンセプトを提案して、そこから制作に入る感じですか? ピ:今回のEPに関しては、自分が別のプロジェクトで作りためていた曲がnoripiのムードにフィットしたところから始まりました。そこからプロジェクトファイルをTwitterのDMで送って、noripiが弄ったデータが返ってきてパスを弄って送って…ってやりとりの繰り返し。 西:コンセプトアルバムになると大変じゃないですか?たとえば『Travel Guide』は後付けだったにしろひとつ大きなテーマがあるアルバムなわけで、パスを投げ合いながら全体のトーンを決めたりお互いのすり合わせをしたりするじゃないですか。僕らはお互いのトーンや世界観を近寄った状態にしてからそれぞれ作っていくので、リョウコ2000が1曲ずつじゃなくてEPとして全体を完成させるまでが気になります。 n:パソコン音楽クラブは目的があってから詰めていく感じなんだろうけど、僕とピアノ男はムードやトーンはぼんやりあっても意図的に言ってない節があって。こういう方向性にして欲しいって言うと自分の作業を分担させてしまうだけになりそうだから、それは絶対にしたくない。最終的にふたつが合体しちゃってるのが理想だと思ってます。2人のムードからモードへ解像度や理解度が完全にマッチしてないと解釈もできないだろうから、意図的に言わずいつの間にかチューニングが合ってる状態にしたいんです。よほどじゃない限り自分からは理想を言わないようにしてるけど、なんやかんや言わずともお互いのモードが完成されていくから良い関係だと感じますね。 西:それはやっぱりお互いの信頼関係ありきですね。 柴:僕たちはよく殺し合いみたいになってますから。 西:そんなことないでしょ(笑)。僕たちの場合は、柴田くんがいっぱい説明してくれようとするけど彼は言葉で伝えるより音楽で伝える方が得意な人で。何言ってるかわからないところを音から頑張って紐解いていってます。それでも限界があるし僕の理解が甘い部分もあるがゆえに抽象度が高くなっちゃうこともある、 柴:そのズレが面白いんだけどね、お互い話し合っていてなんだこれ…?って行き詰まるとseaketaさんが助けてくれる。 西:seaketaさんは物を喩えるのがうまいというか、そこから喩える?って変な形容で物を説明してくれるんですよ。それが妙にフィットする。 柴:彼から返ってきた適当な大喜利が意外と的を得ていたり、問題解決の突破口となることがあって。 これまでseaketaさんに喩えられたことや真理でフィットしたことは何がありますか? 柴:『See-Voice』を聴いてもらった際、これはうわごとだって言われました。うわごとって別に人には聞かせるほどまでもないようなことで、このアルバムで行われていることは「朝起きて適当に時間を過ごしてて、やっとカーテンを開けてみるか…」くらいの内容って言われたんですけど、すごい的確でわかりやすかったです。 西:関係性がなかったら一見悪口みたいな喩えなんですけど、そういうのも遠慮せず言ってくれるのが良いところなんですよね。ひとりひとりが成長するドラマを作ってるんじゃなく、朝目が覚めて真っ暗な状態からカーテンを開けてみるようなちょっとしたことしかしてないけど光が入って物の見え方が違くなったり変化が起きたりするってことを、seaketaさんは説明したかったんだと思います。他にも2人で散歩しているときに「このアルバムは外見はすっごいウェルカムな感じででっかい家に招かれて入ってみたら、ちっちゃい部屋に閉じ込められてずっとうわごとを聞かされてるみたい」って言われたのを覚えてます、こういう喩えを聞くと自分たちでより整理できるようになるので重要な役割を担っているなと。 一見大喜利のようですが、現代詩のようなポエティックさもある喩えですね。 西:個人名やジャンル名で語ったり、歴史的な文脈をしっかり理解した人から批評されるより抽象度が高くてロマンチックな、リリカルな表現で喩えてくれた方がしっくりきます。だからseaketaさんのおかげで曖昧な状態でも作業できてるなとも感じます。 柴:そういえば、僕たちは昔のハードシンセを使って音楽を作るのがコンセプトなんですけど、リョウコ2000は具体的に何を使って制作してるか知りたいです。いろんな話してても意外とそういうのって聞く機会なくて、使ってるソフトやプラグインとか。 ピ:2人ともソフトはAbleton Liveで、プラグインはそんな面白いモノは使ってないです。共通して使ってるのはM1のVSTとSpire。あとは内臓のプラグインやサンプルとか誰もが使ってるようなモノなんで、パソコン音楽クラブみたいに面白い機材は特に。 柴:それが面白い。みんなが使ってるような機材、作ってるような音楽はあるけどリョウコ2000みたいな作風はあんまりいないから。身近な道具の使い方がうまくて面白いんですね。あと他にも聞きたいことがあって、普段お二人は何を食べてますか?ピアノ男さんもnoripiさんにも食べ物のイメージがあまりなくて。謎です。 ピアノ男さんは〈AVYSS ENCOUNTERS 2021〉で音楽ではなく食品をチョイスしてましたよね? ピ:そういえばそうでしたね、何あげてたかな…? 柴:Y1000挙げてましたよ、ヤクルトの最強版みたいなやつ。 西:あれ良いらしいですね、疲労に効いて世の中がパッと明るくなったように感じるんでしょ? ピ:効果の程はわからんけども、Y1000を飲むと朝が始まったなって感じはします。 柴:Y1000飲んだらめちゃくちゃ眠くなりません?睡眠状態がよくなりそうだから僕は寝る前に飲んでます。 ピ:最近だとアボカドをよく食べてます、包丁をやっと手に入れたのでとにかくきりまくってる。どうせ使わないと思ったから調理道具を学生時代の研究室に寄贈しちゃったので、ずっと家に調理道具がなかったんですけど最近また揃えて。ピーマンとかも食べてますね。 柴:noripiさんは何食べてます?一番想像つかない。 n:スーパーのお惣菜とかかなぁ。おじいちゃんおばあちゃんが好きそうなひじきとか入ってる3パックのやつと、安くなってるお弁当を一緒に買ったりしてます。 西:卯の花とか食べてそうですね。 n:落ち着いた食べ物を食べてるかも、湯豆腐とか。 柴:なるほど、西山さんも想像つかないなー。 西:僕はなんでも食べてますよ、柴田くんが一番気持ち悪い食生活してるって。野菜とか全然食べないし。 柴:野菜は全然食べないですね、僕はスーパーで買ったマグロの切り身を丼にしたり豚肉を煮込んでポン酢つけて「酸っぱ!」ってなりながら食べてます。 それぞれの食生活はなかなか聞く機会ないですね。では、リョウコ2000からパソコン音楽クラブの気になるところや知りたいところはありますか? ピ:現段階で今年はどういう作品を作っていきたいか、構想はすでにあるのか知りたいですね。 西:それは僕たちもリョウコ2000に聞いてみたいと思ってました。正直、リリース後くらいからもう『See-Voice』みたいな作品は作りたくないなと考えていて。何故かというとコロナ禍のムードの中で自分と向き合ってモードを作るって結構しんどいんですよ。今年やるとしたらファンキーなモノを作りたいと柴田くんと話してました。今回内省的な作品はやれたんで、それは一回置いといて次は楽しくなれるような音楽を作りたい気持ちがあります。ただこの先もコロナ禍がどうなるかわからないから、自分の中にあるモードがどうなるかもわからない。 柴:楽しい音楽をやりたいよね、最近もどんよりしてるから自分を明るく保ちたい。 西:ここ2年は何事にも真剣に向き合わなきゃいけないムードだったから、ひょうきんさやジョークみたいな成分が世の中にも自分にも足りてなくて。こんな変な名前でユニットやってるのにガチになってるのもバカバカしくなる瞬間もあるからこそ、ジョーク性を取り戻していきたいです。リョウコ2000はどう? ピ:自分はまだEPを全然聴けるテンションではあるけども、次何やりたいかって聞かれたらファーストはアゲでセカンドはダウナーだったし、メンタル的な側面にはあえてフォーカスしないでもっと違うところにフォーカスして作りたいなとは思ってます。でもそれが何かはまだ見つかってない。 西:パソコン音楽クラブもファーストから4作目になるにつれだんだんとアルバムの中の登場人物が3人、2人そして独りになり…とどんどん減っちゃって、そろそろこれ以上減ったら何もない音になりそう。こういう時代だからこそもう少し人の数が増えた作品にもしたいですね。 柴:もうね、残された道がパーティーかお葬式しかない。まあお葬式もパーティーですけど。パソコン音楽クラブの『Night Flow』ってアルバムは友達と歩いてるような温度感なのに、『See-Voice』は30手前の大人が部屋で1人カーテンをちょっと開けて、外が明るいことに4時間くらいかけて気付くようなアルバムだし。こうなると次はもうパーティーか、もしくは心不全で死ぬお葬式みたいなアルバムしか作れないような気もします。だったらもう少し楽しい感情を表現したいなって西山くんと話しました。 西:去年の暮れ、2022年は楽しい音楽が増えるんじゃないかって自分たち以外のアーティストに対しても感じてたんですよ。実際もうそういうムードもあるのかなって。でも同時にコロナ禍は予想がつかない流れにもなってきてるから、すごい不思議な走り出しをしているなと実感してます。 柴:パソコン音楽クラブの場合、自分たちのムードが定まってきたら音源出すぞ!って決めてモードに入ってから音楽を作るんですけど、リョウコ2000は普段どういうタイミングで制作に入ってますか?音楽を作りたくなるトリガーって何かあるんでしょうか。 n:ぼんやりとでも自分が思い描いているモノがあったら骨組み的なのを渡して、お互いの体調や健康面を見ながら徐々に進めてます。楽曲制作を生活の中心に置いてないから、生活がある上での趣味の延長線上でやれるように無理してはやらないって決めてますね。そうじゃないと楽しめなくなるし、だめになりそうなときは何もしないで作れるモードなときがあれば進めてます。 ピ:何がトリガーになってるかはわからないけど、1〜2ヶ月くらい曲を作らないで遊び尽くしてたらいつの間にか曲を作ってる瞬間とかもある。周期的な話なのかなとも思いますね。 柴:自分たちのバイオリズムに曲を作りたくなる波があって、その波に乗ってる感じですかね。僕は自分からDAWを触ることが減っちゃって、イッ!って拒否反応出ちゃうときもあります。 西:柴田くんそんなに強いられて曲作ったりしてないでしょ(笑)。僕はこの前ライブの延期が決まった瞬間には次のEPの曲作ってましたよ、なんかもう忘れよう!ってテンションになって。 柴:すごいな、自分はDAW見てるとExcel見てるような気持ちになったりする。昔はDTMを趣味や遊びの一環としてやれてたけど、趣味の範疇をちょいちょい超えてくることがあるからイッ!ってなっちゃう。 西:作りたくないときは2週間くらいDAW触らないこともあるよ。僕らは聴かせたり一緒にやったりする相手がいるからDTMやれてるのかも。リョウコ2000はそれぞれでも曲を出してるけど、2人で出すときはどういうマインドでやってます? n:前までは自分で曲も作りつつイベントに出たりしてたけど、ちょっと苦しくなっちゃって完全に今はリョウコ2000だけで曲を作って活動してます。それがリョウコ2000を始めた理由でもあって。でも最近は1人でももっとやりたいなと思い始めて触ったりもしてますね。 柴:じゃあお互いのモードが重なったら曲を作ったりリミックスをしたりしてる感じですかね。リョウコ2000とnoripi、epepeでは作風違うしなぁ。 西:意外とユニットでやってる人って少ないよね。僕は3人で活動するとなるとストレスになるときもありそうだなって思ってて。昔バンドやってたから分かるんですけど、2人から3人になると多数決が生まれて民主主義的になる、1人が妥協しなきゃいけない可能性が出ちゃうんですよね。だけど2人だったら相手のことよく分かっていたら上手くいくし、お互いが合意したり譲歩しあったりしない限り何も決められないから、誰かが納得いかないまま進むことはないので仲良い人同士でユニットをやるならストレスがそんなにないのかなって。2人でやれてることに助けられることも結構多いです。 逆にユニットだからこそしんどいことや、活動する上で難しいことはありますか? 西:移動。お互い住んでる場所が離れてるからライブも大変だし、スタジオ入るにも交通費や移動時間が物凄いかかっちゃう。 柴:普段リモートでやりとりしてて、ちょっと一緒に作業画面見たいなーって気軽にできないところとか。 西:それはユニットだからってよりか僕らが遠距離だからって話でもあるけどね。ユニットとしてだと、話し合って進めたり決めたりしないといけないから、フットワークは1人に比べて確実に重くなります。他のプロデューサーやアーティストと話してると、よく2人でできますよねって言われることもありますが、僕らは1人でやるより2人でやる方が楽なんです。3人は難しいけど2人なら大丈夫、その微妙な加減やバランスのいいとこ取りがパソコン音楽クラブでは実現できているんだと思います。 n:リョウコ2000だとやっぱり2人のチューニングを合わせるのが強いて言えば難しいところ。ピアノ男が一緒にやる上でしんどくない相手だからこそやれてます。 ピ:せやねぇ。2人でやることに関してしんどいって思ったことはないかな。 柴:そういう信頼関係やチューニング、気持ちの周期が合わなかったら長く続けられないですよね。お互い半年くらいで辞めてそう。 西:柴田くんが僕と長く一緒に音楽やれてるのも謎やな、柴田くんて相手を選ぶの難しい人だと思うんで。 柴:そうなの!? 西:一緒に音楽をやろうってなったとしてもダルいわってなりそうやもん。偶然バンドをやってるときなし崩し的に始まったからユニットでやれてるけど、手と手を取り合って結成しましょうとは絶対にならなかったと思う。僕や柴田くんみたいな人間が2人もいたらゾッとします。偶然にしろパソコン音楽クラブがやれてるのは運が良かった。 柴:確かに、自分と似た人が2人もいたら嫌だな。ユニットをやれてるのも活動を続けていくにあたって、人生の中で音楽制作の比率や熱量がどれだけ占めてるかってのも重要になると思うんです。お互い近い割合じゃないと続かないかなって、音楽に人生をどれだけ懸けてるかみたいな。 西:人生で何かしたいなっていうのはあったけど、僕も柴田くんも別に音楽じゃなくても良かったはずなんですよ。たまたま身近にあっただけで、全てを捧げるほど音楽の比率が人生を占めてなかったんで。そういう相手だとお互いついていけてなかっただろうな。 柴:日によっては音楽に賭けてみてもいいけど、その波が一緒じゃないとね。 西:全てを音楽に捧げてしまう方より、人生でいろいろ楽しみながら調子良くて余裕のあるときに音楽を作るって方が継続性も高いからね。いつまで音楽をやるかっていう将来性の一致も大事だと思います。世の中には悪魔に魂を売って若くして天才となる道もあるかもですが、死ぬまでボチボチやっていくのもありなんじゃないかなと。 柴:自分たちのペースが崩れ過ぎると音楽嫌いになりそう。 西:ライフワーク的にボチボチ続けられたらいいですね、健康にやりたい。こう言うとやる気ないヤツらに聞こえるかもしれないけど、上を目指すのと同じくらい現状維持って大変なんじゃないかなとも感じます。同じ高さで飛び続けるキツさを、コロナ禍になってから実感させられた人も多いんじゃないかな。どれだけ頑張れど環境や外部要因が変化したら現状維持だけでも難しい、でも活動していくうちに長く続けていきたいなとも思うようになりました。リョウコ2000との出会いもそうですし活動を通じてたくさんのアーティストや音楽に出会えたから、結成から6年でこれだけいろいろあったならこの先60年くらい続けて行ったらもっと面白いことがあるんじゃないかなって。パソコン音楽クラブとしても伝説的な作品を作るんじゃなく、いろいろな出会いや体験を楽しみながらコンスタントに作品を作って活動を継続できたら嬉しいです。 リョウコ2000もこの先コンスタントに活動を継続していきたいですか? n:僕らは本当にのんびりやっていければそれでいいです。リョウコ2000として作品を出すごとにやり切っちゃうというか、ユニットでも個人でもイベントやリリースごとに完結してしまうことが多くて。だから今できることをやるしかなくて長いスパンでは考えてないけど、何か続けられることがあればいいなとは思います。 ピ:死なない程度に無茶をせずやりたいですね。無茶すればそれだけ良いこともあるだろうけど同時にしんどいこともあるじゃないですか。僕らはやっぱり冒険するのが得意じゃないんで、日々の小さな喜びを噛み締めてやっていきたいです。 西:生活を維持しながら自分のやりたいものを作れたらいいですよね。いま音楽をやってる若い人たちにとってはすでに当たり前の感覚になってるのかもしれないけど、学生の時出てたライブハウスとかでは仕事しながら音楽やるだなんてダメ、本気でやるなら正社員なんかならずに頑張れみたいな風潮があったのを覚えてます。リョウコ2000はまさに生活の中でやりたいことがあったら作りましょう、しんどくなったら休みましょうって感じで、健全で理想的な活動の仕方だと思います。 ピ:リョウコ2000とパソコン音楽クラブの違う点って、音楽を専業にしてるかしていないかってところですよね。僕らは別の仕事をしながら音楽をやってるけどおふたりは音楽が仕事になっていて。音楽を専業にした瞬間の覚悟ってどんなものでした? 西:覚悟なぁ…僕も柴田くんも覚悟なんてありませんでしたよね_?ピアノ男とnoripiがちゃんと仕事しながら音楽やれてるのって、それができる人だからなんですよ。柴田くんなんか音楽以外は無理だわって人だもん(笑) 柴:覚悟じゃなくてただ音楽しかできなかったんですよ。それしか選択肢がなくて、働くのはダメだこりゃって感じでした。 西:僕は無理したらまだ社会性があるように見せられたけど無理するのはやっぱり身体に悪かった。音楽を仕事にできたのは運が良かっただけで、覚悟なんてなかったです(笑)。リョウコ2000は最近調子はどうなんですか? n:浮き沈みはありますけどメンタルはアガってはいるつもり。 ピ:僕はアゲでもサゲでもない状態。 柴:僕はアガるようなおまじないみたいなのを生活の中に作りたいですね。ピアノ男にY1000も教えてもらったし、まずは睡眠の質を良くして景気をアゲていきたい。 世の中の風向きがアゲじゃない分、せめて自分たちからアガっていくしかないですもんね。では最後になりますが、パソコン音楽クラブとリョウコ2000の今後の展望について教えてください。 n:もっと無意味で記憶に残らない作品やイベントとかができたらいいですね。豊田道倫さんを聴いたときのような、強烈的に癖があって記憶に残るはずのに聴き終えた頃には考えてたこと全部忘れてる感じの。昨日買った新譜みたいな気持ちでいたいんだと思います。 ピ:なんでここに自分たちがいるのか謎なところに楽曲提供をしたり、効果音を作ったりもしたいですね。僕とnoripiの共通点が音楽だから音楽で表現してるけど、それ以外にもいろいろやってみたい。 西:僕は柴田くんとYouTubeとかやってみたいです。古着屋行って柴田くんにぴったり似合う衣装を探したりしたい。 柴:何やりたいかな…しゃぶしゃぶ食べ放題とか行きたいな。コロナ禍が落ち着いたらみんなでバイキングに行きましょう。 — リョウコ2000 プレイリスト
-
2024/07/13
パソコン音楽クラブが5thアルバム『Love Flutter』を発表
Spotify O-EASTにてワンマンライブ開催 「Love Flutter」の”Flutter”とは、音楽用語でワウ ”フラッター” というレコードや音響機器の回転部のムラにより発生する音の歪みやはためきという意味がある。一方で、心がときめく気持ちを表したり、不安や期待から胸がドキドキする。といった意味ももっている。 友達と遊んでいる中で感じるときめき。ナイトクラブで大好きな曲が流れたときのときめき。好きな本、好きな映画を見ているときのときめき。一人散歩の中で新しい発見をしたときのときめき。日常には様々なときめきが潜んでいる。ダンスミュージックの身体的なビートをベースにしつつも機械的ではない、彼ららしい温かみのあるサウンドからはこうした情緒をふんだんに感じることができるだろう。とのこと。 6月に先行配信した「HELLO feat. Cwondo」よりNo BusesのギターボーカルCwondo。前作「FINE LINE」にも参加し好評を博したアーティスト、LAUSBUBのメンバー髙橋芽以。パソコン音楽クラブも大ファンであるSSW柴田聡子とのコラボも実現。注目を集めるラッパーの一人MFS。5月にニューアルバムを発売し、渋谷WWWでワンマンを成功させたLe Makeup。2000年生まれ、国内外で凛とした存在感が注目されるアーティストHaruy。パソコン音楽クラブの柴田と西山をプロミュージシャンへと導いたtofubeatsが参加。今年で活動9年目となる彼らの好きなもの、ときめくものをふんだんに詰め込んだ「Love Flutter」。8月21日(水)にはCDの発売も決定。ジャケットのディレクターはとんだ林蘭。デザイナーを杉山峻輔が担当。 8月18日(日) Spotify O-EASTにて開催されるワンマンライブ「Love Flutter」リリースパーティーのゲストもアルバムに参加したアーティストの出演も決定し、本日7月13日(土) 正午からチケット一般発売がスタート。クリエイティブチームtsuchifumazuがO-EASTのLEDを全面に使用した演出を担当する。 パソコン音楽クラブ – Love Flutter Label : HATIHATI PRO. / SPACE SHOWER MUSIC Release date : August 7 2024 [CD] PECF-1196 税抜価格 : ¥2,727 税込価格 : ¥3,000 2024.8.21 Release 1. Heart (intro) 2. Hello feat. Cwondo 3. Fabric 4. Child Replay feat. 柴田聡子 5. ゆらぎ feat. tofubeats 6. Observe 7. Please me feat. MFS 8. Boredom 9. Drama
FEATURE
- 2026/03/03
-

-
「森、道、市場2026」にてAVYSS企画「AVYSS Body」が開催
5月23日 MORI.MICHI.DISCO.STAGE (遊園地エリア)
more
- 2026/02/16
-

-
交差する円、重なる身体|AVYSS Circle 2026 photo report
アビサー2026の記録写真 more
- 2026/02/02
-

-
渋谷から新木場廃倉庫レイヴへ|「AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding)」開催
2/13(金) 渋谷から新木場へ座標を再設定
more