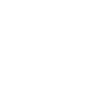読書実録 #5
2018/09/03
不定期にお届けするKentaro Mori(世界的なバンド)のコラム。

■8/20
Ulises Contiのツアーがあるそう。行きたい。
カロリン・エムケ『憎しみに抗って』(みすず書房)を読む。
読みながら、苦しんだ。
なぜ憎しみはなくならないのか、憎しみにどう抗えばよいのか・・・
憎しみは突如沸き起こるものではなく、徐々に育まれていくものなのだ。憎しみを、たまたま生まれた個人的な感情だと考えてしまえば、望むと望まざるとにかかわらず、憎しみがさらに育まれ続ける環境に手を貸すことになる。
傍観者もまたヘイトに加担しているという自覚を持て、と突き付けられた。
自分が「標準」に当てはまる者は、「標準」などないという誤った思い込みを抱きがちだ。[・・・]また、標準に当てはまる者は、そうでない者を自分たちがどんなふうに排斥し、貶めているかに気づかないことが多い。標準に当てはまる者は、その標準の影響力に気づかない。
「私たちは差別「される」側にいるという事実を、(メディアも含めて)日本人の多くが自覚しているようには見えない」という訳者の指摘も突き刺さった。ちょっとしたことで、簡単にひっくり返るような、そんなものだ。
じゃあ、実際どうすりゃいいのよ、ということだが、、、
想像の余地を再び取り戻すこともまた、憎しみに対する市民の抵抗のひとつだ。[・・・]ルサンチマンと蔑視に対抗する戦術のひとつは、幸せの物語である。人を排斥し、人の権利を奪うさまざまな組織や権力構造を前にして、憎しみや蔑視に抗うためには、人が幸せをつかむさまざまな可能性、真に自由な人生を送るさまざまな可能性を取り戻すことが重要なのだ。
ぼくたちは、幸せにならなくてはいけない。
■8/21
Ryo Murakamiの新作『Sea』。ピアノの音も聞こえる。新境地か、楽しみ。黒い海。
『長田弘全詩集』(みすず書房)をついに読み始める。
まずは1965年の第一詩集「われら新鮮な旅人」から。晩年の作品しか読んでこなかったので、一読その重々しさに驚く。
ぼくたちにとって 絶望とは
あるなにかを失うことではなかった、むしろ
失うべきものを失わなかった肥大のことだ。
おびただしい椅子と白壁とにかこまれて
撓(たわ)みながら 鏡は過ぎゆく歴史の記憶をすべる。
多くのものが過ぎていった雨季の階段のうえで
ぼくたちは時代の咽喉を、
そこでただひとりの死者の声をみつける。
名のない魚だって 死んだら
ぼくたちの意識のなかを泳ぐだろう。
鳥だって死んだら意味を飛ぶのだ。
そのように 死者だって回復するのだ。
誤謬のなかの死はいまこそぼくたちの詩をためす。
それというのもいつだって、詩は、どのように過激な行為や言葉よりも過激だからだ。
ぼくたちの内なるやさしさ、
そのものにならねばならないからだ。
(「無言歌」)
「深呼吸」まではまだ遠い。
■8/22
Extrudersの岡田センセイの新バンド。
半分くらい読んでほったらかしていた『フラナリー・オコナー全短篇 上』(ちくま文庫)を再開。
そういえば、こないだ観た『スリー・ビルボード』の登場人物もフラナリー・オコナーを読んでいた。
でもやっぱりこの、暴力・ブラックジョーク・神、というモチーフ、淡々とした空気を読むとミヒャエル・ハネケを感じる。『ファニーゲーム』とか。
森からするどい悲鳴があがり、続いて拳銃の音がした。「どうだね、奥さん。こってり罰をくらうやつもいれば、まったく罰なしのやつもいるなんておかしいと思わないかね?」
短編一作にものすごいエネルギーが詰まっているので、ひとつ読むだけでものすごく消耗する。けど、なぜか読んでしまう。
■8/23

↓これは聴いたことがなかった。ありがとう無印。
「アンビエントとは、自身の奥底にある内面を拡大し、深く入り込んでいく音楽形態だ。アンビエントミュージックを作っていて、これは外部の環境ではなく、むしろ内面の環境だと実感するに至った」
ケイト・ザンブレノ『ヒロインズ』(C.I.P BOOKS)、『正・続 和合亮一詩集』(現代詩文庫)を買う。
古井由吉『杳子・妻隠』(新潮文庫)を読む。
何度も挫折している。が、今ならイケる気がする。
いつのまにか杳子は目の前に積まれた小さな岩の塔をしげしげと眺めていた。[・・・]どれも握り拳をふたつ合わせたぐらいの小さな丸い岩が、数えてみると全部で八つ、投げやりに積み重ねられて、いまにも傾いて倒れそうに立っている。その直立の無意味さに、彼女は長いこと眺め耽っていた。ところが眺めているうちに、その岩の塔が偶然な釣合いによってではなくて、ひとつひとつの岩が空にむかって伸び上がろうとする力によって、内側から支えられているように見えてきた。ひとつひとつの岩が段々になまなましい姿になり出した。それにつれて、それを見つめる彼女自身の軀のありかが、岩の塔をかなめにして末広がりになってしまい、末のほうからたえず河原の流れの中へ失われていく。心細くて、杳子は自分の軀をきつく抱えこんだ。軀の感じはまだ残っていた。遠い遠い感じで、丘の上から自分の家を見おろしているみたいだった。
どうみても「病気」の杳子だが、最後に杳子と男はどうなるのか明示されることはない。
病気を治す/治ることが良いことだとは必ずしも言えないのだ。
何でもない動作にいちいち妙な感じがつきまとうのはかなわない。たとえば手を耳のうしろにやって髪をあぜつけていると、どこかで小肥りの女の人が誰かと噂話をしながら知らず知らず片手を項にまわして痒いところを掻いている、そんな姿を自分の手の動きに感じる。御飯を盛った茶碗を手にすると、箸をもったほうの手が御飯粒みたいな白さとふくらみを帯びてきて、なんだかしきりに羞かしがっているようで、そのくせとても厚かましい感じで、ひとりでにそそくさと動き出す。[・・・]といっても、軀が他人のものになってしまうみたいじゃなくて、どれも自分のもの、どれも自分のものという実感はなまなましいのに、なにか自分の力には余る重みのような気がして、困ってしまう……
■8/24
引き続き「妻隠」。
ときには彼はいくつもの場所に同時にいるような気がした。すると彼はもうどこかにいるという確な感じの支えをはずされて、途方もないひろがりの中に軀ごと放り出され、自分のコメカミの動悸を、ただひとつの頼りとして、心細い気持で聞いていた。動悸の音を細々と響かせて空間はどこまでもひろがってゆき、四方に恐しい深みをはらんだ。しかもその空間のどの部分も、それ自身は空虚でありながら、ちょうど大きな岩の中に封じこめられた紋様のように、永遠で、そのくせどことなく淫靡な相貌を帯びている。
「杳子」に比べると、半分くらいの枚数で、重々しさもないが、どことなく響きあっている。
「一人一人の違いなんて、どうでもいいんだろうね」
[・・・]
「じっさい、われわれはいろんな人間を内側に抱えこんでるようだからな。」
■8/25
これがめちゃ面白かった。
柴崎:建築もそうですが、私が映画はいいなと思うのは、手前と奥がある。それが本当にとってもうらやましいです。手前にいる人と奥にいる人が関係ないことをしているという状況が、実際の空間でも、とても好きなんです。だからそれを小説でやりたいのだけど、小説でそれを書くのはものすごく難しい。小説では二つのことを完全に並行して書くことはできないし、2行を同時に読んでくださいというわけにもいかない。要するに文章は1列しかないから、どうしても順番ができてしまうんですよね。だからそれに近いことをどうやったら実現できるか考えています。
ここんとこヘヴィーな本ばかり読んでいて、気分が鬱々としているので、なんか軽いのは無いかと思って、庄野潤三『絵合せ』(講談社文芸文庫)を読む。
庄野潤三ははじめて読む。
確か村上春樹の『若い読者のための短編小説案内』で庄野潤三も紹介されていたはずだが、その時はまったく興味をもてなかった。
が、さらっと読み始めてびっくり。
机の前に和子と細君がいて、嬉しそうな顔をしている。隣りにいた小学六年生の良二も来て、部屋はいっぱいになった。
「この枝の中に」
と、整理箪笥の上の一輪挿しにいけてある、蔓草のような花をさして、和子がいった。
「尺取虫がいる。どこにいるでしょう」
もう、良い。こんな小説だったんだ。
冒頭の数行で、優しい家族の肖像が浮かぶ。
↓こんなのもある。
その時、隣りの部屋からしゃっくりをしながら、高校一年の明夫が入って来て、
「しゃっくり、止めてくれ」
といった。
すると、しゃっくりが出なくなった。
「あれ?本当に止った」
明夫はびっくりした声を出した。
「いままで止らなかったのに」
「これが本当のシャクトリ虫だ」
黒沢清『ニンゲン合格』を観る。
ふわ~、とした映画で、この映画自体が幽霊のような映画だった。
「おれ、存在した?ちゃんと、存在した?」
「ああ、お前は確実に、存在した」
■8/26
庄野潤三の残りを読む。
断片の連続がゆるやかにつながってくる感じ、小沼丹、小島信夫も思い浮かべた。いや、やっぱり全然違うけど、思い浮かんでしまったということはきっと何かあるはずだ。
そして、待望の待望の、保坂和志イベントへ。
6時間くらいずっとしゃべった。
胸いっぱいです。驚くことに、ほとんど何も覚えていない。
久しぶりに会った親戚のおじちゃん。
そんな感じだった。
■8/27
Astronauts,etc.の新作がいつのまにか出ていた。
これも、ふわ~、としたアルバムで、曲と曲の違いもよくわからないくらい・・・
柴崎友香『わたしがいなかった街で』を読み始める。
「中学の時に見た、たぶん『トワイライト・ゾーン』のテレビシリーズで、人間はずっとおんなじ場所に住んでると思ってるけど、実は一分ごとに新しく作られた世界に移動し続けてる、って話があって、たまに世界を作ってる人のミスで、たとえばソファに置いた新聞みたいなものを置き忘れることがあって、だからさっきまでそこにあったはずのモノがないっていうのはそのせいだ、って言ってて、妙に納得したんだよね。わたし、しょっちゅうモノなくすから」
柴崎さんのこの小説も、「移動」について。
■8/28
引き続き『わた街』。
■8/29
『わた街』読了。
目が痛くなる線香の煙をなんとかかわしながら、白い骨仏に手を合わせていると、ああやって死んでからたくさんの人たちの骨といっしょになるのは悪くなさそうだ、と思う。その膨大な灰の中には、友だちがいるかもしれないし、どこかで一度会っただけでどこの誰ともわからないけど気になっていた人がいるかもしれない。お参りに来る人の中にも、見たことある人がいるだろう。遠い過去も、近い過去も、ここでみんないっしょになって、「現在」の中に煤けた塊として存在し続ける。
1945年、2010年、大阪、東京、広島、沖縄・・・
「わたし」がいなかった街を、時を、想像することはできるだろうか。
この小説の登場人物たちは、違う時、違う場所で、たとえ一度も出会わなくても、どこか響きあっている―
そのことを、この小説を読んだ「わたし」は知っている。
■8/30
Liarsの新作が出るそう。
相変わらずこんな感じ!
ようやく、ザンブレノ『ヒロインズ』読み始める。
手に持った感触が素晴らしく、中身を確かめずに買ったが、読み始めてすぐに正しかったと確信に至る。
私が書いているのは、陰の歴史についての本。書かれた本の陰に隠れた歴史。
■8/31
んあ~!ここ最近聴いてきた中でこれが一番響いた!
引き続き『ヒロインズ』。
文学に少しでも手を染めた人なら誰しも、うすうすと感じていた「犠牲」の歴史。
最近読んでる本のタイトルになぞらえれば「文学は誰のために生まれた」という言葉が脳裏に思い浮かんだ。
日本文学だって、こうした「犠牲」によって生まれてきた、という文学史。
日本文学版『ヒロインズ』の登場が待たれる。
■9/1
この新境地にも驚いた。
世間的に新しくなくても、自分的に新しければそれでいいのだ。
『ヒロインズ』読了。
読んでいる間、常に銃口を突き付けられているようだった。
男に生まれること、そのものの原罪。
読みながら疑問に感じる部分もあった(たとえば、「ほんとに全部「被害者」って言えるのか?とか、全部「男vs女」の構図で考えていいのか?それって結局同じことじゃないの?とか)が、それでもこの一貫した「告発」は突き刺さった。
書きなさい。とにかく、何がなんでも書きなさい。うまく生きられず自分がめちゃくちゃになってしまったら、それについて書いて。そこから学びなさい。そう伝えた。あなたがこれまでしてきた経験が、文学の題材としてふさわしくないなんていうくだらない言葉を、絶対に、絶対に信じてはだめ、と。
ついに『寝ても覚めても』。
その前にこれ
を読む。
濱口:自分が他者であり、他者こそが自分である。その他者を消すことはできない。そうすると、自分が生きるということは、「自分の中の他者と共に生きること」の一択だと思います。それが「受け入れる」ということなのか、あるいは「闘い」なのかは分かりませんが、ほかに選択肢はないと感じています。
このインタビューはものすごい短時間で終わったそう。
これだけのことがすぐ言葉にできる、というのは・・・言葉と身体が一致している。
そして観た。観てしまった。
胸がいっぱいだ。
ちょっとまだ、到底言葉にできないが、
人間への絶対的な肯定がある。
世界への絶対的な肯定がある。
今はこれしか言えない。
■9/2
『寝ても覚めても』の余韻が続く。
『ユリイカ9月号 濱口竜介特集』を読む。
濱口:セリフを言っている人が撮れていればいいわけではなくて、そのセリフを聞いている人っていうのもちゃんと、しかも、セリフを聞いている以上、そこは非常に微細なものになってくるので、その微細さが伝わるようなかたちで撮らないといけない。
映画よりも人間を優先させる姿勢。
東出:面白いことがいくつもあって、たとえば監督が、「ニュアンスを抜いて、相手の心のなかの鈴を鳴らすつもりで台詞を言ってみてください」とおっしゃるんです。
このメソッドは、映画以外でこそ重要なんじゃないか。
映画よりも、人間。
http://kurashi.fujifilm.com/category/interview/100.html
すごい女優が誕生してしまった・・・
唐田さん:たくさん写真を見ていて、もちろん全部写真なのに「これは本当に写真だ」と思える写真があるんです。
−「本当に写真だ」と思える写真…。どのような写真なのでしょう?
唐田さん:なんだろうな…愛を感じるというか…。映画でも何に関してもそうですけれど、やっぱり愛を感じられるものはすごく素敵だと思うんです。
小松理虔『新復興論』(ゲンロン)、ティム・インゴルド『ラインズ 線の文化史』(左右社)を買う。
『新復興論』は、買う前からこれ
を読んでいてぶちあがっていた。
一冊の本が生まれる過程、そしてそれを受け取る人たちの高まり。
「はじめに」だけ読み始める。
観光は常に外部へ扉を開く。同じように、思想もまた外部を切り捨てない。一〇〇年後、二〇〇年後を考え、「今ここ」を離れて思考が膨らんでいくものだ。地域づくりもまた、そうあるべきではないだろうか。ソトモノやワカモノ、未来の子どもたち、つまり外部を切り捨ててはいけない。今ここに暮らしている当事者の声のみで、地域をつくってはならないのだ。
TEXT:Kentaro Mori(世界的なバンド)

category:COLUMN
RELATED
-
2018/07/24
読書実録 #1
不定期にお届けするKentaro Mori(世界的なバンド)のコラム。第一回。 AVYSS編集長から「本とか映画のこと書け」ということだったので、書きます。お付き合いください。 ■7/17 突然だが、恋をしている。 なので、まったく本が読めない。 こないだは1ページ読むのに1時間くらいかかってしまったし、文字がまったく頭に入ってこないし、同じところを何度も読んでいて一向に進まないんです。 では、ごきげんよう。 と、ここで終わりたいところだが、これではさすがに怒られると思うので、頑張って本を開く。 読めない時は、詩集にかぎる。 ということで、今日は『原民喜全詩集』(岩波文庫)を開いた。 冒頭から困惑している。 たとえば 夕ぐれになるまへである、しづかな歌声が廊下の方でする。看護婦が無心に歌ってゐるのだ。夕ぐれになるまへであるから、その歌ごゑは心にこびりつく。 (「夕ぐれになるまへ」) とか おまへは雨戸を少しあけておいてくれというた。おまへは空が見たかつたのだ。うごけないからだゆゑ朝の訪れが待ちどほしかつたのだ。 (「そら」) これは「詩」なのか。 もちろん詩なんだけど、小説のはじまりであってもおかしくない。原民喜の小説は『夏の花』しか読んでいないし、それもよくわからないままに流れて読了してしまった。 しかし、『夏の花』もこの詩も、淡々としたトーンの中に怒りがある、ような気がしている。でももしかしたらそれは、「民喜が原爆被災者である」という知識を持ってしまっていることからぼくが勝手に作り出した物語かもしれない。虚心に読んでいこう。 たった70年ほど前の昭和の作家がこれほどに遠い存在になってしまった。ぼくはこの人のことをまだ何も知らない。 ■7/18 phewとレインコーツのコラボアルバムの先行曲を視聴。 先日のruralでのphewは、本当にすごかった。 3日間のベストアクトだったはずだし、phewはとても謙虚な人なのだと思った。その振る舞いを思い出すだけで、感動して震えてしまう。 「音楽は恐ろしい現実の避難所にはなりませんが、私はこの曲を作っているうちに、この世に生き残るための小さな力を与えると思っていました」 今日も今日とて、本が読めない。 ということで、『原民喜全詩集』の続きを。 ながあめのあけくれに、わたしはまだたしかあの家のなかで、おまへのことを考えてくらしてゐるらしい。おまへもわたしもうつうつと仄暗い家のなかにとぢこめられたまま。 (「ながあめ」) 沢山の姿の中からキリキリと浮び上って来る、あの幼な姿の立派さ。私はもう選択を誤らないであらう。嘗ておまへがそのやうに生きてゐたといふことだけで、私は既に報いられてゐるのだつた。 (「頌」) キリスト教的な、諦念?のようなものもなんとなく感じる。 まだまだ困惑している。 頑ななまでに行替えはないし、短詩でありながら「パンチライン」的なものもなく、「ただそこにある」がある。俳句の趣も感じる。 虚心に読み続けていこう。 ■7/19 食品まつりの新作の先行曲を視聴。 またまたruralの話になるが、食品さんも素晴らしかった。いつもは「仲のいい友達との楽しい闇鍋パーティー」という感じだけど、あの日はしっかりrural仕様のディープテクノで痺れた。何やってもかっこいい。 今日も読めないままに『原民喜全詩集』を。 コレガ人間ナノデス 原子爆弾ニ依ル変化ヲゴラン下サイ 肉体ガ恐ロシク膨張シ 男モ女モスベテ一ツノ型ニカヘル オオ ソノ真黒焦ゲノ滅茶苦茶ノ 爛レタ顔ノムクンダ唇カラ洩レテ来ル声ハ 「助ケテ下サイ」 ト カ細い 静カナ言葉 コレガ コレガ人間ナノデス 人間ノ顔ナノデス (「コレガ人間ナノデス」) おお、突然来た。背筋を伸ばす。 久しぶりにWill Longを聴く。 https://youtu.be/hzvTPKb2txo イイ。 FRUEの第一弾が発表。 すでにすごいメンツ。去年は行けなかったから、行きたい!!! ■7/22 今日は図書館→古本市→喫茶店→本屋。 最近は図書館で絵本を読む。最初は恥ずかしさがあったが、今ではなんのてらいもなく、周りで子どもが騒いでいる中、堂々と絵本に読みふけることができるようになった。なんなら酒井駒子とか読んで泣いたりもする。 古本市では、現代詩文庫の吉岡実と黒田喜夫をゲット。 2週間ぶりの本屋では、リチャード・パワーズ『舞踏会へ向かう三人の農夫 上』(河出文庫)と梯久美子『原民喜 死と愛と孤独の肖像』(岩波新書)をゲット。 気づいたら民喜。民喜に導かれている。 『原民喜全詩集』やっと読み終わった。 もし妻と死別れたら、一年間だけ生き残ろう、悲しい美しい一冊の詩集を書き残すために・・・・・ なんだそれは。ガツーン、というショック。 一九四四年に妻を亡くし、一九五一年に自殺したそうです。 川の水は流れてゐる なんといふこともない 来てみれば やがて ひそかに帰りたくなる (「川」) 「なんといふこともない」、この言葉がぴったりな詩人だった。 民喜ばっかり読んでると死にたくなってくるので、『ワインズバーグ、オハイオ』(新潮文庫)を読み始める。 作家がいた。白い口髭の老人である。ベッドに横たわるのにいつも苦労していた。住んでいる家の窓が高いところにあり、彼は朝目を覚ますときに外の木々が見たいと思った。そこで大工を呼び、窓の高さまでベッドを高くしてもらうことにした。 これに関してはひと悶着あった。南北戦争のときに兵士だった大工は作家の部屋に入って来ると、座り込んで話し始めた。台座を作り、その上にベッドを置いて、高くしたらどうかといった話である。作家は葉巻をそこらに置いてあり、大工はそれを吸った。 冒頭からこんな感じ。やさしい。サローヤンを読むときにも感じる、他人へのやさしさを 感じる。 text by Kentaro Mori(世界的なバンド)
-
2018/08/27
読書実録 #4
不定期にお届けするKentaro Mori(世界的なバンド)のコラム。 ■8/7 『カメラを止めるな!』の監督の短編。 映画の中に現実が組み込まれるメタ映画だが、まったく破綻するスキがない脚本構造の強さ。あと、花嫁、好き。 今日からは『舞踏会へ・・・』下巻。 「すべての言説はその時代の産物である。この言説にしても」。 ■8/9 こんなの出てたなんて知らなかった・・・!!!やっぱりこのドラムすごすぎる。 1年半ぶりでスタジオ入りしたマイルスは非常にモチベーションが高く、両手に掴んでいたのはスライ&ザ・ファミリー・ストーンとカールハインツ・シュトックハウゼンでした。 (菊池成孔・大谷能生『M/D マイルス・デューイ・デイヴィスⅢ世研究』) ようやく『舞踏会へ・・・』読了。 芸術論、写真論、メディア論、小説論、歴史論、すべてが絡まりあって進行していく小説は、ピンチョン的な複雑さがありながら不思議と読み進められた。 我々はフィルム上の出来事に反応しているのではなく、自分の心のなかにおいて同時進行で編集している無数のリールに反応しているのだ。 ■8/11 河野裕子・永田和宏『たとへば君』(文春文庫)を読む。 歌を詠みあうことでよってしか成しえない家族のコミュニケーション、愛、があった。それはいびつなものだったかもしれないが、歌の中が真実だったようにも思える。 一日に何度も笑ふ笑ひ声と笑ひ顔を君に残すため(河野) 一日が過ぎれば一日減ってゆく君との時間 もうすぐ夏至だ(永田) ■8/12 カルヴィーノ『むずかしい愛』(岩波文庫)を読む。 十二の短編集。痴漢小説「ある兵士の冒険」とオタク小説「ある写真家の冒険」が面白かった。 彼女を大きなソファーに座らせると、かれは写真機についている黒い布の下にもぐりこんだ。それはあの後ろの壁面がガラスになっている箱のひとつで、ガラスのところに、乾板に映るのとほとんど同じ像が、時空間内のあらゆる状況から切り離された幽霊のようにかすかに乳色に滲んで映るものだった。アントニーノはビーチェをはじめて見るような感じがした。やや重たげにまぶたを閉じるときや、首を前に突き出すときに彼女がみせる従順さの奥には秘められた何かがあるような気がして、彼女の微笑みも微笑むという行為そのものの背後に隠れているように思えるのだった。 鹿島和夫編『一年一組せんせいあのね』(理論社)が、驚愕の一冊。 子どもたちの感性も素晴らしいが、それを汲み取ることができる先生があってこそ。 子どもたちに詩を書かせることで、子どもたちの潜在的な感情を知る、一種の「箱庭療法」みたいなものともいえるのか? きがかぜにのっていました はっぱがいっぱいありました だから おんがくになるのです (「き」) ねるときは もっとおきときたいのに おきるときは もっとねたい (「へんなこと」) ■~8/19 こないだのMarker Starlingとのツアーも最高だったNicholas Krgovichの新作が、もう!この曲、ライブでやってたな。 旅行中はSuchmosばかり聴いていた。生まれ変わったらSuchmosになりたい。 木庭顕『誰のために法は生まれた』を途中まで。 溝口健二の「近松物語」やギリシャ悲劇を読みながら、法とはなにかを考える本のようで、最初は、なんで演劇なの???と思っていたけど、法って演劇的な空間なんだ、ってことのようです。2千年以上前のギリシャからすでにこのシステムができていて、現在もそれに基づいていることに驚く。面白くなってきたけど、ちょっと疲れたので、今日はこのへんで。 法というのは、以上のような普通の裁判をするのでなく、劇中劇をさしはさんでまずは権力をブロックする、そして劇中劇の外の舞台から、舞台の外、劇場の外にそのまま出て、[・・・]じっくり議論して事柄を吟味し、最終的にどちらの勝ちかを決める、そういうシステムなのです。 旅先で買った、牧野伊三夫『仕事場訪問』(港の人)が素晴らしい。 葛西薫、立花文穂、福田尚代など9名の芸術家を訪ねる。 平易で誠実な文章に引き込まれる。 筆者の芸術への誠実な向き合い方が、文体からうかがえる。 この日、話をうかがいながら、偉そうに、安易に「芸術とは」などと定義するよりも、僕は、まずとことん描いて、そのことを楽しむべきだろうと思ったのだ。 森美術館の『建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの』 が、腰を抜かすほどの素晴らしさだった。濃厚さだった。 「西洋で生まれたモダニズムは、日本にもともと内蔵されていた」、という指摘や、青木淳「ルイ・ヴィトン」の「包装紙としての建築」という和、「内部」と「外部」を入れ子状にする藤本壮介の建築が「和室」の構造からきていることや、「内部=外部」関係をゆるやかに接続する妹島和世=SANAAの「京都の集合住宅」は斬新で、生活の広がりを感じられたし、一方でそれらが注目を集めるほど、坂茂の「紙の建築」は特異であるとも感じた。 これだけ濃密で、知的好奇心を刺激された展示は今まで見たことがなかったと思う。まだの方はぜひ行ってみてください。 大好きな近藤聡乃のアニメーションも面白かった。この人の描く人物の、太ももの太さ。整然とした手書き文字。 TEXT:Kentaro Mori(世界的なバンド
-
2018/08/10
読書実録 #3
不定期にお届けするKentaro Mori(世界的なバンド)のコラム。 ■7/30 Mr Twin Sisterの新曲。 数年前NYで観たライブは最高だった。ライブする喜びにふれて、感動して泣いてしまった。 ボーカルの子は日本大好きみたいだし、メンバーもめちゃいい人たちだったし、誰か呼びませんか? 今日は、柴田元幸・高橋源一郎『小説の読み方、書き方、訳し方』(河出文庫)を読む。 冒頭からグングン面白い。 高橋:本当のことを言うのが文学だというのは、実はまったくの嘘なんですね。でも、よく考えてみたら、これは文学に限ったことではなくて、この世界の構造は基本的に「本当のことは言わない」ということなのかもしれない。つまり「コード」というのは、そういうことですよね。 小説の話をしていて、それが自然に「世界」の話になっていくのが面白い。音楽でも、映画でも、なんでもそうだけど、そのジャンルの話だけしてしまうのはつまらない。 高橋:「小説」というものの最大の特徴は、「人間」がそこに登場することで、そして「小説」以上に「人間」というものを説明できる手段を我々は持っていないからです。 これは、たしか保坂和志も「人間の現われない小説は存在しない。それはなぜなのか、ということをいつも考えながら小説を書いている」(大意)というようなことを書いていた。これを初めて読んだときの「うわっ、ほんとだ、これはすごい、なんかよくわからんけどすごい」と、さも自分が発見したかのように驚いたことを覚えている。それ以来、何を読んでも心のどこかにはこのことが常にある。考えてもわからんのですが・・・ ■7/31 Okkyung Leeのインタビュー や、Latinaの角銅真実のインタビューを読んでいたら、「Mark Fell」という文字を久しぶりに見たので聴きたくなったところ、これまた新作がいつの間にか出ていた。 https://www.youtube.com/watch?v=rSnw-AxWKHk これにはビックリした。Kink Gong化したMark FellもやっぱりMark Fellで、この人の底知れなさ。 引き続き、柴田・高橋『小説の読み方、書き方、訳し方』。 この対談は、「小説というものを読む=書く=訳す、というものはイコールで結ばれるのではないか、といっても全く同じというわけではなく、それは「固体」「液体」「気体」のように変化していくものなのではないか」という所から始まる。 「小説の訳し方」という章でも、「翻訳」の話にはならず、「アメリカ」や「日本」、「世界」の話になる。そこがいい。 高橋:「アメリカ」という言葉を翻訳しても「日本」にはならない。変ないい方ですけど。 つまり「アメリカ」を日本語にしたらどうなるかって考えたんです。翻訳ってそういうことですよね。固有名詞を翻訳するってそもそも無理じゃないですか。だから、誰も「アメリカ」を翻訳しようとは思わないんです。僕は一回やりたいなと思っているんですけど、やり方が見つからない。 保坂和志『ハレルヤ』(新潮社)と木庭顕『誰のために法は生まれた』(朝日出版社)を購入。 保坂和志は発売日に買ったはいいが、楽しみすぎてすぐに開けない。勇気が足りない。 ■8/1 WBSBFK土屋くんが嫉妬しているに違いないPV。 保坂展人『相模原事件とヘイトクライム』(岩波ブックレット)を読む。 社会に蔓延していて、しかもそれを公言してはばからなくなってしまった「ヘイト」の渦。これはどこから生まれるのだろうか。それは醜い「ルサンチマン」から来るのではないか。ぼくの中にもルサンチマンは、ある。それをどう乗り越えればいいか。 読み始めた、立岩真也『増補新版 人間の条件 そんなものない』(新曜社)が面白い。学生時代に旧版を読んだ記憶があって、その時はこのまどろっこしい文体が読めなかったが、今読むとぼくの興味ある領域とぴったりだった。 「不自由」をどう考えるかということ。したいことができないのはたしかに困ったことです。でも、自分ができないことを他人にやってもらったらちょうど同じになる場合もある。 「できることはよいことか」―そんなこと考えたことさえなかった。一度この「常識」を疑うと、いかに自分が「できないこと/人」を排してきたかを思い知らされる。 ■8/2 来たる新作も楽しみ。 引き続き『人間の条件 そんなものない』を。 「できる」「できない」ということの意味をもっと考えたほうがいいだろうと思っています。 […] みんなができるようになる必要はない。 「私の作ったものが私のもの」「私がすることができることが私」ということが「人間の『価値』」とする社会に生きているけど、「そんなものない」。 今読めてよかった。 ■8/3 rei harakamiって、ちょっとナイーブすぎて好きじゃなかったんだけど、今、すごくイイと思える。ようになった。 保坂和志『ハレルヤ』を読む。がまんしきれなかった。 最高傑作。感涙。 時間は、過去→現在→未来、という単線的なものではなく、その度ごとに新しく生まれるものであることを証明してしまった。 過去の出来事は現在の私の心、というより態度によってそのつど意味、というのでなく様相、発色が変わる。 […] 時間のイメージが、流れないで、過去と現在が同時にあると考えている人たちがいるとしたら、その人たちは死を生の終わりであるとは考えないだろう、生には終わりはあるかもしれないがそれを死とは呼ばない、というような。 (「ハレルヤ」) そのことは、19年前の小説『生きる歓び』を再録することでも現れている。 読む度ごとに、新しい今を生きている。すべて響きあっている。 「生きている歓び」とか「生きている苦しみ」という言い方があるけれど、「生きることが歓び」なのだ。 […] 「生命」にとっては「生きる」ことはそのまま「歓び」であり「善」なのだ。 (「生きる歓び」) 問答無用に元気が出る。 世界があれば生きていた命は死んでも生きつづける。 世界があるからこそ命は無になることはない。 ■8/4 齋藤陽道『異なり記念日』を読む。 ぼくのいとこは聴者だが、その両親はろう者で、その家族を思い浮かべながら読んでいた。 一言に「ろう者」と言っても、生まれつきの人もいれば、途中の人もいるし、手話の中にも「日本手話」と「日本語対応手話」と違いがあることもしらなかった。ましてや、ろう者のもとに生まれた聴者がどんなことを思っているかなど・・・何にも知らなかった。 「おとさん。おとーさん」 「なになになに、どうしたの?」 「あったー!」 […] 「音楽、あったー!」 「あ、音楽。ああ音楽か!音楽が、あったんだね」 「異なる」ことを理解し合うことから・・・。 リチャード・パワーズ『舞踏会へ向かう三人の農夫 上』を読み始める。 冒頭、 三分の一世紀のあいだ、私はデトロイトなしで十分やってきた。[…]ところが二年前のある日、都市は私を急襲し、逃げるすきも与えず私を拿捕したのである。 すぐにゼーバルトを連想する。主語は「私」と一人称ながら「私」の存在感は希薄で、建築のディテールが語られる。そして「写真小説」でもある。 そういえば『アウステルリッツ』も『舞踏会へ…』も、駅に到着するところから始まっていたはずだ。 我々はみな、目隠しをされ、この歪みきった世紀のどこかにある戦場に連れていかれて、うんざりするまで踊らされるのだ。ぶっ倒れるまで踊らされるのだ。 ■8/5 今日は久しぶりに映画を。 めちゃくちゃ泣いてしまった・・・ 終了して後ろを振り返ったら、シネコンに満員の光景を見て、また泣けてしまった。 誰にでも薦められる映画。 『舞踏会へ向かう三人の農夫』のつづき。 アウグスト・ザンダーの一枚の写真から小説は始まる。 ロラン・バルトは、絵画と違い、写真は「事物がかつてそこにあったということを決して否定できない」と言っている。 この写真の人物は、確実に在った。では、その写真から始まるこの小説の物語は? 芸術はいまや芸術自身を主題かつ内容としている。絵画についてのポストモダニズム、作曲をめぐる十二音技法、フィクションに関する構成主義小説。さらに言うなら、世紀はそれ自身についての世紀、歴史についての歴史となった。それは静止した、折衷主義の、あまねく自己反映的で、均一に多様な閉じた円環であり、新星出現につづいて宇宙空間に生じる均質的な残骸である。この世紀にあっては、何かが起きればかならず、何か同時に別の出来事が生じてそれと結びつき、共謀してひとつの全体を形成せずにはいない。 安積純子、岡原正幸、尾中文哉、立岩真也『生の技法[第3版]家と施設を出て暮らす障害者の社会学』(生活書院)と『舞踏会へ向かう三人の農夫 下』を購入。 ■8/6 今日は何を読もうか、しばらく前から考えていた。 今年は、現代詩文庫『たかとう匡子詩集』(思潮社)を。 いもうとは冬のひかりの内側をなだれ ひろがっていく 溶けていく 炎のなかを跳びはねて死んだいもうとの その日づけ その刻限 机上の染み (「いもうと考」) TEXT:Kentaro Mori(世界的なバンド)
FEATURE
- 2026/01/17
-

-
“渋谷円環”──最後の接続が点滅|「AVYSS Circle 2026」最終ラインナップ発表
タイムテーブル、オフィシャルグッズなど公開 more
- 2026/01/14
-

-
BALMUNG / chloma / GB MOUTHとAVYSSのコラボアイテムの詳細を公開
ルックをキャラ化した「Curated by AVYSS」の新ビジュアル公開
more
- 2026/01/06
-

-
個を起点に装いとして立ち上がる|POP-UP STORE「Curated by AVYSS」が開催
BALMUNG、chloma、GB MOUTH 参加
more