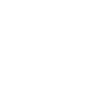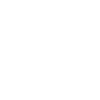轟音の美学─Deftones『private music』Review(後編)
2025/09/12
私的な重さ、あるいは〈夢の重力〉について

20年代以降のネオ・シューゲイズの潮流において影響源となっているオルタナティヴ・メタル・バンド、Deftones。歴史的名盤『White Pony』の発表から四半世紀が経った今年、満を持して10枚目となるスタジオ・アルバム『private music』をリリースした。
メタルやオルタナティブ・ロックの固定観念を崩すかのようなアプローチで強い存在感を長年示し続けてきた彼らの最新作を、スタイリストでありながら長年さまざまな音楽を聴き続けてきたTatsuki Itakuraによる前後編のロング・レビューにて紐解く。前編では「轟音という美学」について整理と再考を試み、後編では『private music』について、過去作との比較や2020年代という時代背景との呼応、ポスト・ジャンル時代における轟音の在り方、「オルタナティブ・ミュージックにおけるカウンター」としてのDeftonesなど、さまざまな視点から紐解く。
Text : Tatsuki Itakura / イタクラタツキ
Edit / preface : NordOst / 松島広人
5. Deftones──深淵に沈む音響
Deftonesは“ニューメタル”の括りで語られることが多いバンドですが、実際に彼らが提示していたのは、オルタナティブ・ミュージックにおけるカウンターであり、深淵へと沈み込む轟音でした。それはシューゲイズやポストロックとも接続するサウンドデザインで、だからこそ今も世代を超えて再評価され続けています。ここではDeftonesの過去アルバムから2作を取り上げ、その轟音の美学を補強します。
『Around the Fur』──逃避の爆音
1997年の『Around the Fur』収録 “Be Quiet and Drive (Far Away)” は、その象徴です。轟音は「遠くへ行きたい」という切実な願望とともにあり、現実から逃避する装置として響きます。未来へ走り抜けたSwervedriverに対し、Deftonesは現実から深く沈み込む轟音を描いたのです。
『White Pony』──深淵のノイズ美学
2000年の『White Pony』では、轟音の深淵性が決定づけられました。“Change (In the House of Flies)”に響くのは怒りの爆発ではなく、孤独や逃避を翻訳する深い海の音響。轟音が「心の奥へ沈む」ための手段となったことで、Deftonesは独自の道を切り開きました。
クラブ的身体性との交差
さらに特異だったのは、その轟音が強烈な身体性を持っていたことです。ダウン・チューニングされた低音はクラブのサブベースのように身体を震わせ、陶酔感を生む。音の壁がノイズでありながら、同時にクラブ的快楽を生む交差点となっていたのです。
畠中実がサウンドアート論で繰り返し論じてきた“音に包まれる身体”という感覚を参照するなら、Deftonesの轟音がクラブ的身体感覚と交差するのは、まさにその現代的リアリティゆえだと言えるでしょう。Deftonesの轟音は外に爆発するのではなく、深く沈む。その体験を通じて、轟音は「哲学」へと昇華されていきました。
6. 『private music』──Deftonesが更新する現在形
2025年、Deftonesが放った最新作『private music』は、彼らの轟音美学をさらに拡張し、過去のキャリアを束ねながらも未来を見据えた作品になっています。
タイトルが示すように、『private music』は「個人的な音楽」。轟音はアリーナの爆音から離れ、イヤホンや自室のスピーカーで鳴ることを前提に再定義されていました。そこにはWisp的な「ベッドルーム感覚」と、Deftonesの「深淵の美学」との交差が確かにありました。アルバムの中で個人的に印象に残った曲を振り返ります。
my mind is a mountain──ネオシューゲイズの記憶
アルバム冒頭を飾る“my mind is a mountain”は、そのタイトルからして象徴的です。ここにはAmusement Parks On Fireの光の轟音や、ネオシューゲイズが提示した「上昇感覚」が明確に刻まれています。分厚いギターの層が立ち上がり、そこにChino Morenoの声が柔らかく重なる。霧の中から光が差し込んでくるような感覚。轟音は圧力ではなく、むしろ精神を上へと導く磁場になっています。2000年代にAPOFを夢中で聴いていた僕からすると、この曲には強烈な既視感がありました。轟音が未来を照らし、リスナーを引き上げていくあの感覚が、Deftonesの手で再び鳴らされていたからです。
locked club──疾走の回帰
続く“locked club”では、Swervedriver的な「疾走の轟音」が蘇ります。疾走するリフとビート、そしてサビで炸裂する爆音。ここでは轟音が沈むのではなく、リスナーを強制的に走らせる推進力として作用していると感じました。Deftonesは深淵のバンドであると同時に、轟音を疾走の美学へと変換することもできる。その柔軟さが、このアルバムをセルフトリビュートに終わらせず、更新の場にしています。
infinite source──Wisp的な共感
アルバム中盤の“infinite source”では、Wisp的なアプローチが顔を出します。ギターは飽和しているのに、声は奥に引っ込み、メロディは儚く揺らぐ。轟音は攻撃ではなく、共感の膜としてリスナーを包み込む。
ここで感じるのは、Deftonesが現代的な轟音の感覚──SNS的な即時共感──を意識的に取り込んでいるということです。TikTok的な拡散を狙ったわけではないでしょう。しかし、音の設計は確実に「孤独なリスナーの耳元で鳴る轟音」になっている。まるでDeftonesが、Wispの世代に手を差し伸べているかのようでした。
milk of the madonna──エモの再解釈
そして“milk of the madonna”では、エモやスクリーモ的な熱情が顔を出します。過去のDeftonesの曲にも見られた切実な叫び、感情をむき出しにする歌声、そこに絡み合う轟音の嵐が広がっていました。ここでの轟音は、深淵でも光でもなく、むしろ「痛みのエネルギー」として作用しています。
7.『private music』──個人的轟音の到達点
アルバム全体を通して浮かび上がるのは、轟音が「Public」から「Private」へ引き寄せられている事実です。アリーナやフェスでの爆音ではなく、イヤホンや自室のスピーカーで聴かれることを前提とした音像。そこには確かにWisp的な「ベッドルーム感覚」がありました。
このアルバムは、Swervedriverの疾走、APOFやAstrobriteの光と過剰、Deftones自身の深淵、そしてWispの共感──それらを総体として束ね、2025年のリスナーに開かれています。だからこそ、多くのアーティストが影響源としてDeftonesを名前に挙げているのではないか。今年9月にトロントで行われたSystem of a DownとDeftonesのジョイント公演に、WispはPolyphiaと共にオープニングアクトとして出演し、世代を超えた轟音の連続性を舞台上で体現する出来事となりました。
Deftonesがなぜここまで長く参照点であり続けるのか。その理由の1つは、彼らが常に「オルタナティブ・ミュージックにおけるカウンター」であり続けたからだと思います。
8. ポスト・ジャンル時代の轟音
つやちゃんが先日自身のnoteに投稿していた “Post-Genre Aesthetic” の視点を借りれば、現在は「ジャンルの時代は終わり、作品は美学・世界観で語られる」時代です。
Deftonesの美学とは何か──解釈は人それぞれですが、僕にとっては「肉体と感情の内面化、影の中で深く響く轟音」でした。そしてそれこそが、今のZ世代の音楽家やリスナーに鋭く刺さっているのだと感じます。
最後に強調したいのは、轟音の意味は世代ごとに変わっても、その必然は変わらないということです。走らせ、照らし、過剰に溺れさせ、深淵に沈め、孤独を包み込む──方法は違えど、音響は常に「遠くへ連れていく力」として響いてきました。
『private music』が示したのは、この轟音の美学がこれからも更新され続けるということ。遠くへ行きたいと願うとき、轟音はきっと、僕たちのそばで鳴り続けます。
前編へ:https://avyss-magazine.com/2025/09/12/63685/
–
✍️ イタクラタツキ
instagram:https://www.instagram.com/tatsuki_itakura/
category:REVIEW
tags:Deftones
RELATED
-
2025/09/12
轟音の美学─Deftones『private music』Review(前編)
私的な重さ、あるいは〈夢の重力〉について 20年代以降のネオ・シューゲイズの潮流において影響源となっているオルタナティヴ・メタル・バンド、Deftones。歴史的名盤『White Pony』の発表から四半世紀が経った今年、満を持して10枚目となるスタジオ・アルバム『private music』をリリースした。 メタルやオルタナティブ・ロックの固定観念を崩すかのようなアプローチで強い存在感を長年示し続けてきた彼らの最新作を、スタイリストでありながら長年さまざまな音楽を聴き続けてきたTatsuki Itakuraによる前後編のロング・レビューにて紐解く。前編では、まず「轟音という美学」について、Wispなどのネオ・シューゲイズなどさまざまなバンドを例に挙げつつ整理と再考を試み、後編では『private music』の内容へ多角的に迫ります。 Text : Tatsuki Itakura / イタクラタツキ Edit / preface : NordOst / 松島広人 1. 轟音の美学──逃避・静寂・解放のプロセス 「轟音」という言葉は、音楽について語るときに多用されがちな表現です。しかし、僕にとっての轟音は、大音量やノイズそのものではなく、「身体と意識の両方を別の次元に連れていく力」のことを指します。それが僕自身の音楽体験の核でもありました。 轟音を「美学」として考えるとき、まず浮かび上がるのは「外に向かう衝撃」と「内に沈む音響」の二種類です。前者はハードコア・パンクやメタルに典型的で、社会や他者に叩きつける運動と捉えられます。後者はシューゲイズやポストロックに見られるような、自己の内面に閉じこもる沈潜です。 しかし「轟音の美学」はこの二項対立に収まりません。僕が音楽を通じて感じてきたのは、「逃避 → 静寂 → 解放」という心理的プロセスです。音の壁はまず現実からの逃避を可能にし、やがて思考を止めるほどの静寂を生み、最後に解放を与える。このサイクルこそが、僕にとっての「轟音の美学」でした。 そして、この美学は世代ごとに姿を変えてきました。90年代にDeftonesが示したのは“肉体的(かつ現場的)な深淵への沈降”でした。2020年代を代表するシューゲイズ/グランジゲイズのアーティストであるWispが提示したのは、SNSとヘッドフォン文化に根ざした“共感の轟音”でした。同じ轟音でも、リアルとバーチャルでは鳴らされ方も受け止められ方も全く異なります。 Deftonesの『private music』を読み解く上で、「轟音の美学」を見直すことには意味があります。それは単なる爆音でもノイズでもなく、常に「逃避」「静寂」「解放」を更新してきた音の哲学だからです。これは僕にとっての轟音の美学であり、同時にDeftonesを通じて見えた“音楽の聴かれ方の変化”の記録でもあります。 2. Swervedriver──疾走する轟音の原点 90年代初頭のイギリスで活動していたSwervedriverは、しばしばシューゲイズ・シーンの括りに入れられますが、実際にはMy Bloody Valentine(以下、MBV)やSlowdiveと並べて語ると、その異質さが際立ちます。MBVが「音響を海のように広げる」バンドだったとすれば、Slowdiveは「夢の霧のように沈潜させる」バンドでした。それに対してSwervedriverは、「轟音をエンジンに変えて疾走する」存在だったのです。 1991年の1stアルバム『Raise』は、まさにその「疾走する轟音」の美学を体現していました。代表曲“Rave Down”では、ノイズの壁が一直線のアスファルトの道となり、リスナーを強制的に走らせます。推進力としての音響──これこそが当時のUKシーンの中でも独自のものでした。 多くのシューゲイズ・アーティストが“内向きの逃避”を描いたのに対し、Swervedriverは「外側への突進」を生んでいました。彼らの音を聴くと、夜の高速道路を全速力で駆け抜ける感覚が生まれる。轟音が「走る」ための言語になったのです。 彼らのサウンドにはMBV的な要素もありました。ディストーションで飽和したギター、ノイズを空間的に重ねる構築性。しかしSwervedriverの場合、それが「揺らぎ」や「没入」ではなく「加速」と結びついていた点が決定的に違います。例えば“Son of Mustang Ford”や“Sandblasted”にしても、どの曲も「走り続けるための轟音」になっている。轟音はリスナーを止めるのではなく、さらに遠くへ連れ去るドライビング・フォースでした。 この「疾走する轟音」という感覚は、アメリカ西海岸で活動していたDeftonesとも直接的な関係があるわけではありません。しかし、彼らの2ndアルバムの代表曲の1つである“Be Quiet and Drive (Far Away)”を聴くと、タイトルからして「走ること」と「遠くへ行くこと」が結びついているのが分かります。ここにはSwervedriver的なドライビングメタファーが、時代を超えて響き合っていました。UKとUSという別々のシーンで、ほぼ同時期に「轟音=ドライブ」という感覚が現れていたこと自体が興味深いのです。 Swervedriverの“Rave Down”とDeftonesの衝撃は、直接の影響関係ではなく、むしろ聴き手にとって必然的に接続される体験だと言えるでしょう。 また、Swervedriverが提示した「疾走する轟音」は、その後、クラブカルチャーやエレクトロニック・ミュージックの感覚とも重なっていきます。“低音の反復” が身体を揺らすように、彼らの轟音もリスナーを突き動かし続ける。轟音が生み出すのは「止まらない身体」でした。ロックとダンス・ミュージックをつなぐ萌芽が、ここには確かにあったのです。 一方、同時代のSlowdiveは全く逆の方向で轟音を鳴らしていました。霧のように広がるアンビエンス、音に沈み込む感覚。Swervedriverが「遠くへ駆け抜けるための轟音」を提示したならば、Slowdiveは「夢に沈むための轟音」を描き出した。外へ走る推進力と、内へ沈む静謐さ──この二つの極の間に生まれた磁場の中で、Deftonesは“疾走”と“沈潜”の両義性を抱え込みながら、独自の轟音を形づくっていきました。 3. ネオ・シューゲイズ──Amusement Parks On FireとAstrobriteが示した光と過剰 2000年代、シューゲイズシーンは「ネオ・シューゲイズ」と呼ばれる再評価の波を迎えます。90年代にMBVやSlowdiveが築いた神話は、ある時期にグランジやブリットポップに押し込められたものの、インターネットの拡大とともに新しい世代へと渡っていきます。ここでは僕が聞いてきたAmusement Parks On FireとAstrobriteについて、Deftonesと接続します。 この2組は、轟音の使い方において正反対のアプローチを取っていたと言っていいでしょう。Amusement Parks On Fire(以下、APOF)は轟音を「光」として響かせ、Astrobriteは轟音を「過剰」として提示しました。つまり、同じネオ・シューゲイズ・サウンドの中でも、轟音の美学を真逆に振り切っていたのです。 Amusement Parks On Fire──轟音を「光」に変える APOFは2004年、当時18歳のMichael Feerickによって始まりました。セルフタイトルのデビュー作は、分厚いギターを重ねながらも、メロディが前景化しているのが特徴です。普通、爆音はメロディを飲み込み、聴き手を壁の中に閉じ込めてしまいがちです。しかしAPOFではむしろメロディが押し上げられ、光の束として響く。 例えば “Venus In Cancer”。轟音が満ちているのに、そこには鬱屈ではなく未来への明るさがある。霧を突き抜ける朝日のように音が広がっていく。Swervedriverが疾走感で未来へ突き進んだのに対し、APOFは光のサウンドで未来を照らし出した。方向は違っても、両者は共に「轟音を未来志向へと変換した」存在でした。 Astrobrite──轟音を「過剰」に推し進める 一方でAstrobriteは、轟音を「過剰」にまで肥大化させました。Scott Cortezによるこのプロジェクトは、彼がLoveliescrushingなどのノイズ・ドリームポップの経験を経て生まれたもので、代表作『pinkshinyultrablast』(2002)と『whitenoise superstar』(2007)は、轟音の極点を示しています。 『pinkshinyultrablast』は、重ねに重ねられたギターが音の洪水のように押し寄せ、メロディはかすかに顔を出すのみ。圧迫感と同時に甘美な恍惚をもたらす体験でした。続く『whitenoise
-
2025/07/11
Deftonesが5年ぶりのアルバム『private music』を発表
『White Pony』から25周年 近年ではWispをはじめ、20年代のシューゲイズアーティストたちの影響源であることも注目されているオルタナティヴ・メタル・バンドDeftones。そんなDeftonesの重要作品『White Pony』が発売から25周年を迎えた今年、バンドは10作目のスタジオ・アルバム『private music』のリリースを発表。リードシングルは「my mind is a mountain」がリリース。 DeftonesはNick Raskulineczと共に『private music』を共同プロデュース。このアルバムは2020年の『Ohms』に続く作品で、同じ年には『White Pony』の20周年を記念して、DJ ShadowやRobert Smithらが参加したリミックス・アルバムもリリースしている。8月からは大規模な北米ツアーが再び始まる。ツアーのサポートアクトはPhantogram、Idles、Barbarians of Californiaが務める。 Deftones – private music Label : Reprise / Warner Release date : August 22 2025 Pre-order : https://deftones.lnk.to/PrivateMusic Tracklist 01 My Mind Is a Mountain 02 Locked Club 03 Ecdysis 04 Infinite Source 05 Souvenir 06 cXz 07 I Think About You All the Time 08 Milk of the Madonna 09 Cut Hands 10 ~Metal
-
2024/04/01
轟音の奥に広がる静謐に身を漂わせて|Waseda Music Records主催「lull」開催
4/30 渋谷La.mama 早稲田大学公認の音楽レーベルサークルWaseda Music Records主催の音楽イベント「lull」が2024年4月30日に渋谷La.mamaにて開催。 本イベントは、轟音の奥に広がる静謐に身を漂わせ、パーソナルな感傷と壮大な音風景の結節点を体感できる場を提供する、とのこと。 – 企画名:lull 会場:渋谷La.mama 日時:4月30日(火)開場18:30/開演19:00 出演:宇宙ネコ子、Healthcare and medical、iVy、Moon In June 料金:学生2500円、一般3500円、当日4000円(+1ドリンク) チケット購入:https://t.livepocket.jp/e/a8w5d ※学生の方は当日顔写真付きの学生証をお持ちください。 ※別途ドリンク代700円をお支払いいただきます。 主催:Waseda Music Records お問い合わせ:wasedamusicrecords@gmail.com
FEATURE
- 2026/02/02
-

-
渋谷から新木場廃倉庫レイヴへ|「AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding)」開催
2/13(金) 渋谷から新木場へ座標を再設定
more
- 2026/01/25
-

-
渋谷の路地裏に出現する未来都市ALLEY108にて「AVYSS RAVE」開催
2月14日(土) 渋谷センター街の路地をジャック
more
- 2026/01/19
-

-
私の正直な感情について|daine interview
1/23 AVYSS Circleにて来日 more