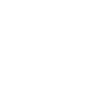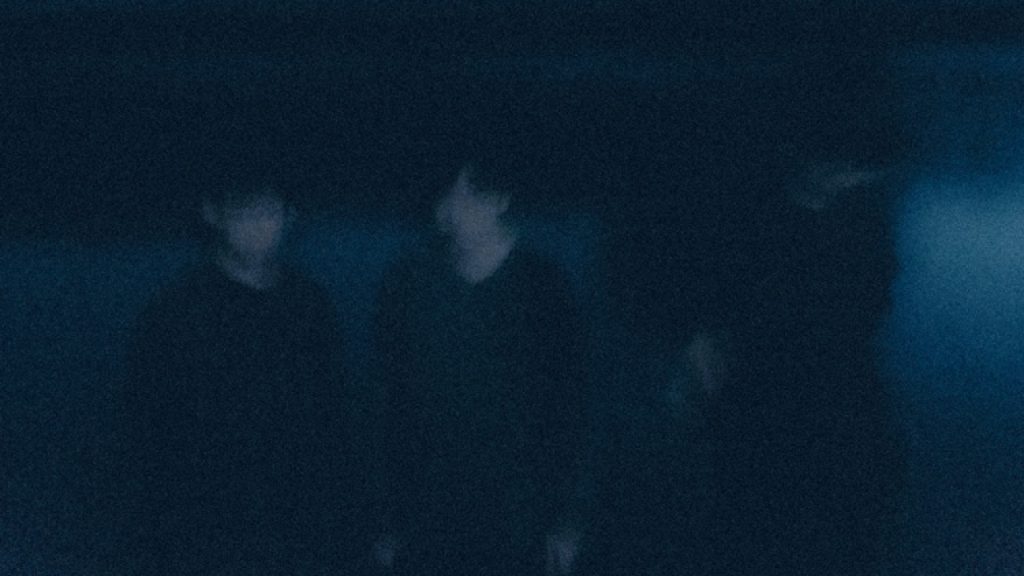仮想の大陸を目指して|雪国 × ephemeral 10000字 interview
2025/01/16
『Lemuria』リリースパーティー開催

2024年も終わるころ、雪国の1st EP『Lemuria』を聴きながら取材先の都内某所まで歩いた。視界に映るイルミネーションの輝きや、夕暮れを過ぎて夜がやってくる瞬間のあの感じと本作が、怖いぐらいの解像度でリンクしていて目眩がしたことが忘れられない。
そのとき脳裏をよぎったのは、múmやSigur Rósといった寒い国のフォークトロニカ~ポストロック……の影響下で音楽を生み出していた日本のインディーバンドをライブハウスの隅でじっと観ていた2010年代の日々のこと。そんな恥ずかしい感傷につい飲み込まれそうになるほどに陶酔的なサウンドスケープを、自分よりも一回り以上下の2003年生まれの世代が築き上げているという事実にも面食らった。
同時多発的に巻き起こったポスト・シューゲイズのようなムーブメントがある(かもしれない)昨今、その文脈のなかでも突き抜けた秀作として耳目を集めた雪国の1stアルバム『pothos』は、2020年代初頭の共通項である「マキシマリズム」を想起させるラウドな音像を、スリーピースというミニマルな編成でたおやかに展開する美しい作品だった。
しかしながら、彼らはそうした場所から出掛けて、とっくに別の地平を目指しはじめている。それは2月3日(月)に開催される『Lemuria』のリリースパーティーの、バンド発信の催しとしては稀有な「リスニング体験」に振り切ったラインナップからも見て取れる。
今回AVYSS Magazineでは、雪国のコンポーザーとフロントマンを務める京英一と、リリースパーティーの共同オーガナイズを務めるイベントシリーズ〈ephemeral〉を主催するDJ・myeinへクロスインタビューを敢行し、「かつて夢想された存在しない大陸」を意味するLemuriaというタイトルに託された意図、そしていま揺籃期を終え次のフェーズに進もうとしている20年代以降の音楽シーンの在り方など、リリースパーティーに紐づくさまざまなトピックについて伺った。
Photo by Momoko Yonezawa
Interview&Text by NordOst / 松島広人
──よろしくお願いします。まずはデビューアルバム『pothos』から新作EP『Lemuria』に至るまでの足跡について聞かせてもらえればと。前作とは大きく異なるトーンで、個人的にはより一層グッと来るものがありました。
京英一(雪国):基本的に、楽曲は活動の流れとは別で常に作るようにしてて。「ワンマンをやる」とかを理由に、そこに向かって作ろうとするようなことはないですね。できていった曲をタイミングで区切って作品にまとめる感じです。『Lemuria』の収録曲を作ったのは、『pothos』のレコーディングが終わってからリリースまでの半年ぐらいの期間で。その時期のムードが今回の作品に反映されているのかなと思います。
https://friendship.lnk.to/pothos
──トラックの骨子を作っている京くんから出てくる物事を集約したものが『pothos』で、そこからさらに飛び出したものが今回の5曲になるわけですね。今作は1stの延長線上でありつつ、ここ半年ぐらいのモード感が反映されているというか。
京:『pothos』は雪国というプロジェクトの一旦の完成形として出来上がった曲をまとめたものでした。だから特別な作品になったのかなと思います。一方で初期衝動的に作った『pothos』は全体的に音像がラウドすぎて「それって俺たちにとってどうなんだろう?」という反省もあって。それを踏まえて、音色の差し引きで繊細な曲を作り込んでいきたかったんですよね。
──音像の大きさからいわゆるネオ・シューゲイズ的なムーブメントと結びつけて語られることもあったけど、『Lemuria』の5曲をしっかり聴いてみると、むしろ逆方向に向かっているような気がして。それは2010年代の、海外のサウンドを換骨奪胎した日本的なインディーポップとも重なるような感覚ですよね。だからこそ、音楽的になにを吸収した上で今作が生まれたのかが気になって。
京:前からいわゆる北欧的なインディーポップの要素が好きだったんですよね。
──なるほど。かすかに鉄琴のようなサウンドが織り込まれてる点ひとつとってもそうだし、そもそもバンド名もズバリ雪国だし(笑)。
京:そうですね(笑)。そういう点もありつつ、今作からシンセサイザーとか新しく手にした機材を取り入れたことで、ギターの音量の大きさに依存しなくても新しい展開が作れるっていうことに気づいて。それが今回の作品の肝になっている部分かなと思います。
──同名の伝説的なインディー/エモバンドもニューヨークに存在しますが、『Lemuria』っていうタイトルの意味自体は「かつてあった仮想の大陸」みたいなものですよね。そうしたファンタジックな概念を下地にしているんでしょうか。
京:(Lemuriaという単語については)myeinに教えてもらいました。俺がダンスっぽくない質感のDJmixに興味が湧いて、一緒に作ろうよって流れになったとき、あらかじめその名前がつけられたプレイリストが送られてきたことがあって。そういうのも印象的だったし、「レムリア」って単語自体が直近で作った曲たちと結びつくアイコニックなワードとして今回立ち上がってきたので、そのままタイトルとして使わせてもらうことになりました。いまの雪国のモードとして、アンビエントとインディーロックの有機的な部分みたいなものを融合させるような取り組みに挑戦したいという気持ちもあったし、今回のリリースパーティーにもつながるよな、と思って。
──EP自体も素晴らしい完成度なのはもちろん、現代的なプレイリスト、楽曲単位での聴取態度の外側でやっていくという強い意志も感じられる内容で。もちろん曲単位で切り取っても楽しめるんですけど、5曲・23分をひとつのまとまりとして聴き通すことでしか得られないような感覚も詰まっていて。ごく私的な感想ですが、雪国のこれからにとっても記念碑的な作品になっていくような気さえします。
京:俺たち的にもその感覚はあって、『pothos』よりも大事な作品として後々残っていくんだろうな、という気がします。

──今回シンセサイザーとして入っているのが、先日”After the quake”というmyeinさんの〈ephemeral〉や今回のリリースパーティーにも連なるような企画を開催されてたriliumさんみたいですね。
京:彼女はいま、実質的にはほぼ雪国の一員なんですよ。スリーピースだけどライブは5人編成でやっていて、riliumともうひとりのギターが重要なサポートメンバーとして俺たちを支えてくれてます。
──雪国については、スリーピースというバンドとして一番プレーンな形を取りつつも、決してサウンド的に目指している場所はそこじゃないというのも印象的で。いわゆるバンドシーンにも背を向けずコミットしつつ、そこに収まらない形を模索した結果が作品づくりだけじゃなく、今回のWWWでのリリースパーティーのような試みにもつながっているのかなと。それは以前取材したときにも言っていた「仕組みの外側で居場所を作る」という意思ともリンクしてますし。
京:それはまさにそうですね、結果的にそうなったというのが正しいですけど。リスニングに振り切ったリリースパーティーをやるというのも、音源とはまた違う形での俺たちの表現の一形態、のような感覚ですね。
──『pothos』以後の半年強の期間で、京くんとはかなりいろんなパーティーでバッタリ会ったりもしたし。そういうところでまた違うインスピレーションを蓄えていったのかなと。
京:「もっといろんなイベントの形があっていいんじゃないかな?」っていうのは、自分の職場でもある渋谷WWWを通して色々な催しを観てずっと思ってきたことで。たとえばWWWβの〈loopな〉もそうだし、今回リリースパーティーのオーガナイズに入ってもらったmyeinが調布Crossでやっている〈ephemeral〉のようなイベントもそうで、ありそうでなかったことを形にしてるなと。そういうサジェストを、より大きな形でやってみることがいま大事なんじゃないかな? と思ったことも今回のリリースパーティーのきっかけになってます。
──私見ですけど、コロナ禍以降に立ち上がったいろんなムーブメントの残り香が違う形に転化したものが、2023年~2024年にかけて具体化されていったなと思ってて。その一環として、ラウドな方向性やマキシマイズ的なアプローチの反動で、よりプレーンで繊細なものに立ち返っていってる流れがあるというか。
京:それはたしかにそうかも。
──だから、京くん自身がスタッフとして大きな場所で働きつつ、そこにはない物事への興味も強まっていったことがいまのスタイルに反映されてるのかな、とも思ってて。具体的にはどういう物事に感化されました?
京:きっかけは明確にあって、下北沢SPREADでケイタ君という同い年のオーガナイザーが手掛けていた〈uncircle〉に出演したことなんですよね。各回全然違う形のチャレンジをしてるような感じで。そもそも『pothos』のリリースパーティーのとき、あえて会場を分けて別々のコンセプトに基づいてやってみたのも〈uncircle〉が着想源になってて。それからmyeinとの交流が生まれたり、クラブに行ったりといろんな体験を経たことが、俺たちのいまのモードに繋がってるのかなと。
──〈uncircle〉から出発して〈ephemeral〉へ、という流れも気になるので、myeinさんについての話も伺えれば。DJやキュレーションのサポートをお願いしようと思ったきっかけは?
京:SoundCloudで彼女のDJmixを聴いたのがきっかけでした。そもそもクラブやダンスミュージック自体にほとんど触れてきてなくて、入口も以前リリースパーティーを一緒に作ってもらったatriくんのイベント〈投擲〉になんとなく行ったぐらいだったので、当初はオンビートで激しめな表現という認識だったんですよね。でも、myeinのDJmixはアンビエント的なサウンドスケープが広がるような感じのオフビートな表現で、しかもそれがイベントで披露されたものだった、ってことに衝撃を受けて。過度に盛り上げず、異なる曲を通じてひとつの世界観を作り込むようなことを、クラブっていう場所でやるのってアリなんだ! って。その後実際に足を運んで聴きにいったりした上で「呼ばせてください」って声をかけたところがスタートでした。
──そういう原体験のしかたもすごく現代的だなあと。myeinさんはDJ自体はどれぐらいやられてるんですか? 〈ephemeral〉の立ち上げの以前からなのか、それともイベントシリーズを始めてからなのか、そのあたりの遍歴もすごく気になります。
myein(ephemeral / 調布Cross):DJは2022年の秋頃からなので、だいたい2年弱ぐらいですかね? 実は私、調布Crossで働き始めるまではクラブとかライブハウスに一切行ったことなくて。働きはじめてからそこにある機材をなんとなく触るようになったのがきっかけでした。
──僕自身DJをはじめたのがコロナ禍の2021年頃だったのでその感覚は分かりつつ、でも同時期にスタートした人の大多数はアッパーな感覚でオンビートな表現にトライするところから始まっていったと思うんですよね、レイヴ~ハードコア・テクノみたいな当時のムード的にも。だから、最初からアンビエントやドローンといったダウナーなスタイルに行き着いているのも不思議に思えて。
myein:それは自分の趣向がそうだったからかも。DJを始めたてのころからBPMとかに一切とらわれず、お気に入りの曲をセレクター的にかけることが多くて。たとえばフライング・ロータスのような、なんというかスピリチュアル・エレクトロニカみたいな感じの音楽は元々好きで聴いてましたし。
──myeinさんの音楽的な原体験はどういうものだったんでしょうか?
myein:いわゆるメジャーな洋楽のヒットチャート的な音楽やThe 1975みたいなバンドが好きで。その後、自然といまかけているような音楽をじっくり聴き入ることを自然とやるようになりました。逆に邦楽はPerfumeとかぐらいしか分からなくて、たとえばボーカロイドの文化とかは私の世代ではすごく大きいものだけど、そういうものは全然通ってきてなくて。でも、DJをはじめてからはダンスミュージックやヒップホップの良さもわかるようになりました。
──ドローン的な美学を最初から貫いてる人の指すヒップホップ像というのも気になります(笑)。
myein:それもオルタナティブ・ヒップホップっていうのかな? 日本だとDos Monosがやっているような、ああいうバランス感のものが好きですね。あと、調布Crossがすごくブーンバップ的な、トラッドなヒップホップに強い箱なのでそういう物事を観て色々と得るものもありました。
──ベーシックなライブハウス的なイメージだったんですが、実はコンシャスなラップが根強い場所なんですね。結構意外です。つまり衝撃的な出会いがひとつあったっていうよりは、自然と行き着いたのがいまのスタイルだったというか。
myein:そうですね。あとは幡ヶ谷FORESTLIMITや〈K/A/T/O MASSACRE〉とかに行って、本当に自由で幅広いスタイルをたくさん目にしたのは大きかったかな。「いろんな形があるんだな」っていうのも、たとえばcocoaさんっていうDJのファンシーで独自のスタイルが確立されている表現に触れたりしたことで発見していったというか。DJって、踊らせるだけじゃないんだなと。

──といった遍歴を、より具体的に形取ったものが主催シリーズの〈ephemeral〉だと思うんですが、こちらはどのようなコンセプトのもと立ち上がったんでしょうか。
myein:以前調布Crossで”Fatum”というリスニング~エレクトロニカ系のイベントをcocoaさん、shinnosukeohiraくん、shiranaihanaさん、necochangさん、吉村晶さん、私というメンバーで開催して。リスニングを軸にしつつ、もう少しイベントとして強固なものをやりたいなと思った最初のきっかけでした。
https://www.instagram.com/p/C0KAWvUhGY3/
──以後、複数のコンセプトで主催イベントを展開していって、それらが〈ephemeral〉に統合されていきつつ〈ほしのおと〉のchihoさんとの共催イベント〈羽化〉などに繋がっていった感じですかね。
myein:リスニングパーティーといってもシリアスすぎず、お客さんとアクトの関係が一方向的じゃないような取り組みを、もう少しショウアップした形でできないかなって思って。その過程で、自分のDJもよりコンセプチュアルなものになっていきました。心境を自分の感覚として実写化させる、みたいな感じですかね。組み合わせでひとつの世界観を作るみたいなことは、〈K/A/T/O MASSACRE〉でのDJsetなんかに現れている気がします。
解放新平(melting bot / Local World / WWWβ):初回の〈ephemeral〉、あまり長居できなかったんですけど僕も行きました。率直に言えば、いわゆるリスニングパーティーのなかでも世界観が一番確立されてるパーティーだなと思って。プロモーター/ブッカーという自分の視点から見ても、いろんなものを見たなかで取捨選択してるっていうのがわかるというか。キュレーションの意義、キュレーターとしての姿勢のようなものを感じましたね。
──個々のアーティストの表現のパワーに頼るのではなく、それをまとめて立ち上がる世界観を出現させるような取り組みを形にできてる人はそう多くないと思いますし。〈ephemeral〉自体も各回が明確なコンセプトのもと独立していて、本当の意味でシリーズになっているというか、企画それ自体が独立しつつも連作のようになっている印象を受けます。
京:それで言うと、〈ephemeral〉の第二回(series ii “Crevasse”)は雪国を軸に組んでくれたイベントで。あれも良かったな。そもそも、俺が前から調布Crossで起きてることに結構食らってて、まだ仲良くなる前のmyeinに「(1stの)リリースパーティーに出てくれませんか?」みたいなコンタクトを取ったのがはじまりだったんですよね。
https://www.instagram.com/p/C9MyAjBSDQt/
myein:そう、「なんか知らない人から連絡来たな」って思って(笑)。
京:DJをブッキングする、ということ自体がまったく初めてのことだったし、ライブハウスの転換DJ文化とかを考えると「転換をお願いするのって冒涜的なことなんじゃないか……?」とか、色々不安にも思いつつ(笑)。その後Crossに出たいな、とも思って声をかけたらああいう内容を組んでくれたりとか、そもそも『pothos』のレコーディングも調布でやってたりとか。だから、調布って土地も雪国的には重要なスポットですね。
──繁華街とか都市ではなく大自然でもない、どちらかというと郊外みたいなところの落ち着きが重要なんですね。多摩地区ってそういう意味では独特だし、多摩川をたどればtmjclubのホームである玉川上水なんかにも繋がってきますし、言うなれば「多摩Swag」みたいな感覚もあるかも? と(笑)。どちらに偏っていても生まれないような独特なムードが、雪国とephemeralに共通しているような気もします。
京:自分の住んでる場所も調布寄りで、楽しいし、近いし、終電気にしなくていいから自然とイベントだけじゃなく、バー営業の日とかにもCrossに入り浸るようになっていって。今回のリリースパーティーをこういう形にするのは最初から決めてたんですけど、DJ陣を加えるならどうしよう、という相談事なんかもCrossでしていくうちに、いっそmyeinと〈ephemeral〉に託しちゃってもいいんじゃないかな? っていう感じになって。
──なるほど! じゃあ、ライブアクトは雪国サイドが決めていって、DJサイドを〈ephemeral〉がキュレーションする、というような役割分担があったわけですね。
myein:完全に分かれつつも、話し合いのなかでavissiniyon(uami+君島大空)の名前が挙がったりとか。
京:uamiさんにお声がけすることは決まってて、それならavissiniyonもよくない?みたいな。俺もavissiniyonのワンマンを観に行ったりしてたから、それだ!と思って追加出演者という形で呼ばせてもらいました。
──こういうバンド発信のもので、アッパー的でないムードのイベントって先例もそう多くないような気がします。とくにある程度の規模感のものでは、No BusesとCwondoさんが手掛ける〈I’m With You〉ぐらいしかなかったんじゃないかなと。雪国を知ってる人はもちろん、雪国のことを知らない人も気になるイベントになっていると思いますね。そういう点にもキュレーションの妙を感じますが、個々の出演者にはどういうふうに声をかけていったんでしょうか?
京:まず宇宙ネコ子さんは、バンド自体の由来というかルーツになっているアーティストで。だから真っ先に、絶対に必要だから誘おうと思ってお声がけしました。そこから考えていって順当にいくと、ほかの近しいバンドに声をかけていくのがバンドシーン的な動き方でいえば自然なんですけど、今回表現したいアンビエンスの感覚や、いまの新しい流れみたいなものを考えるとそうじゃないな、と思って。だからiVyやavissiniyonの存在は欠かせなかったというか。
──同じ価値観を共有できるような人が、やっぱり仲間にいてほしいなっていう気持ちもあって。
京:それもそうだし、俺たちのいまのムードに連なるものの根底としてやっぱりuamiさんのようなアーティストの繊細な表現は欠かせなくて。君島さんの表現も、俺たちがルーツとしてるロック的な感覚が強くあるし。
myein:uamiさんはなんというか、こういう営みをやる上で一番必要になる最後の1ピースみたいな感覚ですね。私も出させてもらった、illequalさん・サ柄直生さんの〈eura〉が主催したFORESTLIMITでの〈えん〉でもそういう感覚をすごく感じて。そもそも私自身もファンだし、1回目の〈Spring Ephemeral〉にも出てもらってますし。
https://www.instagram.com/forestlimit_info/p/C_fOGhmS953/
https://www.instagram.com/p/C4ILlG3yxwj/
──DJ陣を〈ephemeral〉としてキュレーションして集まったnano odorine(ナノ・オドリネ)、Ole Lukøje(オーレ・ルゲイエ)、~離(ユーリ)、Tomo Takashimaといった面々についてはどういう感覚で声をかけていったんでしょうか。
myein:Ole Lukøjeさんたちにもuamiさんと同じく第一回目に出てもらって。
──なるほど。〈ephemeral〉のコアの部分というか。
myein:だし、いろんな催しで一緒になってコミュニケーションを取っていくなかで、今回の美学みたいなものに共鳴してもらえそうだなと思って。
──個人的にはTomo Takashimaくんという、他のアクトよりさらにディープなクラブシーンで活躍しているクラシック〜エクスペリメンタルのヴァイナル・セレクターを、今回のような催しにブッキングすることにも意外性と納得の両方があって感銘を受けたんですが、彼との縁も結構深いんでしょうか。
myein:2,3回ぐらい共演させてもらったなかでアプローチへの共感もありましたし、Ole Lukøjeと同じくクラシックのような音楽が軸にあるってところも共通項だなあと。
京:nano odorineさんについては、唯一自分が思いついたアクトで。DJを観たりするなかでこの人以外に選択肢はないな、と思って。その延長線上としての選択肢をmyeinに委ねた感じですね。
解放:電子音楽的に見ると、いわゆるハイパーみたいなヒップホップやクラブ軸のものがダンスミュージック的に出てきた流れが一段落ついたなか、ムードとしてのアンビエンスっていうのをすごい突き詰めて紐解いていくと、ある種究極のリスニング形態であるクラシックやジャズのような、「伝統」みたいな硬さが自然と求められるようになりつつあるのかな、と。
──ちょっと議論を生みそうな話なのでなんとも言えませんが、いまってオルタナティブなものが飽和してきてて、オーソドックスなものにオルタナティブ性が宿るって逆転現象が起きはじめてますよね。いわば「オルタナティブに対するオルタナティブ」というか。そうなると大樹みたいな、年輪をいくつも重ねたような音楽の凄まじさが新鮮みを伴って伝わってくる。さらに言えば「そうした物事を新しい感覚で咀嚼していく」というのも今後重要な要素になるような気がするんですが、今回その役割を背負っているのが〜離くんなのかなと。
京:〜離さんはしっかり雪国を聴いていただいているようなこともツイッターとかで言及されてましたし、そもそも一回一回のDJや作品を通した表現の深度とかも圧倒的で、ちょっとヤバいなと。
myein:2回目の〈ephemeral〉(series ii “Crevasse”)をやったときに、抽象さんというアーティストをお呼びしたんですけど、その人も〜離さんのレーベル〈i75xsc3e〉からリリースをされてて、uamiさんも同じく〈i75xsc3e〉からのリリースがあったりして。雪国と抽象さんを呼ぼう、と思ったのも〜離さんのTwitterに並びでコメントが出てたのを見て「いいな」と思ったのがきっかけだったので(笑)。

──今回のDJ陣になにか共通点があるとすれば、とにかくすごいディープ・リスナーの5人って感じですよね。どの人もトレンドやムードとは別のところで音楽をすごく能動的に聴く人で、しかもクラシックな面を熟知した上でそうした音楽をフレッシュにかけてる人もいて。クラブによく行く自分のような層からしたら、極論DJだけを観にいってもいいな、と思うような取り合わせにすら感じてて、それもすごく魅力的だなと。
京:今回の裏テーマじゃないですけど、ライブイベントってどうしてもライブアクトに注目度が偏りがちじゃないですか。そこの壁をなくせないかな? とも思ってて。だから理想はライブフロアとラウンジフロアの人口密度が同じぐらいになることですね(笑)。
──行き来もしつつ、いずれかのフロアから離れられなくなるような体験ができると、ずっと記憶にも残るし。デコレーションを担当するSHIBERIAさんとyarilaさんはどういう方々なんでしょうか。
myein:SHIBERIAさんはバンドをやりつつ雑貨屋さんもやられてる方なんですけど、以前私が遊びに行った〈魑魅魍魎〉という新宿SPACEのネオ・ゴスみたいなパーティーでも装飾を担当されてて。その後〈ephemeral〉にも来ていただいたりするなかで、ずっと一緒にやりましょうと話をしてて、今回やっと実現できたような感じですね。yarilaはOle Lukøjeのメンバーの美波(sugar meiha)さんがやられているドールのプロジェクトで、雰囲気的にもピッタリだな、と思ってお願いしました。デコレーションの質感については、一応イメージボードはお渡ししつつ基本的には自由にやってくださいとお願いしてます。
https://www.instagram.com/shiberiantiques/
https://www.instagram.com/yarila.doll/
──先ほど「心境や世界観を実写化する」ようなイメージでDJをしているとも言っていたように、ほぼ脚本家や映画監督みたいな感じでキュレーションに取り組んでるんですね。コンセプチュアルな表現をするにあたって、突き詰めて考えつつもその人の表現や世界観を信頼して託す、というようなバランス感もあるなと。
myein:それこそ松島さんとmewetaくんの”nuzzle”もそういう感じでしたよね。アンビエントとエレクトロニカの有機的な感じに、ダンスミュージック軸なんだけど違う方向を向いてアプローチしている感覚がありましたし。コンセプチュアルだけど、そこに則った上で自由があるみたいな。
京:俺たちのバンド名もまさにだし、北欧的なフォークトロニカ~ポストロックにも影響を受けてきたし、っていうので、1,2月のこの時期に作品を出して、コンセプチュアルなリリースパーティーをやるという一連の流れ自体になにかを感じてほしい、みたいな気持ちもありますね。
──たとえばファッション的なトレンドでいうと”フェアリーグランジ”や”フェアリーコア”というタグがあったりするし、全体的にそういうファンタジックな美学への目線みたいな、言語化されてない価値観がたぶんいろんな人の共通項としてうっすら共有されているのかな、とも思います。
myein:それはそうかも! そもそも〈ephemeral〉自体、「〇〇コアみたいなものから派生したパーティーってあるけどフェアリーコアのパーティーって無いよね?」みたいな話からはじまったパーティーでもあるので(笑)。

雪国 pre. “Lemuria” – 雪国 1st EP 『Lemuria』Release Party –
2025/02/03 MON at WWW
OPEN / START 17:30
TICKET: SOLD OUT
LIVE:
雪国
宇宙ネコ子
iVy
avissiniyon (uami x 君島大空)
DJ:
nano odorine
Ole Lukøje
Tomo Takashima
~離
myein
Decoration: SHIBERIA, yarila
Flyer Design: Karen Nakahara
Curation Support: ephemeral

雪国 – Lemuria
Release date: January 15 2025
https://friendship.lnk.to/Lemuria_ykq2
Tracklist
01.Blue Train
02.時間
03.レムリア
04.金星
05.架空の君へ
Credit:
All Music/Lyrics: 京 英一
Arrange: 雪国
Recording/Mixing/Mastering: Kensei Ogata
Artwork: Yuto Odagiri
category:FEATURE
tags:雪国
RELATED
-
2025/03/04
東京という箱庭で生きる音楽の記録|雪国がツーマンシリーズ “Hakoniwa”を開催
sidenerdsとSleepinsideを招いて2週連続開催 東京を中心に活動するインディーロックバンド・雪国が、5月に主催ツーマン企画”Hakoniwa”の開催を発表。 5月12日(月)に下北沢ERA、5月20日(火)に下北沢近松にて2週連続開催。ゲストアクトにsidenerdsとSleepinsideを招き、黎明期より活動してきた下北沢に回帰したツーマンライブを開催する。 過去に数多くの新しい居場所を探るようなイベントを組んできた雪国が、東京という大きな箱庭で同じ時代に生きる人々が鳴らした音楽をアーカイブし、ひとつの区切りつけるような内容となっている、とのこと。チケットは3/4 20:00より先着順で販売開始。 “Hakoniwa vol,1” 2025.5.12(月) at 下北沢ERA Open/Start 18:30/19:00 Adv/Door ¥3,000/¥3,500(+1D ¥600) U20 ¥2,000 Ticket : https://t.livepocket.jp/t/hakoniwa_fes -act- 雪国 Sidenerds “Hakoniwa vol,2” 2025.5.20(火) at 下北沢近道 Open/Start 18:30/19:00 Adv/Door ¥3,000/¥3,500(+1D ¥600) U20 ¥2,000 (+1D ¥600) Ticket : https://t.livepocket.jp/t/hakoniwa_fes -act- 雪国 Sleepinside Flyer illustration by Masataka Osawa Flyer edit by eiichi kyo Curation by 雪国
-
2025/11/05
雪国が2ndアルバム『shion』から「ひぐらしの夢」のMVを公開
失われたものと、まだ言葉にならないものの間 東京を拠点に活動する3人組インディーロックバンド・雪国が11月5日に2ndアルバム『shion』をリリースした。アルバムより「ひぐらしの夢」MVを公開。 失われたものと、まだ言葉にならないもののあいだに漂うように紡がれた全12曲。寄せては返す波のように揺れるループするアンサンブルと、透明でありながら確かな重みを持った言葉が重なり、時間や場所の感覚を曖昧にしていく。そこには「どこにもないのに確かに在る」景色が広がり、ひとりひとりの記憶や感情と呼応しながら、新しい物語を描き出していく。 アルバムのリリースを記念して11月7日(金)には代官山UNITを中心とした3会場での往来型リリースパーティを開催。チケットが一般発売中。 雪国 – shion Release Date : November 5, 2025 Label : Pothos Records / Perfect Music Stream : https://linkco.re/UmXbphFt CD : https://tower.jp/item/7034994 Tracklist 01 白色矮星 02 君の街まで 03 セスナ 04 生きる地図 05 秘密基地 06 羽化 07 ひぐらしの夢 08 窓辺のノア 09 海月 10 星になる話 11 シオン 12 ほしのおと 雪国 pre. “shion” 雪国2nd album『shion』Release Party 日程 : 2025年11月7日(金) 会場 : 代官山UNIT / SALOON / B1FLAT (同建物内三会場往来イベント) 時間 : OPEN 18:00 / START 18:30 料金 : 前売 ¥4,500(税込 / ドリンク別)
-
2025/09/16
失われたものと、まだ言葉にならないもの|雪国が2ndアルバム『shion』を発表
Release Party 11/7 UNIT / SALOON / B1FLAT 東京を拠点に活動するバンド・雪国が、2ndアルバム『shion』を2025年11月5日(水)にリリース。あわせて、アルバムのリリースを記念して11月7日(金)に代官山UNIT / SALOON / B1FLATの3会場にて往来型のリリースパーティーを開催。 雪国は2023年結成のスリーピースバンド。結成わずか2年で1stアルバム『pothos』がCDショップ大賞の関東ブロック賞を受賞し、2025年にはFUJI ROCK FESTIVAL ’25「ROOKIE A GO-GO」ステージへの出演、中国ツアーでは3日間で延べ1000人を動員するなど急速に存在感を示してきた。 本作『shion』には、失われたものと、まだ言葉にならないもののあいだを漂うように紡がれた全12曲を収録。寄せては返す波のように揺れるアンサンブルと、透明でありながら重みを持った言葉が重なり、聴く者の内面に静かに浸透していくアルバムとなっている、とのこと。 なお、11月7日(金)開催のリリースパーティーのチケットは9月16日(火)22:00より発売開始。雪国と共にシーンを盛り上げるアーティストが集う。 雪国 – shion Release Date : November 5, 2025 Label : Pothos Records / Perfect Music Format : Digital / CD (YKQ2-0003) Price : ¥3,300(税込) [¥3,000+税] Pre-Order : https://tower.jp/item/7034994 Tracklist : 01 白色矮星 02 君の街まで 03 セスナ 04 生きる地図 05 秘密基地 06 羽化 07 ひぐらしの夢 08 窓辺のノア 09 海月 10 星になる話 11 シオン 12 ほしのおと 雪国 pre. “shion”
FEATURE
- 2026/02/02
-

-
渋谷から新木場廃倉庫レイヴへ|「AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding)」開催
2/13(金) 渋谷から新木場へ座標を再設定
more
- 2026/01/25
-

-
渋谷の路地裏に出現する未来都市ALLEY108にて「AVYSS RAVE」開催
2月14日(土) 渋谷センター街の路地をジャック
more
- 2026/01/19
-

-
私の正直な感情について|daine interview
1/23 AVYSS Circleにて来日 more