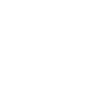12才のYouTubeキッズは夢を追いかける|Equipmentが新曲「Minnow」のMV公開
2023/09/19
混乱と冷静の間のエモ第5波

12才の少年は夢を追いかける。オハイオ・トレド拠点Nick Zander率いるバンド、5th wave emoグループ?Equipmentが近日リリース予定のアルバム『Alt. Account』からシングル「Minnow」をリリース。
「このコーラスは全知全能の語り手の視点から、私の人生の現状を分析している。この曲は、一生のうちに様々な自分になれることを語り、無邪気なレトロゲームチャンネルを立ち上げてから、10年も経たないうちに “パーティー “文化の犠牲になってしまうまでの道のりを描いている。YouTubeキッズはもっとクールだった。」
『Alt. Account』では様々な場面で、12歳のNick Zanderが、精神衛生上の混乱と冷静沈着なカオスの間を常に行き来する。『Alt. Account』で、SEGAのジェネシス(メガドライブ)やLEGOのストップモーションについて話しているのを聞くことができる。これらは、このプラットフォームが本格的に普及する前の2008年に彼が始めた幼少期のYouTubeゲームチャンネルからのサンプルであり、『Alt. Account』が真正面から受け入れているコンセプトである。
アルバム制作中、Nick Zanderは双極性障害II型と診断された。彼の最初の薬はアルバムのアートワークに描かれている。この薬が彼に与えた不眠が、このアルバムの創作に繋がった。Nick Zanderは、完成したアルバムは診断による不安定さを手なずけることができたという事実を祝うものであり、自分自身のパターンを見つけ出そうとしている人たちへの希望の表れだと考えている。

Equipment – Alt. Account
Label : klepto phase
Release date : Sep 29 2023
Pre-order : https://kleptophase.com/collections/equipment
Tracklist
1. Hot, Young Doctors
2. LO/FO
3. Hollister Henleys
4. Bad Bets
5. Jewelry
6. Minnow
7. Username
8. Your Clothes Without You in Them
9. Perfect Temperature Coffee
category:NEWS
tags:Equipment
RELATED
-
2025/06/12
都市生活における美しさと痛み|Equipmentが新曲「espresso lemonade」をリリース
過ぎた時間への未練、かすかなユーモアと哀愁 オハイオ・トレド拠点に活動するエモバンドEquipmentが新曲「espresso lemonade」を〈Brain Synthesizer〉よりリリース。 生活のディテールと人間関係の現実感を丁寧に表現する今作は、若者の都市生活、恋愛の終わり、現実との妥協、情熱の喪失、過ぎた時間への未練、かすかなユーモアと哀愁を自嘲的で愛おしい視点で描いている。 Equipment – espresso lemonade Label : Brain Synthesizer Release date : June 10 2025 Stream : https://orcd.co/espressolemonade
-
2020/04/23
DEATHRO、新曲第2弾「ILLUSION…追いかけて」を緊急配信
本日リリース DEATHROが先週の「闇を切り裂く」に続き、新曲第2弾「ILLUSION…追いかけて」を自身のYoutube Channnelにて公開&配信サイトOTOTOY、Spotify、Apple Musicにてデジタルリリース。 この楽曲の配信サイトOTOTOYでの売り上げは全額”Save Our Place”プロジェクトの一環として、2020/5/9にワンマン公演開催を予定している名古屋のLIVE HOUSE・今池HUCK FINNへ寄付される。 ————————– Emergency Release #2 from Kanagawa KEN-O… 4/16に配信開始した『闇を切り裂く』に引き続き、本来であれば2020年5月に開催される東名阪ワンマンツアー『MAXXXIMUM MATRIXXX FINAL』に標準を合わせて、バンド演奏でレコーディング&リリースを予定していた楽曲がすべてDEATHRO本人によるプログラミング&演奏で急遽レコーディング&リリース。総てが幻想と化す現状の中でも、それを追い求め、更に新しいモノを産み出す意志へと捧げる。 https://youtu.be/u0oKdIwAgiw DEATHRO – “ILLUSION…追いかけて” Royal Shadow / RS-19 Digital Single on OTOTOY https://ototoy.jp/_/default/p/534661 Programming,Bass,Guitar,Vocal:DEATHRO Recording&Mixing Engineer:荒金康佑 Mastering Engineer:中村宗一郎(Peace Music) Cover Design:井上貴裕 Cover Illust:TOMONARI (チーターズマニア)
-
2022/07/08
終わらない夏を、ザッピングで追いかけて|野崎りこん interview
本当の意味でのインターネット・ラップミュージック ネットラップを経由して孤高の表現を続ける野崎りこんが、”終わらない夏”をテーマに3年ぶりとなる新作『We Are Alive EP』をリリースした。パンデミック以降、際限なく加速し続ける消費サイクルの濁流を横目に、自身のペースを崩さず虎視眈々と積み上げたコンセプチュアルなEP。その背景にあったもの、葛藤と実験、ゼロ年代への憧憬、新たな境地に達したセカイ、そして未来についてをWebの異端児が語る。 text:NordOst ――『We Are Alive EP』リリースおめでとうございます。3年という長い期間を経て、どのようにEPを作り上げていったのでしょうか? 野崎りこん(以下、野崎):本来、時間をかけるつもりは無かったんですが、コンセプトが固まりきらなくて。楽曲のアイデアやストックは多数あっても、それらがまとまった全体像が見えてこなかったので、一旦仕切り直しをしたんです。 ――楽曲という点が、1本の線へと繋がっていかなかった、といったイメージでしょうか。 野崎:バラバラだったものを、ゼロから方向性を再考したり、組み直したり。その過程で、いくつかの曲に”夏”という共通項が浮かび上がっていったので、そのイメージをもとに1本の作品として作り上げていった感じですね。 ――『「プールに金魚を放して一緒に泳げば楽しいと思った。」 feat. 加奈子』は2012年に起こった”中学生金魚事件”が着想源になっていると思われます。その事件をもとに作られた『そうして私たちはプールに金魚を、』という短編映画もあり。 野崎:そうですね。EPの収録曲の中では一番古いもので、このあたりのエッセンスを叩き台として作品全体の方向性が固まっていったような感じです。ちなみに、全体的なコンセプトはタイトル通りで、つまりは「僕らはみんな生きている」ってことなんですよね。制作中にコロナ禍に突入してしまって、その真っ只中で結果的に色々なことが変わっていく過程が反映されているような形にはなったんですけど。 ――10年代の空気感と2020年以降一変した雰囲気が同居している折衷感は、逆に今すごく新鮮に映りました。よくない言い方かもしれませんが、これまで野崎さんの軸にあった”ルサンチマン感”を残しつつも、より開かれた表現に転化しているような印象を受けて。 野崎:以前は皮肉だったり卑屈な表現が多かったんですが、この状況を受けて考え方は大きく変わりました。そういう表現は一切やめよう、と思うようになっていきました。”ふとした時に観返す映画”みたいな、もっと明るくなれる、楽しくなれるようなものを作ろう、という気持ちで。自嘲的なメッセージを意識的に排除してみた結果が『We Are Alive EP』ですね。そういうマインドは全く無くなったというわけではないんですけど、それを今、音楽で表現したくはないな、って。 ――EPの客演にはe5(Dr.Anon)、Nosgovと今まで以上にフレッシュなアーティストを迎えていますが、どういった経緯で起用されたのでしょうか。旧作でも一貫して、早期に若手をフックアップするような形で個性的な人選をされている印象です。 野崎:客演をお願いする際は基本的に「自分が今聴いているアーティストを説明したい」という意図から、その時その時のテーマや雰囲気に合わせて選出しています。若手のフックアップというよりむしろ「新しい音楽を作っている人たちと一緒にやらせてもらう」みたいな気持ちで……(笑)。一方で、「野崎りこんってこういうアーティストだよね」みたいな感じで、イメージが形式化していくことを避けるため、異なった方向性のアーティストとコラボしたいという考えもあります。あとは、自分の作品を好きでいてくれる人々に驚きを与えたり、シンプルに魅力的だと感じたアーティストをより多くの人とシェアしたいな、という気持ちが大きいです。 ――たとえば旧作に登場した「冴島さなぎ」という架空のキャラクターへ本作で具体的な肉付けがなされ、客演の一人として加わっていることも、以前からの変化のひとつなんでしょうか。彼女がどのように作品の中で生きていて欲しいと思ったのか、非常に気になっていて。 野崎:まず最初に「架空のアーティストのCMスポットが、急に挿入される」というアイデアが生まれて、そのアイデアと、以前から自分のリリックの中だけで存在していた冴島さなぎというキャラクターと結びつけたらよりキャッチーなものにできるのではないかと考えました。『We Are Alive EP』のテーマを伝えるガイドのような役割を持たせるために、スキットを表題曲にしてみたり。「50077 gecs feat. 冴島さなぎ」のリリックにも、本作のコンセプトを込めました。 ――VHSのアニメや映画をレンタルすると、昔はよくプロモーション映像が挿入されたりしていましたよね。あるいは、YouTubeに勝手にアップロードされている昔の音楽番組っぽさみたいなザッピング感があって。あえて流れを断ち切り違和感を与えるような構成が、逆説的にEP全体に強い統一感をもたらしているように感じました。 野崎:分断した流れから新たな流れを生み出すような仕掛けは意識しましたね。スキットが折り返し地点になるような感じを意識して。そこからパッと明るく開けた「50077 gecs」が入ってくる、という感じで。 ――たしかに、1~3曲目と冴島さなぎの2曲、そして後半の3曲は絶妙に異なるカラーで、8曲入のEPに3層構造のようなレイヤーを感じます。 野崎:特に意識したのが、「自分で繰り返し聴いて楽しめる作品になっているか」という点で。そういう意味では、比較的新しく出来た「ルックバックfreestyle」や「MEMORIES」は、全体のバランスを整える役割を持っていたりしますね。 ――近年、「激情から生まれるエネルギー」をそのままパッケージングしたような衝動性に溢れる作品も目立ちますが、あくまでも野崎さんは冷静なプロデューサー目線から本作を作っていた、と。 野崎:長く聴けるような作品を追求するとなると、やっぱり全体像から細部を整えていくようなやり方がフィットして。コンセプチュアルであること自体を楽しめるのが理想的で、パーツ単位から作品を組み上げるような形を意識しました。 ――EPに先立ちリリースされた「ラブ&ポップ」は単独のシングル作品として区分けされていますが、あえて収録せず独立させたのもそういった意図からなのでしょうか。先ほど「マイナスな表現を意図的に排除する」と仰っていましたが、この楽曲は以前までの野崎さんの雰囲気と、今のバイブスの中間にあるような印象を受けました。 野崎:そうです。ちょうどこの曲が分水嶺みたいな感じですね。これも本当はEPのために作った曲だったんですが、サウンドの質感がコンセプトとそぐわないように感じてしまって。ただ、リリックで伝えたいことはEPの世界観の延長線上にはありますね。だからシングルとして分離させました。EPのジャケットや曲とも繋がる「プール」というキーワードが登場したり、EPの外伝的な役割を与えました。アニメのOVA版とか、前日譚とかみたいなイメージですね(笑)。 ――新作のリファレンスについても伺いたいです。前作『Love Sweet Dream LP』からシングル「ラブ&ポップ」、そして『We Are Alive EP』へと繋がっていった3年間で、どのように音楽を聴いていましたか? 野崎:trash angelsとか、LOWPOPLTD.など、新しい表現に取り組んでいるアーティストがたくさん生まれていく流れをSoundCloudで観測していましたね。その他には、EPの質感とはちょっと逸れるんですが、ずっと好きなJPEGMAFIAの作品だったり、Travis Scott『Astro World』とかKanye West『Life Of Pablo』など。ちょっと前の作品ですが、トレンドは横目でチラ見しつつも、自分らしく好きな表現を参照してます。どれもコンセプチュアルで斬新なことが刺激的だったので、そういった表現に取り組むきっかけにはなりました。コラージュっぽい作品になったのもJPEGMAFIAや『Life Of Pablo』、『Astro World』からの影響ですね。 ――音楽以外にはどんなコンテンツがリファレンスとなっているんでしょうか?そこはかとなくセカイ系的なイメージを想起させられたりと、聴けば聴くほど面白さが浮かんでくるのが新作の良さだな、と思い。 野崎:音楽以外のリファレンスも今回は多かったですね。収録曲の中では「summer haze」あたりのリリックに顕著に出ているのですが、「イリヤの空、UFOの夏」とか「おねがいツインズ」、「シュタインズ・ゲート」、「デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!」など複数の作品を下地に、それらの要素をコラージュ的に重ねていった感じで。 ――庵野秀明が90年代にエヴァでやったような制作手法に近いものを感じますね。大量の好きなものをパーツとして並べて、それを自身の感覚で組み上げて新しいものを創り上げるような。 野崎:情報の過積載のような方法をとったのは、個々の作品を深く知らなくても、それぞれの持つイメージを並べることで見えてくる共通項が浮き彫りになるのが面白いからですね。そもそも、僕自身ひとつの作品を深堀りしたり、厳格にコンテンツと向き合ったりするというより、その作品の世界観、空気感を楽しむというタイプで。だからザッピング的な感覚があるのかも。自分が深く知らないからこそ、イメージしか知らない人にも言葉で説明しづらい質感やイメージを共有できるだろうな、と思ってます。「なんとなく」みたいな感覚って大事だと思ってて。 ――インターネット・ミーム的な価値観ですよね。野崎さんには最初期から一貫して、いわゆる特定の物事に精通したオタク像ではなく、ひたすらWeb上で雑食にトピックを吸収していくスタンスが見受けられますが、これってdiscordなどに通底する、今のネット感覚に近いところがあるというか。 野崎:インターネット・ミームの感覚は正にそうですね。TumblrとかPinterest。4chanのノリというか。制作が終わってから後追いで知ったんですが、Liminal Spaceやアネモイアといった概念も自分のやりたい表現にピッタリ当てはまっていて。存在しないノスタルジーを追いかける感覚なんでしょうか、完成後にそういったムーブメントをチェックして、「自分がWe Are Aliveでやりたかったことって、これだな」と思いましたね。 ――答えにくい質問かもしれませんが、「ネットラップ」的シーンから足を伸ばして以降の活動や、その中での葛藤・新たな発見・心境やムードの変化などはあったんでしょうか。 野崎:うーん…そうですね、ニコラップの規模感に限界を感じてしまった、というのはあるかもしれません。なので「一歩離れてやってみよう」と決めたものの…やっぱりそこがホームだったので、そこから離れたことで家なき子状態になってしまいました。自分はオタクと自称できるほどディープなオタクでもなく「インターネット人間」といった感じなので、ネットにもリアルにも居場所が無くなった感じでしたね。「どこで表現していけばいいのかな?」と一時的が悩んでたんですけど、OMSB君のフックアップや電波少女との繋がりが、僕を繋ぎ止めてくれた糸ですね。 ――同じスタンスや出自で今のようなスタイルの表現を続けていること自体、他にほとんど類を見ない感じですよね。”異端児”としばしば評されるように、孤軍奮闘を続けられているように見えます。 野崎:異端児というのも、自分から言い始めたわけじゃないので小っ恥ずかしい感じですが…(笑)。本来、日本語ラップの本流に馴染めなかったはみ出しものが集まっていたネットラップのシーンから、更にはみ出してしまったのが僕なので。ただ、自分がやっているような表現こそ、本当の意味で「インターネットのラップミュージック」なんじゃないかな?とは思っています。 ――正にそう思います「サブカル系」という言葉のニュアンスが変質していった感じと近いですよね。前作『Love Sweet Dream LP』では、やはりそういった疑問をぶつける意識があったんでしょうか。 野崎:そうですね。だからこそ、前作でネガティブな表現はやり尽くした感じもあって。暗い感情を出し切ったから、今新しいムードに前向きになれた、というのはあるかもしれないです。一回振り切れたことで、卑屈さを出さずとも自然と自分の強みや魅力が出せるな、と。今までは何もかもすべてさらけ出すような表現一辺倒だったんですけど、「何でもかんでも言っちゃうのが必ずしも良いというわけじゃないな」…と。だから「野崎りこん」は、そういう意味ではもう既に成仏してるのかもしれないですね(笑)。 ――旧作のタイトルはゲームの「LSD」の引用だったり、いわゆる「Y2K」的な物事にいち早く反応していたようにも思われます。「時代が追いついてきた」ような形になりましたが、そういったゼロ年代文化リバイバルというトレンドにはどのような感情を抱きましたか? 野崎:単純に嬉しかったですね。自分がずっと好きな時代が90年代の後半からゼロ年代にかけてだったので、それらが再評価される流れが来たのは。それに、今まで全く通じなかった作品の話がドンドン出来るようになったのも嬉しくて。どんどん好きなものをシェアできるようになりましたね。「serial experiments lain」なんかの話も、一昔前だったらまず通用しなかったですよね。もはやインターネット的カルチャーの象徴的存在になっていってるのは新鮮な感覚です。 ――ゼロ年代リバイバルとインターネットの新たな盛り上がりは、人々が内に籠るようになった2020年代ならではの流れと密接に関係していると考えているんですが、コロナ禍以降ご自身の中でどんな変化が生まれましたか? 野崎:脱・ネガティブ以外で言うと、むしろ良いインプット期間としてマイペースにゆっくり過ごせましたね。世間は目まぐるしく変わっていたかもしれないですが、自分の周りはむしろ停滞していったような印象です。ラップシーンの流れも緩やかになったので、逆に好きなことをしっかり掘り下げる時間が作れました。あと、VTuberにハマって…(笑)。 ――VTuberは新しいカルチャーですよね。僕は最初期に少し追いかけていた程度でしたが、最近サロメお嬢様(壱百満天原サロメ)にまんまとドハマりしちゃいました…。可処分時間がドンドン奪われるコンテンツでもありますよね。 野崎:お嬢様、良いですよね〜!逆に僕はVTuberのおかげでパンデミック以降の精神的ダメージを受けなかったんじゃないかなとは思ってます。最初は宝鐘マリンとか兎田ぺこらとか、ホロライブ周辺のVにハマっていたんですが、だんだんスキャンダルなどでドロドロした感じになったのがしんどくて、一回観れなくなり…。その後、月ノ美兎の過去動画を経てにじさんじ周辺をチェックするようになりましたね。周央サンゴのスペイン村のやつとか、最高でした。人によって色んな楽しみ方があると思うんですが、僕は深夜ラジオ文化っぽいなと思って見ていて。 ――なるほど。たしかに言われてみると、ゼロ年代の声優ラジオカルチャーに近い雰囲気があるように思えます。めちゃくちゃ納得しました…。 野崎:正に声優ラジオノリですよね。癒やしとして楽しめる感じがありがたいですね…。 ――あくまでもキャラクターのロールプレイとして配信をするアカウントや、「中の人」感をあえて前面に出すようなアカウントもあって、一枚岩じゃないことはニコラップ期の表現とも重なりますよね。 野崎:ホロライブがちょっと生々しさが出てしまったりはしましたけど、基本的にそういった要素をカットしてうっすらとした繋がりを与えてくれる、というのが良いですね。 ――すみません、脱線してしまいましたが…こういうコンテンツも後年”20年代カルチャー”として総括されそうな気がします。100 gecsの引用も作品に見られましたが、いわゆるhyperpop以降のムーブメントはどのように見ていますか? 野崎:エモとかオルタナティブロックが再び盛り上がっている流れには注目していますね。Apple MusicのStation機能で知らない音楽をドンドン聴いていってた中で見つけたSoccer Mommyとか、 CVN:横から失礼します。野崎さんから反応いただいたAVYSSのコンテンツの中に、「これに反応してくれるんだ」と思えるものも多くて。韓国のAsian GlowやParannoulの周辺は5th wave emoと言われているんですが、「リリィ・シュシュのすべて」にインスパイアされた作品が生まれたりと、野崎さんの世界観とも呼応するような感覚はあるんでしょうか。 野崎:新しいものを模索する中ではAVYSSのキュレーションもチェックしてます。新作の中だと「GTA’s Easter Eggs and Some Nostalgia」にはリリィ・シュシュのイメージを込めていて。これもParannoulなど、海外のアーティストの斬新な解釈に感化されてのことですね。やっぱり、ゼロ年代カルチャーを参照する人が僕以外に増えたのは嬉しいな…と。 ――hyperpopというジャンルが登場し、即座にクリシェ化してしまったように消費サイクルのスピードが際限なく加速してしまっている現状がありますが、そこに思うことは? 野崎:うーん…例えるなら「大縄跳びに入れない」って感じですね…(笑)。Hyperpop自体には共感してましたけど、自分のペースを崩さずに合流することができず。今はもう下火になってしまいましたよね…。あとは、安易に取り入れてもEPの世界観が崩れるな、と思って。消費サイクルの速さ自体には必ず面白いものが生まれるので肯定的には捉えていますが、自分はスローペースなのでそこに引っ張られないようにしています。 ――ライブや次作の構想などは既にあるんでしょうか。 野崎:新作には以前よりハイペースに取り組むつもりです。今回のEPでは「ラップ」があまりやり切れなかったので、次はそこに照準を合わせていって、HIPHOPとしての強度が高いものを作りたいです。 ――ちなみに、今後もし共演できるとしたら、どんなアーティストに声をかけたいですか? 野崎:めちゃくちゃ理想…というか夢みたいなことを言えば、米津玄師、Mura
FEATURE
- 2026/02/16
-

-
交差する円、重なる身体|AVYSS Circle 2026 photo report
アビサー2026の記録写真 more
- 2026/02/02
-

-
渋谷から新木場廃倉庫レイヴへ|「AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding)」開催
2/13(金) 渋谷から新木場へ座標を再設定
more
- 2026/01/25
-

-
渋谷の路地裏に出現する未来都市ALLEY108にて「AVYSS RAVE」開催
2月14日(土) 渋谷センター街の路地をジャック
more