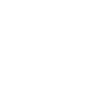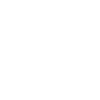nul (bringlife)とkurashigeのコラボアルバム『Coffee Challenge Baby』がリリース
2025/03/04
MVも公開
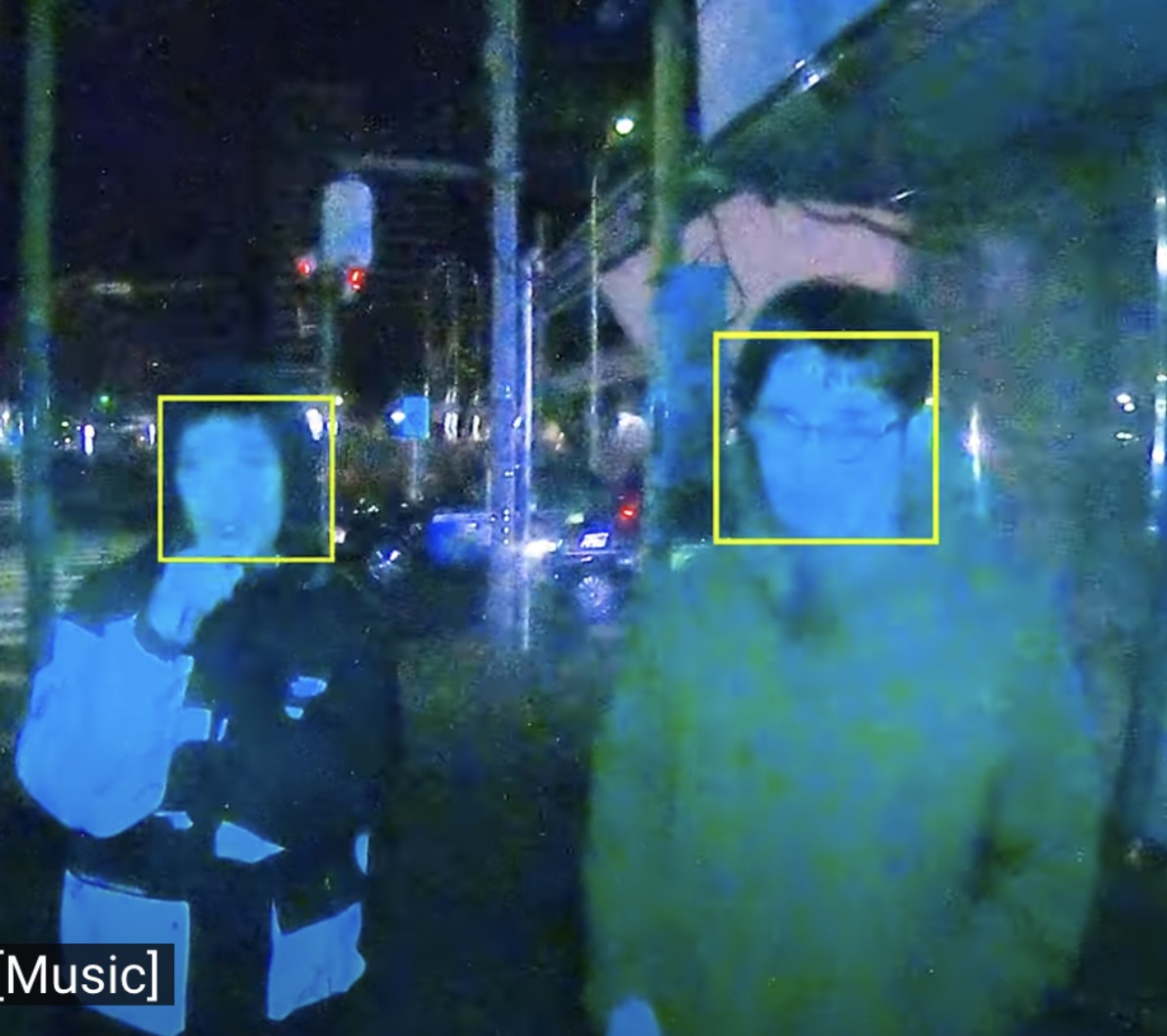
ヒップホップクルー・bringlifeとしても活動するNaked Under Leather (nul)とラッパー・kurashigeのコラボレーションアルバム『Coffee Challenge Baby』が、3月4日(火)にリリース。
アートワークはタトゥー/現代アーティストのCCHが描き下ろし、マスタリングは〈Nyege Nyege Tapes〉の諸作も手がけるDeclared SoundのDominic Clareが担当。
また、リリースにあわせて収録曲より「PS」のMVも公開。アルバムに先立って公開されていた「Baby2」に続き、どちらのMVも撮影・編集は没 a.k.a NGS (Dos Monos)が手掛けた。
nulとkurashigeの両者がそれぞれ半分ずつビートを手がける本作は、彼らがTSUTAYAで安くレンタルしてきた2010年代のロックや電子音楽と、現行のヒップホップシーンの双方の影響を感じさせる一作、とのこと。オルタナティブなヒップホップでありながら、どこか懐かしい感覚を想起させる。

nul × kurashige – Coffee Challenge Baby
Release Date : March 4, 2025
Stream : https://distrokid.com/hyperfollow/nulkurashige/coffee-challenge-baby
Tracklist
1. school
2. w2d
3. PS
4. kangae
5. watermark
6. Oishii Mizu
7. baby2
8. Fire Pattern
9. half
10. Town
1, 2, 4, 5, 7, 8 Mixed by kurashige
3, 6, 9, 10 Mixed by nul
Mastered by Dominic Clare at Declared Sound
Artwork by CCH
category:NEWS
tags:Kurashige / Naked Under Leather
RELATED
-
2023/09/28
没 a.k.a NGSとNaked Under Leatherのコラボアルバム『Revolver』がリリース
「final cut」のMV公開 東京のヒップホップトリオ・Dos Monosのラッパーであり、MVディレクターとしても活動する没 a.k.a NGSと、神奈川県は大船を拠点とするヒップホップクルー・bringlifeのプロデューサー兼ラッパーのNaked Under Leatherによるコラボアルバム『Revolver』がリリース。アルバムのラストを飾る「final cut」のMV公開。 客演を迎えず、ラッパーとトラックメイカーを兼任する没 a.k.a NGSとNaked Under Leatherが各々収録曲の約半分ずつをプロデュースしている本作では、生粋のヒップホップ愛好家である2人が、独自の好奇心と実験精神を爆発。エクスペリメンタルなビートとラップでありながら、現行のヒップホップシーンとの同期も感じさせる。カバーイラストは雨霧うみが描き下ろした。 Naked Under Leather, 没 a.k.a NGS – Revolver Release date : Sep 28 2023 Stream : https://distrokid.com/hyperfollow/nakedunderleatherbotsuakangs/revolver 1. summer Produced by Naked Under Leather 2. mariah carey Produced by 没 aka NGS 3. shhh Produced by 没 aka NGS 4. onzon Produced by Naked Under Leather 5. naitemoiiyo Produced by Naked Under Leather 6. all x Produced by
-
2023/11/26
ラフさの美学と同時代性|没 a.k.a NGS & Naked Under Leather interview
「正当なヒップホップ」のアルバム Dos Monosのメンバーであり、ラッパー/トラックメイカー/ビデオグラファ―として活動する没 a.k.a NGS(以下、没)と、神奈川県大船を拠点に独自に進化したクラウドラップを展開するクルー・bringlifeのラッパー/トラックメイカーであるNaked Under Leather(以下、nul)によるアルバム『Revolver』が9月28日にリリースされた。 『Revolver』はアンダーグラウンド・ヒップホップを彷彿とさせる「summer」で幕を開けたかと思えば、ナイトコアといったインターネット音楽を思わせる大胆なピッチ変調、IDMのような電子音、ノイズ、有機的なカットアップ、スラッカー・ロック風の楽曲など、ユニーク且つ多彩なアプローチが詰め込まれた作品だ。 これらの要素は(少なくとも国内では)主流ではなく、本作は一見“本流”とは異なる実験的な作品であるように感じられる。しかし『Revolver』は、ただ本作を「エクスペリメンタルヒップホップ」と形容するだけでは済まされない「ヒップホップ」らしさが垣間見える作品ではないだろうか。 インタビュー・構成 : Ritsuko 撮影 : niijima / ナガタダイスケ ●異形に見えて実は正統派。現行ヒップホップへの反応 ──1曲目『summer』のリリックに登場する「BLANKEY JET CITY」に「アベフトシ」という単語や、10曲目の『final cut』など、どことなくバンドの文脈を感じさせる要素も目立ちます。 没:そうですね。ただ自分たちは「(突飛な手法で)カマしてやろう」という考えでバンド要素を取り入れた訳ではなくて。最近の作品でいえばLil Yachtyが『Let’s Start Here』で新しいサイケを試みてたり、Lil Uzi Vert も『Pink Tape』でロックを使ってた。だから、バンド的なことをやるのも「今のヒップホップにおいて当たり前の手法だよね」というスタンスで捉えてます。 ──なるほど。ただ、Lil Yachtyの『Let’s Start Here』などに反応した作品などは、現時点では国内ではあまり見られませんね。 没:リスナーとして反応しているのも、いわゆる“音楽オタク”のひとたちが多い気がする。ちょっと脱線するけど、Kendrick Lamarの一番新しいアルバム(『Mr. Morale & The Big Steppers』)でも、今までのヒップホップにはない技法がたくさん組み込まれているのに、割かし当たり前みたいな受容をされている感じがするんですよ。ケンドリックがやっぱりケンドリック過ぎるのとか、プロダクトとしての完成度が高すぎて自然に聞けちゃうのとか、理由は色々あると思うんだけど。そういうのは少しもったいないなと思ってます。 ──つまるところ、“バンド文脈”に限らず、ヒップホップとして繰り出される新たなアプローチも、国内ではなかなか一般化し辛い傾向を感じます。 nul:なので案外、「なんでやっている人がいないんだろう」といった“フラストレーションの塊”みたいなものが『Revolver』と言えるかもしれないです。 没:フラストレーションはめっちゃあった!振り返ると「日本で他にやるやつがいないなら俺らで先にやっといたほうが良いんじゃないか?」という考えは、アルバムを作り始めたきっかけの一つですね。 ──仮想敵にするわけではないですが、聴きなじみのない方にとっては『Revolver』を「Dos Monosの亜種」のように捉える方もいると思うんです。 nul:「エクスペリメンタルヒップホップのひとつ」のような。 ──でも、今お話をして頂いたように、『Revolver』はかなり現行のヒップホップを踏まえた作品であると。 nul:そう。『Revolver』では普通に現行のヒップホップへのリアクションをしたつもりであって、そういった意味では同時代性のある作品だと思っています。 没:Dos Monosに関しては、いわゆる「ラップ的な価値観」をあえて理解しないままヒップホップを作ることで“突然変異”のような作品を目指すグループだと思うんだよね。 ──楽器に触れたことがない人もバンドを結成し、新しい音楽のムーブメントとなった「NO WAVE」のようなスタンスなんですね。 没:そういう魅力だと思います。それを踏まえると『Revolver』は、今のヒップホップのマナーを踏まえて作っているので、真逆のスタンスかも。 nul:だから、『Revolver』は自分たちの中では純ヒップホップアルバム。 ●ストリートに流通する「実験性」と「ラフさ」の美学 ──いっぽうで、『Revolver』ではある種の「ラフさ」やDIYな質感が重んじられているように思います。昨今では「大手レーベルからリリースされるフォーマット」を意識したエンジニアリングやプロモーションを趣向するアーティストが多く感じるため、珍しいように思いました。 没:まじで「若い人たちうますぎない?」「プロダクト化する力がありすぎない?」って思います。ミキシング・マスタリングにしても凄すぎる(笑) nul:そうですね。いっぽうで、2010年代のインターネットミュージックにあったいわゆるヴァーチャルな「インターネット」感とラフな「手触り」のような感覚が両立した作風は失われているような気がしているんです。ノスタルジアかもしれませんが、その点は『Revolver』を制作する際にふたりが共有していた認識だと思います。 没:逆に今の国外のラッパーには「インターネット」と「手触り感」がある。 ──ブルックリンドリルとかでも「なんかBPM速すぎない?」みたいな作品や「ガサついたDIYなミックス」でヒットしている作品が沢山ありますよね。 没:自分が好きなニューヨークのRXK NephewとかイギリスのPretty Vは年間400曲みたいなあり得ない速度で曲をリリースしていて、結果として自然と「手触り感」が残されたまま楽曲がリリースされてるのが最高で。それがインターネット上のコミュニティや音楽オタクからではなくて、いわゆる“フッドのラッパー”から出力されている点が今を象徴してると思うし、共感する。 ──「インターネット」と「手触り感」の共存という点において、『Revolver』を聴いたときにニューヨークのクルー・Surf Gangを思い出しました。 没:Surf Gangは自分たちの作品を「post-apocalyptic rap」って言ってるんですけど、そのキーワードにマジで共感するんです。 ──技術や文明が目指す「数値的な完成度」のような指標が臨界点に達し、そこにフィジカルな有機性を介入させていくようなニュアンスを感じます。 没:まさに「インターネット」やと「手触りを感じさせるラフさ」、「プロダクションのクオリティ」と「実験性」両方の感覚が当たり前になったことを示すキーワードだと思います。 ──ひと昔前ならPC Musicだとか、アートスクール系の人たちが持っていた感覚を、現代ではストリートの人たちも持っていると。 没:そうそう。だからSurf Gangのプロデューサー・Evilgianeがアールやケンドリックにビートを提供しているのは「その感覚が当たり前になってるんだよ」ってことの表れだと思います。さっきLil Yachtyの『Let’s Start Here』の話題が出たけど、第一線級のラッパーはこの変化に自然に順応してるんだと思う。 ──その点、まさに『Revolver』はネットレーベルやインターネットを彷彿とさせる技法とDIYなラフさ、アンダーグラウンドヒップホップのような物質性と実験性が同居した作風になっていて、改めて作品の同時代性を感じます。 没:かなりファストに作ってるので良くも悪くも変なところがあるとは思いつつ、メチャクチャ普通にナウいヒップホップをやったつもりです。色んな要素が同居してるのも、ラップミュージックだからこそ可能なアプローチだとも思う。かっこいいラップを突き詰めるなら「じっくり完成度を高めるだけじゃなくて、適当にスピードだけで出すラフさも必要でしょ」っていう感覚がありますね。 nul:なので昨今のSurf GangもWu-Tang Cranも俺の中で完全に等価で、根本的な考え方は同じだと思っています。 没:俺の中でも、Playboi CartiとEarl Sweatshirtのラップのカッコよさは一緒というか、等価なものとして存在してる。 ──「クオリティ」だけじゃなく「ラフなカッコよさ」も必要であるという根本的な考え方は共通しているということですよね。 nul:ヒップホップっていう歴史を本気で体験したら、皆それぞれ形式は違っても同じ根本的なカッコよさ、Dopeさとも言い換えられるかもしれないけれど、そういうアウラみたいなものを持つことになると思うんです。90年代のNYのスタテンアイランドの空気でヒップホップをしたらWu-Tangになるし、サウスだったら例えばトラップ、現代のブルックリンだったら例えばBKドリルになる。では、日本に今住んでいる自分達が当事者性を持ってヒップホップをしたらどうなるか。現在にまで至るヒップホップの歴史に本気で自分達を溶かして、出力する。そういう考え方で俺も作品を作っていますね。 ──商業的には「盛り上がっている流行の形式」にあわせて作品を作るアーティストが多い印象です。 nul:流行のジャンルにおいても、その形式が持っている歴史的価値など、自分達が知らないリアリティがいっぱいあると思うんです。トレンドにあわせて楽曲の構造自体を取り入れることはできるかもしれないけれど、ジャンルが寓意するものを吸収するのは自分にとっては簡単じゃない。 ──つまり、ヒップホップに見出してきた根本的な価値観や考え方をとおして、自分たちなりの当事者性をもって制作した作品が『Revolver』であると。 没:ひとまず、そういったテーマの作品を1作品リリース出来たかな。 ●ルーツは2010年代インターネット/LA発のビートシーン。James Matthewからの影響 ──『Revolver』にはネットレーベル全盛期のような美意識が感じられます。そこで、ふたりがそれぞれクルーに所属する以前の活動も伺いたいです。 没:2019年にDos Monosとして世に出始めた頃に、ソロ名義でもYouTubeに曲を上げたり、ライブをやったりしはじめました。nulは渋谷の7th floorでやった俺の最初のソロライブからゲストで参加してくれてたんで、今年で4年ぐらいの付き合いです。最初にnulにコンタクトをとったのは、MCビル風さんという方が、「Dos MonosとCQ Crew(bringlifeの前身クルー)が絡んだら面白そう」ってツイートしていたのがきっかけで、そこからnulのTwitterを見つけてDMして会いました。 nul:俺は恐らく6〜7年前に音楽を作り始めました。それまでは音楽を作ってなかったのですが、友達からAblton Liveの存在を教えてもらって、作った曲をSoundCloudにアップロードし始めたのが最初。当時から自分が好きだったノイズとかアンビエントみたいな音源です。リリースした作品としてはWasabi Tapesというレーベルからリリースしたノイズ/コラージュ作品が1作品目です。その後にbringlifeの前身になるクルーのビートを作り始めました。 没:自分もヒップホップを作る前は、ひとりでノイズを作ってmyspaceとかサンクラにあげてました。当時よくチェックしていたHi-Hi-Whoopeeという音楽ブログ/メディアがあって、2013年か2014年くらいにそこで取り上げて貰ったこともあったり。 ──やはりふたりの活動初期にネットレーベル色があるんですね。 没:メッチャあります。ビートを自分で作ろうと思ったのはそのHi-Hi-Whoopeeのコンピ『Meili
-
2025/05/21
bringlife、PICNIC YOU、没 a.k.a NGSによるコラボEP『5 Star Cowboy』がリリース
表題曲のMV公開 bringlife、PICNIC YOU、没 a.k.a NGSのコラボEP『5 Star Cowboy』がにリリース、表題曲のMVも公開された。 オランダのRIP DRARIとのコラボレーションアルバムやクルー名義、メンバーnulのアルバムも話題のbringlife、17曲入りの1st album『友愛』でジャンルを超えた反響を呼ぶヒップホップユニット PICNIC YOU、ヒップホップトリオ Dos Monosでの活動のほか、ソロでの楽曲制作・MVディレクターとしても活躍する没 a.k.a NGS。 3者のコラボレーションのEPとなる本作は、没 a.k.a NGS、田嶋周造(PICNIC YOU)、bringlifeのnulと10,10,10がビートを手がけ、全員がラップする”完全内製EP”。ヒップホップのフィールドを超えて、ヒップホップの活動をする彼らの熱いぶつかり合いと暖かいシンパシーが共存するEPが完成。アートワークには出版グループ・YACIのjulian seslcoによる、5人のポートレートがあしらわれている。 アルバムに先立って公開されていた「frozewn」に続いて、本日表題曲「5 Star Cowboy」のPMも公開に。どちらも撮影・編集は、没 a.k.a NGSが担当している。 bringlife, PICNIC YOU, 没 aka NGS – 5 Star Cowboy Release date : May 21 2025 Stream : https://linkco.re/Qa50dmN6 Tracklist 1.Frozewn Produced by nul、Mixed by 田嶋周造 2.5 Star Cowboy Produced and Mixed by 田嶋周造 3.Post-Furo Produced by 10,10,10、Mixed and Add Production by nul 4.World
FEATURE
- 2025/06/18
-

-
iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」がWWWにて開催
1stアルバム『混乱するアパタイト』CD版発売決定 more
- 2025/06/05
-

-
誰でもない私になるための方法|iiso interview
最新EPから「Ash」のアコースティック版がリリース more
- 2025/05/27
-

-
もうひとりの私と出会う|nyamura『Seraphim March』レポート
Text : つやちゃん more