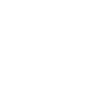アクセルを踏み抜き、サウンドデザインを超えた新境地へ|ウ山あまね interview
2023/12/12
リズムと歌に回帰するネオモードへ

衝撃的な破裂音のような、それでいてASMR的快楽性をも併せ持つ唯一無二のサウンドデザインをもって2020年代以降のシーンで脚光を浴びるウ山あまね。PAS TASTAでの活動もあわせて、近年ますますその活動ぶりに進化の予兆を感じさせる。2022年にはアルバム『ムームート』を発表するなど活発なリリースを続け、本年のソロ・リリースはシングル「Ghostyard」とリミックスワークのみに留まったが、実は水面下で爆発的な変化を続けていた。
今回、AVYSSではウ山あまねとともにクリエイター向けPCブランド〈raytrek〉を使用した10分間での音楽制作動画〈10min DTM powered by raytrek〉の収録へ参加。前作『ムームート』制作時の心境やここ最近生じた変化、そして改めて「リズムと歌」に回帰しようとする氏のネオ・モードを掘り下げる。
Test by NordOst
――10 min DTMお疲れ様でした!先ほど収録中に出てきた話の中で、「今までやったことないタイプのアプローチになったから定期的にやっていきたい」みたいな話も出てたと思うんですけど、それ以前に基本的にそのウ山さんの中でルーチンになってるような制作スタイルから伺えればと思います。
ウ山:現時点の話だと、1ヶ月ほど前にDAWをCubaseからAbleton Liveに乗り換えたばかりなんですが、そこで新しいアプローチや実験をできるのがすごく楽しくて、その延長で制作を始めることが多いですね。Abletonに移ってからは自分がタッチできる範囲がすごく広がったのが嬉しかったです。たとえばLFOをあらゆるパラメータにかけられたり、エンベロープ、シェイプアウト、モジュレーションとかいろんなパラメータをモジュレートする機能が充実してるんですが、それは他のDAWにはない機能なので、すごく新鮮に感じてます。
――ウ山さんは制作上、個々の音色を大事にされてるような印象を受けるのですが、そういう意味ではDAWの切り替えが自身のスタイルにもプラスになっているわけですね。
ウ山:そうですね。あと、海外とかではいわゆるサウンドデザインを武器に戦っている人たちは基本的にAbletonなんですよ。もちろん、全然違うDAWを使ってる人もいるんですけど。なので、ネット上のチュートリアルを即座に実践できるっていうのが自分にとっては嬉しくて。創作意欲につながるし、インプットの幅も増えますね。
――ありがとうございます。ウ山さんの遍歴や音楽体験のはじまりについては既出の記事でお話されていると思うので、今回はその後の話、主に2021年の後半から今に至るまでのことについて伺えればと。この2年間でアルバム『ムームート』のリリースやPAS TASTAのスタートなどもあり、我々聴き手としては大きな成長期、キャリアとしての転換期を迎えた時期だったと思うのですが、ウ山さんの感覚としてはどうでしたか?
ウ山:まずそういう風にご期待いただいているってことがすごくありがたいなって思いますね。ただ、本当に変わった部分がありすぎてどこから話せばいいか全然分からない、というのが本音なんですけど。一つ言えるのは、いまは曲を作るモチベーションがすごく高いってことでしょうか。それも活動一つひとつが直結してるというより、複合的な要因からそういう精神状態になっている感じで。
――それこそPAS TASTAの活動のスタート以降楽曲提供やリミックスワークなどもより活発化し始めている雰囲気も感じられます。やはりプラス要素としては大きかったんでしょうか。
ウ山:PAS TASTAでの活動は間違いなくプラスには働いていますね。なんならAbletonにしたのもPAS TASTAの活動があってのことで。(PAS TASTAとしての活動を)始めるまでは基本的に全部一人で制作をしていて、他者と共同で作業をする経験もほとんどなかったんです。自分と同じようにパソコンで曲を作る人たちと一緒に集まって、近い形でモロに影響を受けあいながら作っていくっていうのは本当に自分にとって刺激的ですし、勉強にもなっていますし。それがなかったら今はなかっただろうなとも思います。
――やっぱり切磋琢磨っていうか、お互いに高め合っていく感覚があると。
ウ山:切磋琢磨もそうですし、(制作に)自分以外の視点が設けられている状態が自分にとってすごく好ましい状況で。今までの自分の作品は全部自分でジャッジをしなきゃいけない状態だったんですけど、PAS TASTAは6人分の価値観のもとで6人分のジャッジをひとつの曲に対して下していく感じで進んでいくので、自分の仕事に対する5通りのフィードバックが得られる環境にいるんですね。採点みたいな雰囲気では全然ないんですけど。ダイレクトな反応から「こういうのはあまりウケが良くないんだな」「逆にこれはすごくウケるんだな」みたいな判断や、自分の意外な長所を発見したり、作業ごとのレベル感を把握したりすることができて。そういった部分が、自分にとっての学びに直結してますね。
――ある種のベンチマークになるような人たちが一気に周りに5人も増えた、というのはすごく大きな出来事だと思います。自分の話になってしまいますが、文章を書く仕事というのは人の手に渡って初めて分かることがたくさんあるんですね。音楽制作でもそれは同じかな、と。
ウ山:そうですね。僕はもう、その辺の感覚がとびきり弱いというか……(笑)。何でも良いところが見えてしまうし、悪いところが見えてしまうような感じで、自分の中のジャッジの仕方が分からない状態だったんですけど、5人分のサンプルを収集することで見えてきた部分があるというか。自分の中に新たな基準を設けられるきっかけになったっていうのはすごく大きいです。
――PAS TASTAを通した作業のなかで得られたフィードバックは、どういう判断で自分の仕事に還元していますか? たとえば「この感じはソロに切り出していけそうだな」とか「これはPAS TASTAに提供すべきだな」といったような。
ウ山:なんだろう?PAS TASTAでもソロでも、まだ実践で導入できていない部分が多くあるというのが正直なところなんですが、でも「どういうものが受け入れられてどういうものがナシか」っていう感覚は自分の仕事にも応用して考えています。PAS TASTAでは「ポップスと感じられるものの領域を広げる」という共通の課題があって、たとえばサウンドがちょっと荒唐無稽でもダンサブルであるとか。そういうポップスとそうじゃないものの境界を探っていくことは、今後の自分の制作にもより強く影響が現れると思います。
――今はご自身の価値基準をブラッシュアップしているような段階にあるわけですね。それで言うと、前インタビューでおっしゃってたプロデューサーとしての視点、たとえばA. G. Cookのように自分の楽曲を別のシンガーの方にも提供していけたら、みたいな話もされてたと思いますが、そういった意識には変化がありましたか? 目標や美意識みたいなものの変化でも大丈夫です。
ウ山:基本的には変わらず、そういうプロデュースワークみたいなのには憧れがあるんですけど、今はその優先順位が一段後ろに下がった感覚があります。それ以上にまず自分の聴きたいものというか、理想像みたいなものを作りたい、というのが目標であり一番の欲求ですね。それと「自分は気に入ってるけど伝わらなさそうなものをどうやったら伝えられるか」という考えもあって。そういった意識のもと、今思い描いているアイデアを改めてみんなに提出したいっていう気持ちがありますね。今だったらその結果がどうなっても全然受け入れられます。だからもう、気持ちとしてはアクセル全開で茂みの中に突っ込んでいってる感じです(笑)。茂みを越えたら岩があるかもしれないけど、「いいや岩あっても、とりあえず行けるとこまで行こう!」という。
――たとえばその中の話で言うと、過去作の中でのお気に入りってあるんでしょうか。他者の評価は置いておくとして、純粋に自分が思い入れ深い楽曲など。
ウ山:「茂みから」っていう曲があって、それは最初のEP(『Komonzo』)に収録されてるんですけど、やっぱりあれが一番自分らしいと思っていて。歌詞も本当に自分の持ってる言葉で書いてるなという感じもするし、好きなものを作ってるなっていう感じもするし。
――先ほど伺った「あえて偶発性を取り入れる」というアプローチって、おそらく現代音楽とか現代美術で言われる「チャンス・オペレーション」みたいな、かつてジョン・ケージが言っていたことに近い試みをDAWでやってるのかなって思っていまして。『Komonzo』然り『ムームート』然り、そこにはやはりウ山さんなりの美学が一貫性をもって込められているな、と。それはもちろんサウンドデザインの練り込みもあると思うんですけど、個人的には歌とリズムのところが気になっていまして。
ウ山:リズムですか?
――はい。たとえば、いわゆるクラブユースな電子音楽を作るアーティストって出自がハウスの人だったらハウシーな感じになるし、UK文脈のものに影響を受けている人だったらガラージの色が出てきたりとか、人の遍歴によって変わってくる要素が大きいと思うんですが、ウ山さん自身はバンドやポップスに出自があり、必ずしも電子音楽やクラブミュージックから出発した方じゃない、というところにまず独自性を感じていて。だからこそ、リズムの捉え方に面白さがあり、たとえば今日作られてたトラックにしてもブレイクビーツといえばブレイクビーツなんですけど、リズムのところで見るとありそうで無かった刻み方をされてる印象もあって。リズムへの意識っていうのはどのように捉えていますか?
ウ山:リズムを意識し始めたの自体は結構最近というか。『ムームート』以降、特にリズムが独特なアフロポップやアフリカの音楽、あとブラジルの音楽を改めて聴いてて、そういう意味ではリズム的なアプローチを研究してますね。
――今はその領域をも飛び出しつつあるんでしょうか。
ウ山:そうですね。『ムームート』を制作してたときは、サウンドデザインっていう部分に重きを置きすぎちゃってる時期でもあって、リズムって本当に必要かな? とすら思ってたんですよ。突出して綺麗な音色のコラージュの集合体であればいいじゃないか、みたいな。リズムって言ってしまったら制限でもあるじゃないですか。だから四つ打ちにボーカルを乗せるとかそういうのがあんまり好きじゃなかったんですよ、その頃。すごい窮屈な感じがしちゃって。「リズムがあるからサウンドデザインも自由じゃなくなるんじゃないか?」っていう疑問がずっとあったんですが、『ムームート』を作り終えて「リズムやな…音楽は」と(笑)。やっぱりポップスの出発点ってリズムなんだな、っていうのを痛感して。だから今改めてリズムを研究するというか、体に馴染ませようとしている最中なんです。『ムームート』の時期はリズムよりもメロディーの方が自分の中のヒエラルキーだと大きかったので、それに伴いリズムにおいてもメロディー的なアプローチをおそらくしていて。そのときの感じが今回作ったトラックにも出てるのかな、っていうのは自分でなんとなく感じたことですかね。
――それって、割とバンドを通過してる人の考え方というか、(音楽制作を)アンサンブルで捉えてるようなところがあるような気がします。歌メロに対応してギターのリフが出来て、そこに乗せるベースラインも自ずと出来上がっていくような。歌についてですが、僕はに初めて「Hiuchiishi」を聴いたとき、いわゆるJ-POPのメロディーラインから距離を置くことに成功していて本当に衝撃を受けたんです。とくにBUMP OF CHICKENやRADWIMPS、ASIAN KUNG-FU GENERATIONなどの登場以降、邦楽のポップスやロックはかなりそこに傾いていった体感があり、それは米津玄師のようなアーティストにも引き継がれているようにぼんやり考えてまして。
ウ山:ありがとうございます(笑)。
――そういう人ってすごく稀有なので。だからあえてリズムと歌について聞いてみた、っていうのは、『ムームート』を聴いているとおそらくサウンドデザインについては突き詰め続けた結果、ある種一度全クリしたような感覚があるんじゃないかな、と。
ウ山:それもありますし、けどリズムに進んだ目的としてはやっぱりポップスが作りたかったっていうのが大きいですね。『ムームート』は自分の中では正直、ポップスとして全員が全員聴けるものができたな、とは思ってなくて。自分の音楽にある種の大衆性みたいなものが欠けてるかも、と課題に感じた部分もあったのでビートやリズムへの理解に進んだっていうのはありますね。

――この2年ほどで歌への捉え方や意識も変わっていったんでしょうか。
ウ山:すごく変わりましたね。メロディーというか歌そのものに対して改めてフォーカスするようにはなりました。『ムームート』は「サウンドデザイン史上主義」みたいな作品で、自分の声に対してあまり特別な感情を持ってなかったんですけども、作品を聴いた感想で「声がすごく特徴的で面白い」っていう風なことを言われて、自分の作品を自分たらしめてるものってやっぱり絶対に自分の声だな、と思うようになりました。
――つまり、歌こそ自分しか持ってない本当のシグネチャーサウンドだった、という。
ウ山:そうなんですよ! なので「これ」をやっぱ使いたいな、っていうのが強くて。繰り返しになるんですけど、本当に「ポップスが作りたい」っていうのが自分の中でより大きくなってるので、そうなると自分の癖のようなメロディーをやり続けるのもいいんだけど、それだと自分の引き出しを増やせないな、と思いまして。
――手癖から脱却するのではなく、手癖になっているフィールドを拡張していきたいということですね。
ウ山:そうですね。ちゃんといいメロディーを狙って書けるようにしたいし、感覚じゃなくてちゃんと自分の中で理論化したいっていう思いが最近はあって。それで言えば、先ほど米津さんやBUMP OF CHICKEN、アジカンから脱却していることに成功しているってお褒めの言葉をいただいたんですけども、逆に僕は今そっち側を結構研究してて。
――なるほど! では逆に、近しい人だといかがでしょうか。先日ちょうど延期になっていた「ウ山あまね × MON/KU × honninman」というスリーマンも行われましたが。
ウ山:三者三様で素晴らしかったんですが、個人的には特にMON/KUさんのライブアクトとしての3年間での進化がすごくて。自分がやっても同じようにはならないなっていうところがまずあったし、そもそもMON/KUってめちゃくちゃ歌がうまくて。かといって割と自身は自分の歌には頓着があまりなさそうなっていうバランス感とか、自分がライブで達成したいものでもあったので、それがすごい悔しかったっていうのもあり。もう嫉妬で素直に聞けなかったですね、メラメラと(笑)。
――そのハングリーさみたいなものは、今までなかったような感情だったりしますか?
ウ山:うーん、嫉妬はずっと持ってた、というかすごく強い方だったんですよ。なんならもう、それが自分にとって一番のエネルギーだなと感じてた時期すらあって。それが強すぎて元気が無くなっちゃった時期もあって、『ムームート』の制作中は特にそうでした。
――やっぱり大変でしたか。
ウ山:いやー……すごい大変でした。やっぱ自分が制作するもの、いいものを納得のいくまでやり続けるみたいなことをやってたので、今考えたら病院で相談した方が良かったんだろうなっていうような感じでした。だから作り終えた時って本当にボロボロだったんですよ。で、もはやそのときは嫉妬する元気もなかったというか。すごい人が現れたとしても「ああ、また俺のやることがなくなるわ」みたいな。敗北感とか空しさみたいな。
――ゲームで言うとコントローラーを投げるような感じっていうか。
ウ山:「もうどんどん痛ぶってください」みたいな(笑)。そういう状況だったんですけども、ようやく最近そこから楽しいことが見つかって、嫉妬する元気も出てきたというか。負けないぞっていう気持ちも出てきたし、また身体壊すからわざわざ嫉妬しないようにしとこうっていう風にも考えるようになりましたね。とはいえ、完全に傷が癒えることってないんだなっていうのもすごくひしひしと感じています。やっぱりダメージを受けてた自分も、まだ自分の中にいるんですよ。超回復、起こってほしいんですけど。
――起こると思いますよ。今こうして話せているっていう時点で相当だと思うんです。たとえば1年前にインタビューしてこういう話になったら、結構厳しかったのでは。
ウ山:そうですね。もう絶対こんなことは言えなかったですね。もっと投げやりな感じのことを言ってたと思います。
――今年リリースした「Ghostyard」ってシングルには、立ち直って以降の「次の予兆」みたいな雰囲気をちょっと感じたんですが、あれはいつ頃作られたんですか?
ウ山:あれは『ムームート』を出し終わってライブが決まる前ぐらいから作り始めてて。疲弊してた時期にリハビリのつもりで作ったというか、自分に対して『ムームート』で設けていた制限を一つ取っ払おうという意識で作ったものなんですけども。
――それはどういう制限でしょうか。
ウ山:制作中、自分の周りの友人や尊敬するミュージシャンのみんなから「こんなもんか」って思われるのが怖くて。ちょっと自意識が過剰気味だったんですね。全然当時は意識してなかったんですけども、そういう他者の視線みたいなのがやはり自分の中ですごく束縛になってたんです。その視点をまず取っ払おうという意識で作ってはいましたね。
――たしかに、ある種ムームートの後日感的にも伝えられるシングルではあったように思えます。完全に「ウ山あまねの曲」としてもう自立していて、歌やメロディラインに新しい普遍性みたいなのが生まれつつあるのかなと。
ウ山:歌詞も『ムームート』を作ってたころだったらこんな書き方絶対できなかった、みたいな作り方をしてたり。
――それは最後のほうの、ギターをパワーコードで鳴らすっていうアプローチもですか? ここまで音像にこだわりのある人がバンッってパワーコードを打ち出すというところにもモードの変化を強く感じました。
ウ山:そうです。だからもう、あれはそういう意味では諦めて作っているというか。それこそ岩にぶつかっちゃってもいいや、という気持ちの発露ですね。
――以降、今年ですとリミックスワークがいくつか出ていますが、いずれも自由に解き放たれた状態のように聴こえてきます。提供先のチョイスもすごく面白くて、ウ山さんならではな感じです。
ウ山:ありがとうございます。たとえばバスクのスポーツですが、これに関してはもう本当にずっと好きで。本格的に音楽活動を始めたころぐらいに一回一緒(のライブ)になっても、そこからもうずっと一緒にやりたいって思ってたんで、熱意が結実したようなものになってますね。クリエイティブもすごくかっこいいんですよね、バスクのスポーツは。作るものに対する姿勢とか、できたものへの愛着がすごく伝わってくるし。なんというか、『ムームート』は疲弊しながら出した作品だったんで、正直トラウマ的な作品にもなってしまっているというか。でも、得てしてその人の限界の状態で作られた作品って結構みんな好きになってくれるもので、それがきっかけになって今いろんなものが集約してきてる感じがあるので、今年はそういうものが結実する年だったなと感じましたね。

――じゃあ、今のムードとしては羽ばたく寸前で、羽休めじゃないですけどある種自分の好きなことに立ち返る時期でもあるというか。
ウ山:まさしくそうですね。立ち返っている段階だし、一度「温泉でも浸かろうよ」というか、焦らず行こう、力みすぎてたな、と(笑)。自分は間違いなく音楽が好きだし、ある程度好きにやって自分らしい作品になるっていう自信もあることに気づいたというか。できないことも当然あるんですが、そういうものはきっぱり諦めつつ俺は俺にできることを、というかやりたいものをやるしかないんだ、という本当に気持ちいい諦念で今進んでて。となると、いろんなことを無理やりやってもしょうがないわ、っていう気持ちでいます。
――最高の状態じゃないですか! たぶんそろそろ最後の質問になっていくんですけど、おそらくこれから心身ともに新しい環境で今までと全く違うスタイルでの制作が始まりつつ、改めて歌やリズムに立ち返るような制作スタイルにもなっていく中で、具体的ではなく ぼんやりとしたビジョンで大丈夫なんですが、今後こういう表現に挑戦していきたい、こういうスタイルでいたい、みたいな展望みたいなのってありますか? 観念的なことでも大丈夫です。
ウ山:なんだろうな。とりあえず、今は「サウンドデザインもういいかな」みたいな感じにはなってて。もちろん好きだから全然続けるけど、今までみたいにサウンドデザインが一番上にあるみたいなのはもはや意識してないというか、そういうものから離れたものを作りたいですね。それ(特有の音像)を期待されているな、っていうプレッシャーがずっとあったんですけど、でも別に俺ってそれだけじゃないよな、みたいな。サウンドデザインが面白い音楽がたまたま好きだった時期に作った作品が広く聴かれるようになっただけで、それまではアフリカの音楽やブラジルの音楽が好きだったり、テクノが好きだったり、ロックが好きだったりと、本当にいろんなやりたいことがあるんですよ。なので、最初の話に戻るとそれを今のこの状態で提出して「さぁどうだ?」って言いたいっていうのがあって。今までの質感を好きでいてくれてた人の期待を裏切ることになるかもしれないんですけども、それもちょっと楽しみな気もしてて。変わっていくことに対してすごくポジティブというか、そこには「これでダメだったらもうダメだ」っていう清々しい諦めがあるんです。なので、とりあえず作品をたくさん作りたいっていうモチベーションではあります。まとまった作品にできたらなって思うんですけども。
――それがどうなるかっていうのは今後もお楽しみに! ということですね(笑)。
ウ山:そうですそうです(笑)。ただ、期待を裏切らない部分もありつつ裏切る部分もありつつやっていきたいなっていうバランス感はあるかな。
――でも、もう今期待してる人も裏切られようが「ウ山あまねのサウンド=ウ山あまね」っていう信頼はもうできてると思いますよ。
ウ山:ありがたいですが、そういうある種リスナーに甘えてる態度はあんまり自分としては取りたくないなって思いますね。もう本当に、「そこはちゃんとジャッジしてくれていいよ、ただ俺も好きにやるよ」という。そういう腹のくくり方ができてるっていう感じですね。頑張ります。
raytrekのサイトでのインタビューはこちら
category:FEATURE
tags:ウ山あまね
RELATED
-
2023/01/16
ウ山あまねが新曲「Ghostyard」をリリース
アートワークはUtaeが手掛けた 2022年9月にリリースした1stアルバム『ムームート』が話題となったシンガー/プロデューサー・ウ山あまねが新曲「Ghostyard」をリリース。 J-POPの新たな可能性を模索し続けるウ山あまね。最新曲「Ghostyard」は、ハイパーエクスペリメンタルで、ギターロックグリッチポップス。楽曲のミックス/マスタリングはウ山自身が行い、アートワークはシンガーソングライターのUtaeが担当。これまでにメジャー/インディー問わず様々なアーティストのプロデュースやリミックスをこなしてきた彼のスキルとセンスが詰まった2023年の序章的な作品になっている。 ウ山あまね – Ghostyard Release date : January 16 2023 Stream : https://809.lnk.to/au_Ghostyard タイトル:ウ山あまね “ムームート” Release Party 日程:2023年1月19日(木) 会場:WWW 出演:ウ山あまね / 君島大空(独奏) / Carl Stone / 諭吉佳作/men / 俚謡山脈 時間:OPEN 18:50 / START 18:50 前売:¥3,000 (税込 / オールスタンディング / ドリンク代別) 問合:WWW 03-5458-7685 チケット: 一般発売 / 11月29日(火)19:00 e+ 【https://eplus.jp/uyamaamane0119/】 ※本公演は「ライブハウス・ライブホールにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に基づいた対策を講じ、開催いたします。 チケットのご購入、ご来場の際は「新型コロナウイルス感染拡大予防対策の実施について」を必ずご確認いただき、ご同意の上でチケットのご購入とご来場をお願いいたします。 公演ページ:https://www-shibuya.jp/schedule/015077.php
-
2022/09/23
ウ山あまね、ニューアルバム『ムームート』をリリース
センサイ、カワイイ、グロテスク、ポップネス シンガー/プロデューサー・ウ山あまねによるフルレングス・アルバム『ムームート』がワーナーミュージック内のレーベル〈+809〉よりリリースされた。 春ねむり「Bang (ウ山あまね Remix)」のリリースや、hirihiri、kabanagu、phritz、quoree、yuigotと共に結成したユニット・PAS TASTAでのリリースやライブを重ねるなど活動を活性化しているウ山あまね。シングル「来る蜂」「Hiuchiishi」を含む全8曲入りのアルバム作品は、繊細で、可愛くて、グロテスクにも聴こえるサウンド、そして何よりもポップネスが溢れる「歌」が紡ぎ出されている。 楽曲のミックスはウ山あまね自身が行い、マスタリングは電気グルーヴや七尾旅人、フィッシュマンズなどをはじめ多岐にわたる作品を手掛けるkimken studioの木村健太郎が担当。またアルバムのアートワークは韓国を拠点に活動するアーティストであるJun seo Hahmが制作し、作品の世界観を視覚的に具現化することに成功している。 ウ山あまね – ムームート Label : +809 Release date : 23 September 2022 Artwork : Jun seo Hahm Stream : https://809.lnk.to/au_mumuto Tracklist 1. いたるところ 2. 来る蜂 3. タペタ 4. デン 5. ランドリー 6. Hiuchiishi 7. 粉 8. キチュンシツン
-
2022/11/29
ウ山あまね、アルバム『ムームート』のリリースパーティをWWWにて開催
「粉」と「デン」のビジュアライザー公開 ウ山あまねが、2022年9月にリリースしたアルバム『ムームート』のリリースパーティを2023年1月19日(木) WWWにて開催。 リリースパーティに出演するのは、現在合奏形態によるワンマンツアーを開催中の君島大空(独奏)、 現在中京大学工学部 メディア工学科の教授を務めるCarl Stone、 艶のある伸やかな歌声で注目を集めるSSW 諭吉佳作/men、 日本各地の民謡を収集/リサーチし、CDやレコードの再発を手掛けるムード山+TAKUMI SAITOによるDJユニット俚謡山脈の4組が出演。フライヤーデザインは中屋辰平が手がけた。チケットは只今より販売開始。 また、ウ山あまねのYouTubeチャンネルから、アルバム収録曲の「粉」と「デン」のビジュアライザーが公開。 タイトル:ウ山あまね “ムームート” Release Party 日程:2023年1月19日(木) 会場:WWW 出演:ウ山あまね / 君島大空(独奏) / Carl Stone / 諭吉佳作/men / 俚謡山脈 時間:OPEN 18:50 / START 18:50 前売:¥3,000 (税込 / オールスタンディング / ドリンク代別) 問合:WWW 03-5458-7685 チケット: 一般発売 / 11月29日(火)19:00 e+ 【https://eplus.jp/uyamaamane0119/】 ※本公演は「ライブハウス・ライブホールにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に基づいた対策を講じ、開催いたします。 チケットのご購入、ご来場の際は「新型コロナウイルス感染拡大予防対策の実施について」を必ずご確認いただき、ご同意の上でチケットのご購入とご来場をお願いいたします。 公演ページ:https://www-shibuya.jp/schedule/015077.php ウ山あまね – ムームート Label : +809 Release date : 23 September 2022 Artwork : Jun seo Hahm Stream : https://809.lnk.to/au_mumuto Tracklist 1. いたるところ 2. 来る蜂 3. タペタ 4. デン 5. ランドリー 6. Hiuchiishi 7. 粉 8. キチュンシツン
FEATURE
- 2025/07/10
-

-
ゆっくりと記憶が蘇り、また消えていく|「AVYSS Chain」VLOG公開
雨と私の夢とファイアファイア more
- 2025/07/08
-

-
iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」に出演するバンドメンバー発表
iVy コンテンポラリー・パーク・オーケストラ♪としての演奏も披露
more
- 2025/06/18
-

-
iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」がWWWにて開催
1stアルバム『混乱するアパタイト』CD版発売決定 more